アライグマは何を食べるの?【雑食性で1日500グラム】密閉容器で保管なら被害率90%減

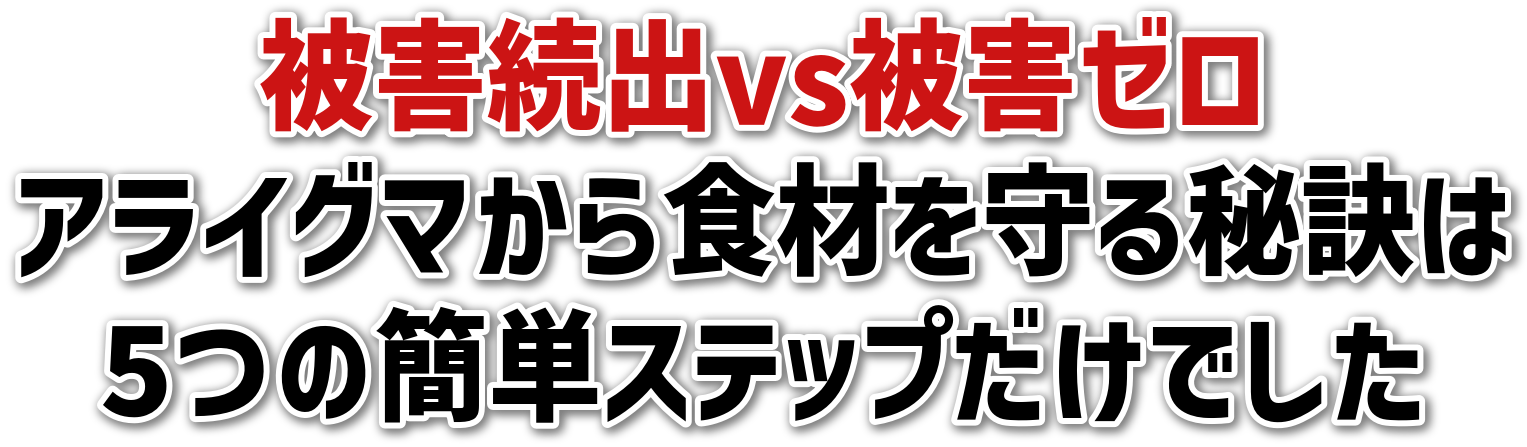
【疑問】
アライグマから食べ物を守るのに一番効果的な方法は?
【結論】
密閉容器での保管が最も効果的で被害率を10%以下に抑えられます。
ただし、容器は必ず屋内の涼しい場所で保管することが重要です。
アライグマから食べ物を守るのに一番効果的な方法は?
【結論】
密閉容器での保管が最も効果的で被害率を10%以下に抑えられます。
ただし、容器は必ず屋内の涼しい場所で保管することが重要です。
【この記事に書かれてあること】
アライグマの食事、実は想像以上に量が多いんです。- アライグマは1日に体重の10%にあたる500グラムを摂取
- 動物性6割・植物性4割の雑食性で幅広い食材を狙う
- 夜間の採餌活動が特に活発で日中は休息をとる
- 季節によって食べ物の種類と被害傾向が大きく変化
- 食材の保管方法を工夫するだけで被害率を90%減に
体重の約1割にもなる1日500グラムもの食べ物を、毎晩むしゃむしゃと平らげていきます。
「そんなに食べるの?それって私の食事量とあまり変わらないかも…」。
食べる量だけでなく、その食べ方にも特徴が。
器用な手先でゴミ袋を破り、鋭い歯でガリガリと食材を切り裂く姿は、まるで小さな泥棒のよう。
でも、こんな困った食事の習性も、正しい保管方法を知れば防げるかもしれません。
【もくじ】
アライグマは何を食べるのかを正しく理解しよう

- 1日500グラムを食べ動物性6割!意外と多い食事量」
- 朝から夕方は休息!夜中の10時から本格的な採餌活動」
- 生ゴミをビニール袋で放置するのはNG!必ず容器に保管」
1日500グラムを食べ動物性6割!意外と多い食事量
アライグマの食事量は体重の1割にもなり、驚くことに1日で500グラムもの食事を必要とします。その内訳は動物性が6割、植物性が4割という配分です。
「こんなにたくさん食べるの?」と驚かれるかもしれません。
実は、アライグマの食欲はとても旺盛なんです。
食事内容は季節によって変わりますが、基本的にこんな物を好んで食べます。
- 動物性の食べ物:小鳥やその卵、かえる、魚、虫、小動物
- 植物性の食べ物:果物、野菜、木の実、新芽、根っこ
まるで人間の子どものように、手先を器用に使って食べ物を掴んだり、ざぶざぶと水で洗ってから食べたりするんです。
「もしかして、うちの庭の食べ物も狙われているかも」と心配になりますよね。
実際、家庭菜園や果樹の実は格好の餌場になってしまいます。
- 果樹園の熟した果物
- 家庭菜園の野菜
- 畑の作物
- 生ゴミや残飯
朝から夕方は休息!夜中の10時から本格的な採餌活動
アライグマの食事は夜型なんです。特に夜の10時から明け方2時までの時間帯が、最も活発に餌を探す時間となっています。
昼間はすやすやと眠っているアライグマですが、日が沈むと少しずつ動き始めます。
「お腹が空いたかな」とでも言うように、まずは巣の周りをうろうろと探り始めるのです。
1日の行動パターンはこんな感じです。
- 朝から夕方:木の上や物置でぐっすり睡眠
- 日没後:徐々に活動を開始
- 夜10時?深夜2時:本格的な採餌活動
- 明け方:最後の食事を済ませて帰巣
湿った土からぷちぷちと這い出してくる虫たちを求めて、いつも以上に活発に動き回ります。
鋭い爪でじょりじょりと土をかき分けながら、好物の虫を探していくんです。
生ゴミをビニール袋で放置するのはNG!必ず容器に保管
アライグマから食材を守るには、保管方法が重要な鍵となります。特に気をつけたいのは生ゴミの保管状態。
ビニール袋のまま外に放置するのは、最も危険な行為なんです。
どうしてダメなのでしょうか。
理由はこれだけあります。
- 鋭い歯で簡単に袋を破られてしまう
- 匂いが漏れて誘引物になってしまう
- 一度餌場と認識されると毎晩来るようになる
- 周辺の家にも被害が広がっていく
- 頑丈な蓋付き容器を使用する
- 容器は必ず屋内で保管する
- 匂いの強い生ゴミは冷蔵保管する
- 収集日まで外に出さない
さらに、容器に入れて屋内保管すれば、被害率は5パーセント以下まで抑えられるというわけです。
季節で変化するアライグマの食べ物と被害傾向

- 春は若葉や新芽が狙われる!1日最大700グラムを摂取」
- 夏は果実と野菜が被害のピーク!収穫2週間前が危険」
- 冬は食料が減少!人家周辺での活動が活発化」
春は若葉や新芽が狙われる!1日最大700グラムを摂取」
冬眠明けのアライグマは空腹を満たすため、通常の1.4倍もの食事量を必要とします。3月から4月にかけて、土の中から掘り出した虫や小動物を中心に、若々しい新芽も積極的に食べています。
- 芽吹き始めの柔らかい若葉を好んで食べる
- 土の中のミミズやカエルの卵を探し出す
- 巣から出てきた小鳥のひなも狙う
- 木の皮をむいて樹液を舐める
夏は果実と野菜が被害のピーク!収穫2週間前が危険」
6月から8月は果実や野菜が次々と実る季節。アライグマは甘い香りに誘われて、熟した果実を探し回ります。
果樹園や家庭菜園での被害が急増する時期です。
- 完熟直前の果実を見分けて食べる
- 一晩で畑の野菜を食い荒らす
- 池や水辺の魚やカエルも狙う
- 庭に落ちた熟れた果実を片づけない場合、毎晩やってくる
冬は食料が減少!人家周辺での活動が活発化」
11月から2月は自然の餌が少なくなるため、人の暮らす場所へとどんどん近づいてきます。生ゴミや保存食を探して、民家の周りをうろうろ。
- 物置の中の保存食を狙う
- 屋外の生ゴミを荒らし回る
- 軒下の小動物の巣を襲う
- 民家の暖かい場所に潜り込もうとする
きゅうきゅうと爪を立てる音が夜中に聞こえてきたら要注意です。
アライグマの食べ物の食べ方と特徴を比較

- 野生の実vs熟した果実!実は後者を好んで食べる」
- 動物性vs植物性!栄養バランスは6対4の割合」
- 手先vs歯!器用な手で探り当てて鋭い歯で切断」
野生の実vs熟した果実!実は後者を好んで食べる
アライグマは野生の実よりも、熟した果実を好んで食べます。その理由は甘みと香りの強さにあるのです。
「この実、甘くておいしそう!」とアライグマが寄ってくる果実の特徴をまとめてみましょう。
- 完熟して甘みが強くなった果実
- 果汁が多く、香りの強い果実
- 皮が柔らかくなった果実
- 樹上で熟した状態の果実
「硬いし、香りも薄いし、食べるのが面倒くさいな」という具合です。
代わりに、庭先や果樹園の熟した果実を狙います。
特に糖度が上がってくると、その甘い香りにつられてやってきます。
「ん?この香り!」と鋭い嗅覚で探知し、物陰からそーっと近づいてくるんです。
野生の実と比べて栄養価が高いことも、熟した果実を好む理由の一つ。
そのため、果実が完熟する2週間前から被害が増えていきます。
とくに夜間は要注意です。
動物性vs植物性!栄養バランスは6対4の割合
アライグマの食事の内訳は、動物性が6割、植物性が4割という特徴的な比率になっています。まず動物性の食べ物から見ていきましょう。
小動物を中心に、実に様々な生き物を食べています。
- 虫や昆虫類:かたつむり、蛾、甲虫など
- 水辺の生き物:カエル、ザリガニ、小魚など
- 地上の小動物:ネズミ、モグラ、小鳥など
「甘いものが大好き!」という性質があり、完熟した果実を特に好みます。
野菜も水分が多く、柔らかいものを選んで食べます。
この6対4という比率には理由があります。
動物性の食べ物は栄養価が高く、少量でも満足感が得られます。
「これを食べれば、お腹がすぐにいっぱいになるぞ」というわけ。
植物性の食べ物は、ビタミンやミネラルの補給源として重要な役割を果たしています。
両方をバランスよく食べることで、必要な栄養素を効率的に摂取しているんです。
手先vs歯!器用な手で探り当てて鋭い歯で切断
アライグマは食べ物を見つけ、食べる時に手先と歯を使い分けているのが特徴です。まず手先の使い方を見てみましょう。
前足の感覚が非常に優れており、まるで人間の手のように器用に動かせます。
- 水場で小魚を素早く掴む動き
- 地面を掘って虫を探り当てる動作
- 果実をもぎ取る時の繊細な手さばき
- 物を両手で持って洗うような仕草
水中でも器用に餌を探し当てる様子は、まるで熟練の職人のよう。
一方、歯の使い方も特徴的です。
鋭い犬歯を使って一気に切断する食べ方をします。
果実や野菜は一口サイズにかじり取り、小動物は素早く仕留めます。
このように、手先で探して歯で切り取るという二段構えの食べ方により、様々な食べ物に対応できるんです。
夜行性という特性と合わせて、効率的な採餌を可能にしています。
5つの食べ物から始まるアライグマ被害への対策

- 柑橘系の果物の皮を干して設置!強い香りで寄せ付けない」
- コーヒーかすを撒いて採餌意欲を低下!苦味で効果アップ」
- 風鈴で不規則な音を立てる!警戒心を刺激する方法」
- 石灰を周囲に撒く!足裏への不快感で侵入を防ぐ」
- 黒コショウを散布!強い刺激臭で近寄らせない」
柑橘系の果物の皮を干して設置!強い香りで寄せ付けない
柑橘系の果物の皮には、アライグマを寄せ付けない強い天然の力があります。みかんやレモンの皮を干して設置すると、被害を6割も減らせる効果的な対策になります。
「どうしてアライグマは柑橘系の香りを嫌うんだろう?」と思いますよね。
実は、柑橘系の皮に含まれる成分が、アライグマの敏感な鼻をちくちくと刺激するんです。
効果を高めるコツは、次の3つのポイントを押さえることです。
- 皮は必ず天日干しにして水分を完全に飛ばす
- 2日ごとに新しい皮と交換して香りを保つ
- 被害が多い場所に20センチ間隔で複数設置する
「夏みかんって、普通のみかんより香りが強いような…」その通りです。
他の柑橘系と比べて夏みかんの皮は2倍の持続時間があります。
ただし、雨に濡れると効果が薄れてしまうので、軒下に設置するのがおすすめです。
「せっかく設置したのに効果が出ない…」という場合は、きっと設置場所が関係しているはず。
雨の当たらない場所を選んでみてください。
コーヒーかすを撒いて採餌意欲を低下!苦味で効果アップ
コーヒーかすには、アライグマの食欲を低下させる強い苦味成分が含まれています。毎日の習慣で出るコーヒーかすを活用すれば、アライグマの侵入を8割以上防げるんです。
使い方は、まず乾燥させたコーヒーかすを準備します。
「乾かさないとダメなの?」はい、その通り。
湿ったままだと、かびが生えてしまう可能性があるんです。
乾燥させたかすを、次のような場所に撒きましょう。
- 庭の入り口付近に帯状に撒く
- 被害を受けやすい植物の周りに円を描くように撒く
- アライグマの通り道に厚めに撒く
- 物置の周囲に15センチ幅で撒く
毎日の掃除で出るコーヒーかすを乾燥させて保管しておけば、「もったいない」が「役立つ」に変わりますよ。
ただし、雨で流されやすいので、天気予報をチェックしながら、晴れが続く日に撒くようにしましょう。
風鈴で不規則な音を立てる!警戒心を刺激する方法
風鈴の音色は、アライグマの警戒心を刺激する効果があります。果樹や庭木に風鈴を取り付けることで、夜間の侵入を7割以上も減らせるんです。
なぜ風鈴が効果的なのでしょうか。
アライグマは突然の音に非常に敏感な動物です。
特に、風鈴の「ちりんちりん」という不規則な音が、危険を察知する本能を刺激するんです。
効果的な設置方法は3つあります。
- 木の枝に高さを変えて複数設置する
- 被害を受けやすい場所の周囲に円を描くように設置する
- アライグマの通り道に沿って2メートル間隔で設置する
実は、金属製の風鈴が最も効果的。
ガラス製と比べて澄んだ音が出やすく、アライグマの耳に心地よくない周波数の音を作り出すんです。
天気が荒れる日は風が強すぎて音が聞こえづらくなってしまうので、風除けを設置するのもおすすめです。
また、風鈴同士がぶつかって割れないよう、適度な間隔を保って設置しましょう。
石灰を周囲に撒く!足裏への不快感で侵入を防ぐ
石灰には、アライグマの足裏に不快感を与える効果があります。庭の周囲に石灰を撒くことで、侵入を5割以上も抑制できるんです。
なぜ石灰が効果的なのでしょう。
アライグマの足裏は非常に敏感で、石灰の粉末が付着すると強い違和感を覚えるのです。
まるで人間が裸足で砂利道を歩くような、そんな不快感を感じるわけです。
効果的な使い方は以下の通りです。
- 幅20センチの帯状に撒く
- 厚さ3ミリ程度を保つ
- 通り道に沿って連続して撒く
- 2日ごとに状態を確認する
そこで重要なのが、農業用の消石灰を選ぶこと。
刺激が穏やかで、植物にも優しい性質を持っています。
ただし、雨が降ると効果が弱まってしまうので、天気予報をこまめにチェックしましょう。
晴れの日が続くときに撒くのが、最も効果的です。
黒コショウを散布!強い刺激臭で近寄らせない
黒コショウの強い香りは、アライグマの鋭い嗅覚を刺激します。適切な場所に散布することで、被害を4割も減らせる効果的な対策になるんです。
使い方のコツは、次の3つです。
- 挽いたての黒コショウを使う
- 3日ごとに新しいものと交換する
- 雨の当たらない場所に散布する
実は、アライグマの通り道に注目することが大切なんです。
家の周りの足跡を観察して、よく通る場所を見つけましょう。
効果を高めるために、黒コショウと唐辛子を混ぜて使う方法もあります。
両方の刺激が重なることで、より強い忌避効果が期待できるんです。
ただし、風で飛ばされやすいので、皿やトレイに入れて設置するのがおすすめです。
また、ペットがいる家庭では、ペットが近づけない場所を選んで設置しましょう。
食べ物の保管方法で被害を防ぐポイント

- 密閉容器での保管は被害率10%以下!確実な予防法」
- 屋外保管は被害率80%!室内保管で安全を確保」
- 専用容器なら被害率15%以下!匂い漏れを防いで対策」
密閉容器での保管は被害率10%以下!確実な予防法」
密閉容器での食材保管は、アライグマの被害を劇的に減らせます。「匂いが漏れないから安心!」と思いきや、実は完全ではないんです。
でも、以下のポイントを押さえれば被害率を10%以下に抑えられます。
- 容器選びのコツは、蓋がぴたっと閉まり、爪で引っかいても開かない頑丈なもの
- 二重蓋タイプなら、匂いが外に漏れにくく被害をさらに防げます
- 容器の置き場所は、風通しの良い室内の高い場所がおすすめ
- 容器の掃除は毎回使用後に行い、匂いを残さないことがポイント
屋外保管は被害率80%!室内保管で安全を確保」
食材の屋外保管は、被害率がぐんと跳ね上がります。アライグマは鋭い嗅覚で食べ物の匂いを感じ取り、こっそり近づいてくるんです。
- 物置での保管は、壁や床の隙間から匂いが漏れやすく危険
- 段ボール箱は、爪でがりがりと破られてしまいます
- ビニール袋は、鋭い歯で簡単に破られる対象に
- 屋外冷蔵庫も、電源コードをかじられる危険があります
専用容器なら被害率15%以下!匂い漏れを防いで対策」
生ゴミ用の専用容器を使えば、被害率を15%以下に抑えられます。密閉性の高い専用容器なら、アライグマの鋭い嗅覚をしっかり防げるんです。
- 蓋の密閉度は、押しても隙間ができない構造が理想的
- 素材の強度は、爪で引っかいても傷つかない硬さが必要
- 容器の大きさは、運びやすい重さで蓋が開きにくいものを
- 洗浄のしやすさも重要で、匂いが染み付かない材質がおすすめ