夜行性のアライグマはいつ活動する?【日没後2時間が最も活発】月齢と季節で変化する行動時間に要注意!

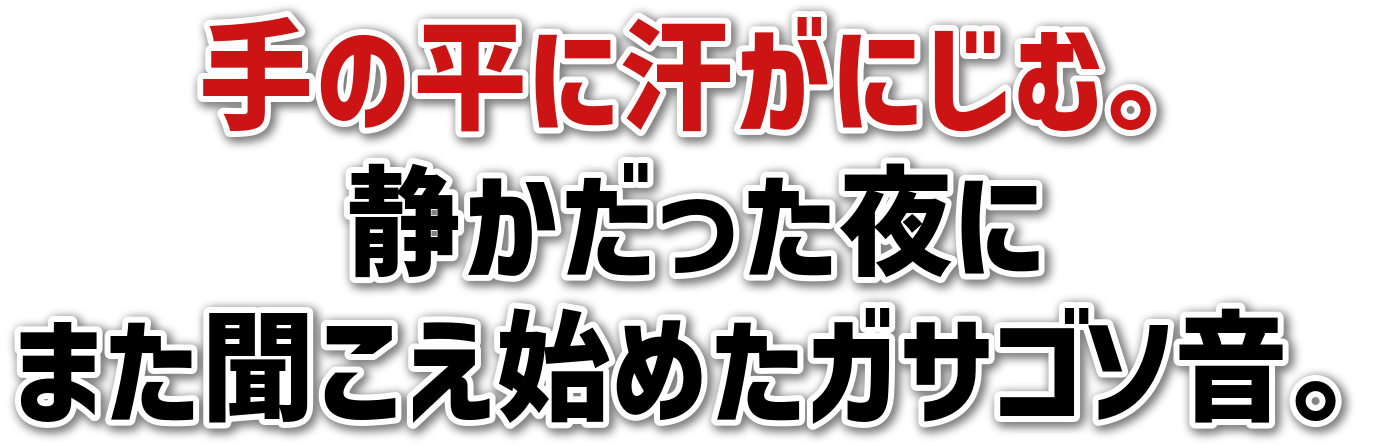
【疑問】
アライグマの活動時間って本当に夜だけなの?
【結論】
アライグマは日没後30分から活動を開始し、特に日没後2時間が最も活発になります。
ただし、繁殖期や空腹時には昼間でも2時間程度の活動をすることがあります。
アライグマの活動時間って本当に夜だけなの?
【結論】
アライグマは日没後30分から活動を開始し、特に日没後2時間が最も活発になります。
ただし、繁殖期や空腹時には昼間でも2時間程度の活動をすることがあります。
【この記事に書かれてあること】
家の周りでアライグマの被害に遭っているけれど、「いつ対策をすれば良いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?- アライグマの最も活発な活動時間帯は日没から2時間後
- 夏と冬では活動開始時刻に4時間もの差が生じる
- 月の満ち欠けで活動時間帯が大きく変動
- 効果的な対策には5つの時間帯別アプローチが重要
- 他の野生動物と比べて行動範囲が2倍以上の広さ
実は夜行性のアライグマには活動のピーク時間があるんです。
日没から30分後に活動を開始し、その2時間後には最も活発に行動する時間帯を迎えます。
さらに、月の満ち欠けや季節によっても活動時間が変化するため、効果的な対策にはこれらの特徴を知ることが重要です。
この記事では、アライグマの行動パターンを徹底解説していきます。
【もくじ】
夜行性のアライグマの活動時間帯

- 日没後2時間が「アライグマの活動ピーク時間帯」に!
- 日没から30分後に行動開始「動き出しのタイミング」
- 深夜0時までの対策は「逆効果になる失敗例」に注意!
日没後2時間が「アライグマの活動ピーク時間帯」に!
アライグマが最も活発に行動するのは、日没から2時間後の時間帯です。「いつ対策すれば効果的なんだろう?」と悩む方は多いのですが、この時間帯を把握しておくことが重要です。
日没から2時間後というのは、アライグマにとって絶好の行動時間なんです。
辺りはすっかり暗くなり、人の活動も少なくなってきた頃合い。
「よーし、そろそろ行動開始だぞ!」とばかりに、巣から飛び出してきます。
この時間帯の特徴をより詳しく見てみましょう。
- 視界が暗くなり、目が活発に働き始める
- 巣から半径2キロメートルの範囲を素早く移動
- 餌場を次々と探索する行動が顕著に
- 手先の感覚が最も鋭くなり、物を掴む動作が活発に
「ガサゴソ」「カサカサ」という物音が聞こえてきたら要注意。
その正体は、活動のピークを迎えたアライグマかもしれません。
日没から30分後に行動開始「動き出しのタイミング」
アライグマは日没からちょうど30分後に活動を始めます。この時間はまだ薄明かりが残っているため、慎重に行動する時間帯なんです。
最初の動きは実にゆっくりとしています。
巣の中でじっとしていた体を、少しずつ動かし始めるんです。
「周りは安全かな?」「人はいないかな?」と、辺りの様子を細かくうかがいながら、そーっと這い出してきます。
この時間帯の動きの特徴を見てみましょう。
- まず耳を動かし、周囲の物音を確認
- 鼻先を上げて、空気の匂いを慎重に確認
- 尻尾を低く下げ、警戒した姿勢で移動
- 身を隠せる場所を確認しながらゆっくり前進
この時間帯は警戒心が最も強く、人の気配を感じると素早く身を隠してしまいます。
深夜0時までの対策は「逆効果になる失敗例」に注意!
深夜0時を過ぎてからの対策は、実は大きな失敗のもとです。なぜなら、この時間帯にはアライグマの活動はすでにピークを過ぎているからです。
夜中の12時までには、アライグマはもう十分に餌を確保しています。
「お腹いっぱいだから、そろそろ休もうかな」という具合に、活動が徐々に落ち着いてくる時間帯なんです。
この時間帯の特徴的な行動をまとめてみましょう。
- 餌場の探索行動が大幅に減少
- 水場で手を洗う行動が増加
- 巣に向かって戻り始める個体が出現
- 動きがのろのろと緩慢に
対策は日没後2時間以内に済ませることが、最も効果的なんです。
季節による活動時間の違い

- 夏と冬で4時間の「活動開始時刻の差」が発生!
- 繁殖期は活動時間が「2時間以上延長」の傾向に
- 雨の日は活動開始が「2時間ほど遅延」の特徴
夏と冬で4時間の「活動開始時刻の差」が発生!
季節によってアライグマの活動開始時刻は大きく変化し、夏と冬では最大で4時間もの差が生まれます。夏は日没が遅いため、活動開始は午後8時頃からスタート。
一方、冬は日没が早まるため午後4時頃から動き出すんです。
この時間差を理解していないと、対策のタイミングを見誤ってしまいます。
- 夏の活動開始:午後8時頃から活発に行動
- 冬の活動開始:午後4時頃から行動開始
- 春秋の活動開始:午後6時頃がスタート時間
繁殖期は活動時間が「2時間以上延長」の傾向に
アライグマは春の繁殖期になると活動時間が通常より2時間以上も長くなります。これは子育てに必要な栄養を確保するためです。
通常なら夜中で終わる活動も、繁殖期は夜明け前まで続くことも。
この時期は餌を求める行動が活発になり、住宅への侵入を試みる回数も増えてしまいます。
- 活動時間が2時間延長して深夜まで続く
- 餌を求める行動が普段の2倍以上に増加
- 夜明け前までうろうろと動き回る習性
雨の日は活動開始が「2時間ほど遅延」の特徴
雨天時はアライグマの行動パターンが大きく変化します。普段の活動開始時刻から2時間ほど遅れて活動を始めるんです。
これは雨音で周囲の様子が分かりにくく、身の安全を確保しづらいため。
その分、雨が上がった後は通常以上に活発に動き回ります。
- 雨の日は活動開始が2時間遅れにシフト
- 雨上がり後はいつもより活発に行動
- 深夜まで執着して餌を探し回る傾向
他の動物との行動範囲の比較

- タヌキvsアライグマ「行動範囲は2倍の差」あり!
- 猫vsアライグマ「活動範囲は6倍以上」の開き
- キツネvsアライグマ「行動時間の集中度」の違い
タヌキvsアライグマ「行動範囲は2倍の差」あり!
アライグマはタヌキの2倍の範囲を動き回ります。アライグマは一晩で最大4キロメートルも移動するのに対し、タヌキは2キロメートルほどしか移動しないのです。
「なんでアライグマの方が広いんだろう?」と思われるかもしれません。
その理由は、アライグマの身体能力の高さにあります。
ぴょんぴょんと跳びはねながら垂直に1メートル以上も跳び上がり、がりがりと爪を立てながら5メートルの高さまで木に登る力を持っています。
アライグマの行動範囲の広さは、次のような特徴があります。
- 高い運動能力を活かして、建物の屋根から屋根へと渡り歩く
- 鋭い嗅覚で半径2キロメートル以内の餌場を記憶している
- 木の上を自由に移動して近道を作り出すことができる
- 縄張り意識が強く自分の餌場を広げようとする習性がある
猫vsアライグマ「活動範囲は6倍以上」の開き
野良猫の行動範囲はおよそ300メートルなのに対し、アライグマは2キロメートル以上の範囲を縄張りとしています。その差は実に6倍以上にもなるのです。
アライグマが猫よりも広範囲を移動する理由は、食べ物の確保方法にあります。
猫は決まった餌場に通うことが多いのですが、アライグマは毎晩のようにふらふらと新しい餌場を探し回ります。
アライグマの行動パターンには以下のような特徴が見られます。
- 複数の餌場を掛け持ちして巡回する
- 住宅地の中をジグザグに移動しながら探索する
- 見つけた餌場を毎日違う時間に訪れるため予測が難しい
- 餌場までの最短ルートを覚える学習能力が高い
キツネvsアライグマ「行動時間の集中度」の違い
キツネは夜通し断続的に活動するのに対し、アライグマは日没後の4時間に活動を集中させます。この行動時間の違いが、両者の活動範囲に大きな影響を与えているのです。
キツネはぽつぽつと少しずつ行動範囲を移動していくため、一晩の総移動距離は長くなります。
一方、アライグマは短時間で効率的に餌を探し回る習性があります。
アライグマとキツネの行動の違いは、次のような特徴として現れます。
- アライグマは集中的に広範囲を素早く移動する
- キツネは同じ場所に長時間とどまることがある
- アライグマは複数の餌場を短時間で巡回する
- キツネは一か所の餌場で時間をかけて採餌する
アライグマ対策に効果的な5つの時間帯活用法

- 日没2時間前からの「段階的な明るさ調整」が有効!
- 活動開始30分前の「柑橘系の香り」で撃退
- 月明かりを利用した「不規則な光の動き」作戦
- 活動ピーク時の「自動音声システム」構築法
- 深夜0時前の「最終チェック」で安心確保!
日没2時間前からの「段階的な明るさ調整」が有効!
日没前からの明るさ調整で、アライグマの活動開始時間をずらすことができます。アライグマは光の変化に敏感な生き物です。
「夕方になったから動き出そう」という行動のきっかけを、私たちの工夫で少しだけ混乱させることができるんです。
具体的な手順をご紹介します。
- 日没の2時間前から、庭や物置の照明を徐々に明るくしていきます
- 30分おきに明るさを少しずつ強めていきます
- 日没時には通常の2倍の明るさにします
- 活動開始予定時刻までその明るさを維持します
ところが、がばっと明るくすると逆効果。
アライグマが「何かおかしい!」と警戒心を強めて、むしろ用心深く行動するようになってしまいます。
まるで夕暮れがゆっくり進むかのような、自然な明るさの変化を演出することがコツ。
そうすることで「もう少し待とう」という判断を誘導できるというわけです。
活動開始30分前の「柑橘系の香り」で撃退
アライグマの活動開始時刻の30分前に柑橘系の香りを仕掛けることで、その場所への接近を防ぐことができます。アライグマは鼻がとても良く効く動物です。
特に柑橘系の香りを嫌う習性があり、この特徴を利用した対策が効果的なんです。
具体的な方法を見てみましょう。
- みかんやレモンの皮を細かくちぎって準備します
- 活動開始30分前に、よく通る場所にまんべんなく配置します
- 2時間後には必ず回収して、翌日また新しいものと交換します
香りが弱くなった古い皮は、逆に「食べ物があるかも」という誤ったメッセージを送ってしまうことがあるのです。
皮をちぎる時は、ぷちぷちと破裂する油は手につけないように注意。
アライグマの鋭い嗅覚なら、人の匂いが少しでも混ざっているのを感じ取ってしまうからです。
新鮮な柑橘の香りだけを、すーっと漂わせることがポイントになります。
月明かりを利用した「不規則な光の動き」作戦
月の光を反射させる仕掛けを設置することで、アライグマに不安を与え、接近を防ぐことができます。月明かりは自然の光なので、アライグマも警戒心を解きやすいもの。
でも、その光がふわふわと不規則に動くと、とたんに用心深くなるんです。
具体的な設置方法をご紹介します。
- 反射する素材を小さな風車の羽に取り付けます
- 庭の複数の場所に分散して設置します
- 風で動く角度で微妙な光の変化を作ります
ですが、月明かりを利用する方法なら、まぶしすぎる心配はありません。
自然の風に任せて、ゆらゆらと揺れる光の動き。
アライグマからすれば「何かいるのかな?」「危ないかも?」という不安がよぎります。
そんな微妙な心理を刺激することで、縄張りに入ることをためらわせる効果があるというわけです。
活動ピーク時の「自動音声システム」構築法
アライグマの活動がピークを迎える時間帯に、自動で音を鳴らす仕組みを作ることで、警戒心を刺激できます。人の気配を感じると用心深くなるアライグマ。
この特徴を利用して、まるで人がいるかのような錯覚を与えるのです。
効果的な音の出し方を見てみましょう。
- ラジオを小さな音量で流します
- 時間を決めて不規則に音が変わるように設定します
- 人の話し声が中心の番組を選んで流します
しかし、それは逆効果。
騒音に慣れてしまうと、かえって警戒心が薄れてしまうのです。
ささやくような小さな音で、ぼそぼそと人の声が聞こえる状況。
それこそが、アライグマの警戒本能を刺激する絶妙な仕掛けになるんです。
深夜0時前の「最終チェック」で安心確保!
深夜0時前の見回りで、アライグマ対策の効果を確認することができます。この時間帯は、アライグマの活動がいったん落ち着く時期。
対策の成果を見極めるのに最適なタイミングなんです。
チェックポイントを確認しましょう。
- 柑橘系の香りがまだ残っているか確認します
- 反射板の向きが適切な角度か点検します
- 音声装置が正しく作動しているか確かめます
- 新しい足跡や荒らされた形跡がないか調べます
でも心配いりません。
室内から窓越しに、双眼鏡を使って確認するだけでも十分なんです。
もしアライグマの姿を見つけても、決して外に出ないようにしましょう。
ぴくりとも動かず、そっと様子を見守ることが大切です。
翌日の対策に活かせる貴重な観察チャンスになるというわけ。
月齢と天候による活動変化の注意点

- 満月の夜は「警戒心と大胆さ」が同時に増加!
- 新月の夜は「活動時間が3時間延長」の傾向
- 雨天時は「活動開始が遅れる」ので要注意!
満月の夜は「警戒心と大胆さ」が同時に増加!
満月の夜は、アライグマの行動が大きく変化します。「月明かりが強いから活動が減るはず」と思いがちですが、それは大きな勘違い。
月の明かりで警戒心が高まり活動時間は2時間ほど短くなりますが、その分行動が大胆になってしまうんです。
「家の中なら安全」と考えるのか、建物への侵入が増える傾向にあります。
特に気をつけたい点は以下の3つ。
- 建物の隙間や換気口からの侵入が1.5倍に増加
- 屋根裏や物置への営巣行動が活発化
- 通常より高い場所を好んで移動
新月の夜は「活動時間が3時間延長」の傾向
新月の夜は、暗闇に紛れてぐんぐん活動範囲を広げます。通常より活動時間が3時間も延長され、被害が広範囲に及ぶ危険性が高まります。
「暗いから見つからない」と考えるのか、より大胆な行動をとる特徴が。
活動の特徴は次の3つです。
- 巣から2キロ以上離れた場所まで移動
- 餌場の探索時間が2倍に増加
- 複数の場所を同じ夜に荒らす傾向
雨天時は「活動開始が遅れる」ので要注意!
雨の日は活動開始が2時間ほど遅れるため、油断は禁物です。じとじとした雨が止むのを待って行動を開始し、深夜まで活発に動き回ります。
「雨の日は出てこない」と思っている人も多いのですが、それは大きな間違い。
むしろ次のような特徴的な行動が見られます。
- 雨宿りできる建物への侵入が増加
- 水たまりで手を洗う時間が長くなる
- 餌場に留まる時間が2倍に