アライグマの繁殖期と繁殖力がすごい【年2回出産で1度に4匹】半年で新たな繁殖期に突入!

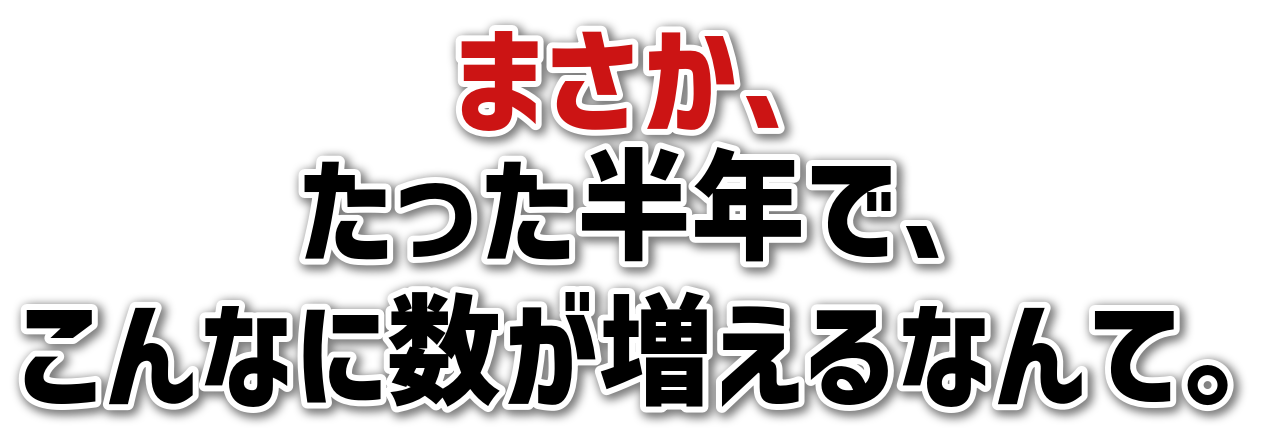
【疑問】
アライグマの繁殖力はどれくらい高いの?
【結論】
年2回の繁殖期があり1回の出産で最大6匹を産むため、1年で最大12匹まで増える可能性があります。
ただし、子どもは生後10か月で性成熟に達するため、2年目には個体数が急激に増加する危険性があります。
アライグマの繁殖力はどれくらい高いの?
【結論】
年2回の繁殖期があり1回の出産で最大6匹を産むため、1年で最大12匹まで増える可能性があります。
ただし、子どもは生後10か月で性成熟に達するため、2年目には個体数が急激に増加する危険性があります。
【この記事に書かれてあること】
アライグマの繁殖力の高さをご存知ですか?- アライグマは年2回の繁殖期があり、1回の出産で最大6匹の子育て
- 生後6か月で完全に独立し、10か月で次の繁殖が可能に
- 子育て中の母親は巣の周辺で警戒心が極端に高まる
- 市街地は山間部より繁殖率が2倍以上高い傾向
- 繁殖期前の対策で被害の拡大を防止できる
一度見かけただけでも油断は大敵です。
年2回の出産で、1度に4匹もの子どもを産むこの動物は、わずか1年で一家族が20匹以上に増える可能性があるんです。
「まだ1匹だけだから様子見でいいかな」なんて思っていませんか?
実は、生後わずか10か月で次の世代の繁殖が始まり、あっという間に被害が広がってしまうのです。
今のうちに、アライグマの繁殖力と対策方法をしっかり理解しておきましょう。
【もくじ】
アライグマの繁殖期と繁殖力について知っておくべきこと

- 年2回の出産で「1度に4匹の子育て」が基本!
- 生後6か月で「完全に独立」して新しい場所へ!
- 繁殖期は「餌付け厳禁」の警戒が必要!
年2回の出産で「1度に4匹の子育て」が基本!
アライグマは1月下旬と6月下旬の年2回、繁殖期を迎え、1度の出産で平均4匹もの子どもを産みます。まるで子育て名人のように、アライグマのお母さんは子育てのスケジュールをきっちり決めています。
「そろそろ繁殖期かしら」と気温の上昇を感じ取ると、ほっそりした体つきのメスの様子が急に変わります。
繁殖期から出産までの流れを見てみましょう。
- 妊娠期間は63日間でじっくり赤ちゃんを育てます
- 春の出産は4月下旬から5月上旬
- 夏の出産は8月下旬から9月上旬
- 1度に最大6匹まで産むことも
なぜなら、年2回の出産で1年に最大12匹も増える計算になるからです。
赤ちゃんは生まれてすぐは目も開かず、ぷにぷにした状態で母親の世話が必要です。
でも3週間もすると目が開き、すくすくと育ち始めます。
そして2か月ほどで立派な子アライグマに。
「こんなに早く大きくなるの?」と驚くほどの成長速度なんです。
生後6か月で「完全に独立」して新しい場所へ!
アライグマの子どもは、生まれてからわずか6か月で独立してしまいます。まるで人間の子どもの10倍以上のスピードです。
成長の様子を時系列で追ってみましょう。
- 生後1か月で体重が10倍に急成長
- 2か月で固形物を食べ始める
- 3か月で親の半分まで大きく
- 4か月で親とほぼ同じ大きさに
- 6か月で完全独立して新天地へ
「えっ、もう子どもが産めるの?」と思わず声が出てしまいますよね。
そのため、春に生まれた子は年内に成熟して、次の春には自分の子どもを産めるようになります。
ころころと転がるような赤ちゃんが、あっという間に親になってしまうんです。
繁殖期は「餌付け厳禁」の警戒が必要!
繁殖期のアライグマは、普段の2倍近く食べ物を必要とします。そのため、人の生活圏に現れる機会が増えてしまいます。
ここで絶対にしてはいけないのが餌付けです。
「かわいそうだから」と思って一度でも餌を与えると大変なことに。
その理由をご説明します。
- 餌付けされた場所を繁殖地として選ぶ
- 子育ての際も同じ場所に戻ってくる
- 出産後は警戒心が極端に高まる
- 子どもたちも同じ場所に定着する
「この物置、暖かくて居心地がいいわ」とばかりに、家屋に侵入しようとします。
一度でも餌付けされた場所は、まるで実家のように代々受け継がれていくことも。
「最初は1匹だけだったのに」という声をよく耳にしますが、これが急激に増える原因なんです。
アライグマの子育ての特徴と行動パターン

- 母親の行動範囲は「半径100メートル以内」に限定!
- 子育て中は「朝夕2回の授乳時間」が決まっている!
- 子育て期間は「生後4か月で親と同サイズ」まで!
母親の行動範囲は「半径100メートル以内」に限定!
子育て中のアライグマの母親は、巣を中心に半径100メートル以内で行動します。普段は2キロメートルほど動き回るアライグマですが、子育て中は行動範囲がぐっと狭まるんです。
子育ての時期には、次のような特徴的な行動が見られます。
- 巣の周辺をくるくると回りながら餌場を探し続ける
- 子どもが危険にさらされないよう見張りを欠かさない
- 危険を察知するとすばやく巣に戻って子どもを守る
- 巣の近くに人が来ると激しい威嚇行動をとる
子育て中は「朝夕2回の授乳時間」が決まっている!
アライグマの母親は朝と夕方の決まった時間に巣に戻り、子どもに授乳します。この時間帯は特に警戒心が強まり、巣の周辺での活動が活発になります。
授乳のタイミングには、決まったパターンがあるのです。
- 朝は日の出1時間前から授乳を始める
- 夕方は日没直後から授乳を始める
- 1回の授乳は30分程度で終わる
- 授乳前後は巣の周辺を入念に確認する
子育て期間は「生後4か月で親と同サイズ」まで!
アライグマの赤ちゃんは、驚くほど早い速さで成長します。誕生時は目も見えず体重100グラムほどですが、わずか4か月で親と同じくらいの大きさになってしまうんです。
成長の様子は次のような段階を経ます。
- 生後1か月で体重が10倍に増加
- 生後2か月で固形物を食べ始める
- 生後3か月で夜間の単独行動を開始
- 生後4か月で親と同じくらいの大きさに
アライグマの繁殖場所の特徴を比較

- 市街地vs山間部「繁殖率2倍の差」に驚き!
- 古い家屋vs新築「定住率5倍の差」が明確!
- 物置vs屋根裏「子育ての成功率」を比較!
市街地vs山間部「繁殖率2倍の差」に驚き!
市街地は山間部と比べて、アライグマの繁殖率が2倍以上も高くなっています。これは餌が豊富で天敵が少ないという環境が、繁殖に適しているからです。
「こんなに差があるなんて!」と驚かれる方も多いでしょう。
実は市街地には、アライグマの繁殖を後押しする要素がたくさん潜んでいるんです。
- 生ごみや果樹など、豊富な食べ物が年中手に入る
- 犬や猫の餌を食べられる場所が点在している
- キツネやタヌキなどの天敵が少ない
- 電灯で夜でも行動しやすい
「お腹いっぱいで体調もばっちり!」という状態が続くため、繁殖に必要な栄養が十分確保できるというわけです。
また、子育ての成功率も市街地の方が高くなります。
山間部では「子どもが天敵に襲われちゃった…」という事態も珍しくありませんが、市街地ではそんな心配がほとんどないのです。
そのため、生まれた子どもの90パーセント以上が無事に成長できる環境になっているんです。
古い家屋vs新築「定住率5倍の差」が明確!
築20年以上の古い家屋は、新築と比べてアライグマが定住する確率が5倍以上も高くなります。これは古い家屋の方が、アライグマにとって住みやすい特徴をたくさん持っているためです。
「なぜ古い家屋がこんなに好まれるの?」その理由は、建物の特徴にあります。
- 壁や屋根に小さな隙間がたくさんある
- 断熱材が劣化して巣作りの材料になる
- 雨どいや外壁に乗りやすい凹凸がある
- 木材が柔らかくなって爪でひっかきやすい
「ここなら安心して子育てができる!」とアライグマが判断すると、その場所をずっと使い続けようとします。
さらに、古い家屋には断熱材がむき出しになっている場所も。
これがふかふかの巣材として最適なため、アライグマにとっては「理想的な子育て環境」となってしまうのです。
物置vs屋根裏「子育ての成功率」を比較!
アライグマの繁殖場所として、物置と屋根裏では子育ての成功率に大きな違いが出ます。物置は70パーセント程度なのに対し、屋根裏は90パーセント以上と高い成功率を示すのです。
なぜこんなに差が出るのでしょうか。
実は屋根裏には、子育てに適した条件がそろっているんです。
- 人が近づきにくい高さにある
- 雨風を完全に防げる
- 温度変化が少なく安定している
- 逃げ道を複数確保できる
「赤ちゃんが快適に過ごせる場所」として、屋根裏は年間を通じて安定した温度を保っています。
一方、物置は地面に近いため「人が出入りする度にびくびく」という状態に。
また、夏は暑く冬は寒いという温度変化も激しいため、子育ての環境としては屋根裏に及ばないというわけです。
アライグマの繁殖を防ぐ5つの対策方法

- 繁殖期前の「ライト照射作戦」で巣作りを阻止!
- 換気口に「目の細かい金網」で侵入を防止!
- 柑橘系の香りで「繁殖場所として避ける」効果!
- 巣になりそうな場所に「2重の防鳥シート」設置!
- 風見鶏の「動く影」で警戒心を刺激!
繁殖期前の「ライト照射作戦」で巣作りを阻止!
アライグマの繁殖期前の対策として、強力な照明で巣作りを事前に阻止できます。夜行性のアライグマは明るい光を極端に嫌う習性があります。
「こんな明るい場所は子育てに向かないわ」と考えて、別の場所へ移動してしまうんです。
効果的な照明方法には次のようなコツがあります。
- 照射時間は日没後から夜明け前までの間に、2時間おきに10分間ずつ
- 照明は屋根裏や物置の入り口に向けて設置
- 雨の影響を受けない軒下に取り付けるのがおすすめ
- 人感センサー付きの照明なら自動で点灯するので便利
繁殖期の2週間前から始めることで、巣作りの計画段階で「この場所は危険」と判断させることができます。
夜中にぴかっと光る不気味さで、アライグマの警戒心を刺激するわけです。
「もしかして天敵がいるのかも」と感じさせることで、効果的に追い払えます。
換気口に「目の細かい金網」で侵入を防止!
換気口からの侵入を防ぐには、目の細かい金網を二重に設置するのが効果的です。アライグマはわずか3センチの隙間があれば入り込めてしまいます。
「小さな穴なら通れるはず」と、いろいろな場所を探り始めるんです。
金網の設置では、以下の点に気をつけましょう。
- 網目は1センチ以下の細かいものを選ぶ
- 金網と壁の間に隙間を作らないよう端をしっかり固定
- 角の部分は特に丁寧に留める
- 二重に重ねて設置することで噛み切られにくくする
- 定期的に破損がないか点検する
もし動物がいる場合は、夜間に外出している間に設置するのがコツです。
「今まで通っていた道が突然ふさがれた」と気付かれないようにするためです。
金網は耐久性の高いステンレス製がおすすめ。
多少値は張りますが、アライグマの鋭い歯や爪にも負けない頑丈さが魅力です。
柑橘系の香りで「繁殖場所として避ける」効果!
柑橘系の果物の皮を乾燥させて設置すると、アライグマは繁殖場所として避けるようになります。アライグマは鋭い嗅覚の持ち主。
「この場所は子育てに向かない」と判断する基準の一つに、苦手な香りがあるんです。
効果的な設置方法は以下の通りです。
- みかんやレモンの皮を天日干しにする
- 乾燥させた皮を小さな網袋に入れる
- 巣になりそうな場所の周辺に3個以上設置
- 3日おきに新しいものと交換する
- 雨で濡れない場所を選んで設置する
天日干しにすることで香りが凝縮され、アライグマの敏感な鼻をくすぐります。
「この刺激的な香りの場所では、落ち着いて子育てができない」と感じるわけです。
腐らないように定期的な確認も忘れずに。
かびが生えた皮は逆効果になってしまいます。
巣になりそうな場所に「2重の防鳥シート」設置!
防鳥シートを2重に重ねて設置すると、アライグマの巣作りを効果的に防げます。アライグマは肉球が非常に敏感です。
とげとげした触感が苦手で、「この場所は歩きにくい」と感じると、別の場所を探すようになるんです。
防鳥シートの設置には次のようなコツがあります。
- シートの端は隙間なくしっかり固定する
- 2枚を互い違いに重ねて設置する
- シートの向きを変えて凹凸を不規則にする
- 雨どいの周辺は特に丁寧に覆う
- 月1回は破損がないか点検する
「今まで通っていた道が突然ふさがれた」と気付かれると、より危険な場所に移動してしまう可能性があります。
風見鶏の「動く影」で警戒心を刺激!
風見鶏型の回転する装置を設置すると、その動く影でアライグマの警戒心を刺激できます。アライグマは動くものに敏感な動物です。
月明かりに照らされた影が動くと、「この場所には何か危険なものがいる」と感じて警戒するんです。
効果的な設置方法をご紹介します。
- 月光で影ができる高さに設置する
- 風通しの良い場所を選ぶ
- 複数の方向から影が見えるように向きを調整する
- 金属製の軽い素材を選ぶ
- 強風でも外れないよう頑丈に固定する
空を舞う大きな鳥の影は、天敵を連想させやすいのです。
「ここは捕食者のなわばりかもしれない」と感じさせることで、巣作りを諦めさせることができます。
繁殖期のアライグマへの注意と配慮

- 出産直前は「警戒心が最大」になる危険性!
- 子育て中の「巣の撤去」は新たな被害を誘発!
- 近隣との「情報共有」が対策成功のカギ!
出産直前は「警戒心が最大」になる危険性!
妊娠後期のアライグマは、とても警戒心が強くなっています。「このまま巣にしよう」と決めかけた場所でも、人の気配を感じると即座に別の場所へ移動してしまうんです。
- 人が近づくとすぐに逃げ出す習性があり、より危険な場所に移動することも
- 物音や光に極端に敏感になり、わずかな刺激でも警戒
- 巣の周辺10メートル以内は完全な警戒区域として、激しく威嚇や攻撃をする
出産直前のメスは、むしろそれまで以上に慎重に行動するため、より見つけにくい場所を選んでしまいます。
子育て中の「巣の撤去」は新たな被害を誘発!
子育て中のアライグマの巣を見つけても、すぐに撤去するのは危険です。母親は「子どもを守らなきゃ」という本能から、より安全な場所を必死で探すんです。
- 巣を失った母親は24時間以内に新しい巣を作る
- 慌てて移動するため、予期せぬ場所に巣を作ることも
- 移動中の母親は非常に攻撃的になり、人や動物に襲いかかる可能性も
むやみに刺激を与えると、かえって状況が悪化してしまいます。
近隣との「情報共有」が対策成功のカギ!
アライグマの繁殖対策は、1軒だけでは難しいものです。「うちの対策はバッチリ」と思っても、お隣の家に巣を作られては元も子もありません。
- 目撃情報はすぐに近所に共有することで被害を防げる
- 餌場になりそうな場所をみんなで確認し、対策を統一
- 繁殖期前の2週間は特に注意して、情報交換を密にする