アライグマが外来種として引き起こす問題とは【年間被害額1億円超】生態系破壊から農作物被害まで深刻化

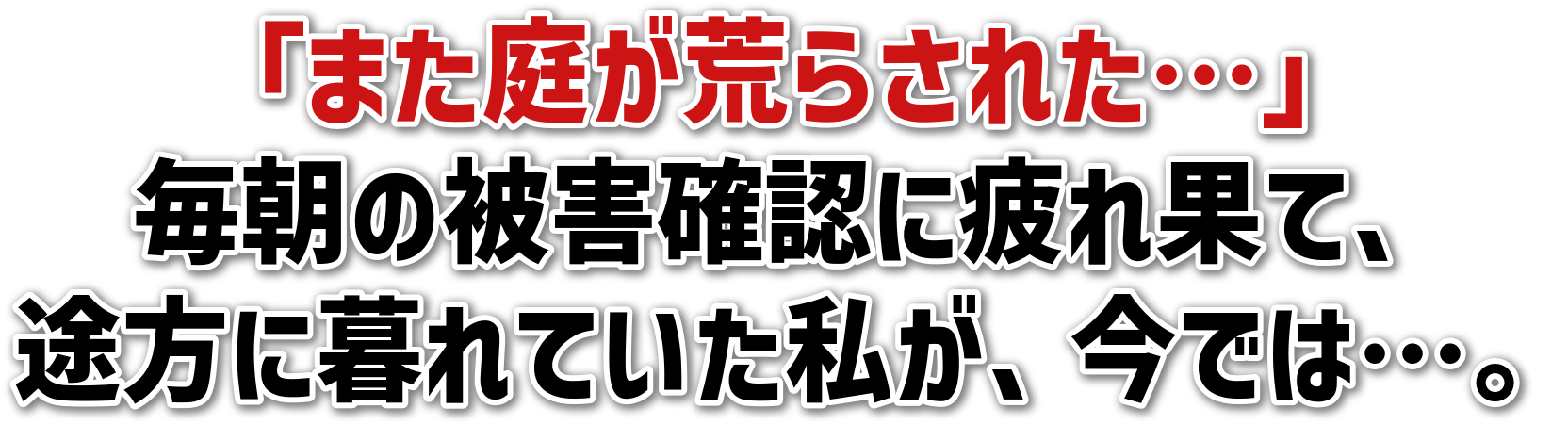
【疑問】
アライグマの被害はどこまで深刻なの?
【結論】
全国で年間1億円を超える被害額に加え、40種以上の在来種が捕食被害を受けています。
ただし、適切な対策を講じることで被害を最小限に抑えることは可能です。
アライグマの被害はどこまで深刻なの?
【結論】
全国で年間1億円を超える被害額に加え、40種以上の在来種が捕食被害を受けています。
ただし、適切な対策を講じることで被害を最小限に抑えることは可能です。
【この記事に書かれてあること】
庭に生ゴミを放置していたら、気がつかないうちにアライグマが住み着いていた…。- アライグマによる年間被害額が1億円を超える深刻な事態
- 47都道府県で確認され繁殖力は年間20パーセント増加の勢い
- 絶滅危惧種を含む40種以上の在来種が捕食被害を受ける
- 農作物被害から生態系の破壊まで幅広い問題を引き起こす
- 効果的な5つの対策方法で被害を最小限に抑制可能
そんな悩みを抱える人が増えています。
北米からやってきた外来種のアライグマは、なんと年間1億円を超える被害を引き起こしているのです。
しかも、繁殖力が強く、今では47都道府県すべてで確認されています。
「このままでは大丈夫かな」と思っていると、取り返しのつかない事態に発展してしまうかもしれません。
アライグマが引き起こす外来種問題の実態と、効果的な対策方法を詳しく解説します。
【もくじ】
アライグマによる外来種問題の深刻さを知る

- 年間被害額1億円超!被害は全国に拡大中
- 北米原産の外来種が日本で急増中!47都道府県で確認
- 餌付けはNG!被害を広げる人間の危険な習慣
年間被害額1億円超!被害は全国に拡大中
アライグマによる被害額が年間1億円を超え、深刻な社会問題となっています。「たかがアライグマでしょ?」なんて甘く見てはいけません。
被害は年々増加の一途をたどり、特に農業分野での被害が目立ちます。
農家の方々からは「一晩で収穫前の果物が全滅」「せっかく育てた野菜が次々と荒らされる」という悲鳴が上がっています。
被害の特徴は以下の3つです。
- 作物を食い荒らすだけでなく、収穫前の果実を見境なく踏み荒らす
- 収穫期に集中して被害が発生し、農家の収入に直結する
- 被害にあった農地は翌年も狙われやすく、連続被害に発展
屋根裏に住みつくと、断熱材を引き裂く、電線をかじる、糞尿による衛生被害など、建物の価値を大きく下げてしまいます。
「修理費用が100万円を超えた」という事例も珍しくありません。
このままでは被害額は増える一方。
早めの対策が不可欠というわけです。
北米原産の外来種が日本で急増中!47都道府県で確認
もともと日本にいなかったアライグマが、今では47都道府県すべてで確認されています。この事態は深刻です。
北米大陸が原産のアライグマは、1970年代に人気テレビアニメの影響でペットとして大量輸入されました。
「かわいい!」と飼い始めた人々。
しかし成長すると凶暴化して手に負えなくなり、多くが野外に放たれてしまったのです。
野生化したアライグマは驚くべき繁殖力を見せます。
- メスは生後1年で出産可能に
- 年2回の出産で1回に2?5頭を産む
- 寒さに強く、日本の気候に完璧に適応
10年で約6倍にも膨れ上がっているんです。
「このまま放っておいたら、いったいどうなってしまうの?」という不安の声が全国から上がっています。
餌付けはNG!被害を広げる人間の危険な習慣
「かわいそうだから餌をあげよう」。この優しい気持ちが、実は被害を広げる原因になっています。
アライグマへの餌付けがもたらす問題は深刻です。
餌付けされたアライグマは人を恐れなくなり、住宅地への出没が増えます。
さらに悪いことに、餌場として覚えた場所には執着し、餌がなくなっても繰り返し訪れるようになるんです。
危険な習慣は他にもあります。
- 生ゴミの放置は格好の餌場に
- 果実の収穫忘れが誘引のきっかけに
- 庭の池は餌場として記憶される
一度でも餌にありつけば、その場所を餌場として学習し、どんどん仲間を呼び寄せてしまいます。
餌付けは絶対にしない、これが鉄則というわけです。
アライグマの驚くべき繁殖力と被害の実態

- メス1頭から年間10頭誕生!驚異の繁殖スピード
- 生態系への打撃!40種以上の在来種が深刻な被害
- 農作物被害は年々拡大!果物や野菜が食い荒らしの標的に
メス1頭から年間10頭誕生!驚異の繁殖スピード
メスのアライグマはわずか1年で年2回の出産が可能です。アライグマの繁殖力がすごいのは、1回の出産で2〜5頭もの子どもを産むから。
つまり、メス1頭から年間最大10頭も増えちゃうんです。
- 生後1年で繁殖可能になり、すぐに子育てを始めます
- 春と秋の年2回、たくさんの赤ちゃんを産みます
- 子育ての成功率が高く、8割以上が無事に育つんです
- 子どもたちも1年後には親になり、さらに数が増えます
生態系への打撃!40種以上の在来種が深刻な被害
アライグマによる在来種への被害は深刻です。絶滅が心配される生き物を含む40種以上が、アライグマに襲われてしまっています。
- 水辺にすむカエルやサンショウウオが食べられてしまいます
- 希少な水鳥の卵や雛が巣ごと襲われます
- 小さなトカゲや昆虫まで、手当たり次第に捕まえます
もともと日本には夜に活動する肉食動物が少なかったため、在来種は夜の捕食者から身を守る方法を知らないのです。
農作物被害は年々拡大!果物や野菜が食い荒らしの標的に
アライグマの食い荒らしによる農作物への被害は、毎年約20パーセントも増加しています。器用な手先を使って、おいしそうな実を次々と食べ荒らしてしまうんです。
- ぶどうやスイカは収穫2週間前が特に危険です
- サツマイモは地中の実を掘り起こして食べます
- トウモロコシは実が柔らかい時期を狙って襲います
- 落花生は匂いを嗅ぎつけて掘り出してしまいます
生態系の脅威と被害の状況を比較

- タヌキよりも「行動範囲の広さ」に要注意!
- キツネvsアライグマ!夜行性の狩りの実態
- ハクビシンとの「食害レベル」を徹底比較
タヌキよりも「行動範囲の広さ」に要注意!
タヌキの3倍以上の行動範囲を持つアライグマは、1晩で最大2キロメートルも移動します。「こんなに広範囲を動き回るなんて…」と驚かれる方も多いはず。
タヌキは決まった場所に巣を作り、そこを中心に500メートル程度の範囲で行動します。
ところがアライグマは違います。
1晩で2キロメートルもの距離を移動し、複数の寝床を持ち歩く生活をしているんです。
その行動範囲の広さから、被害も急速に拡大します。
例えば、ある農家さんの畑で見かけたアライグマが、その日のうちに隣町の果樹園まで被害を広げてしまうことも。
実際の被害の特徴をまとめると、以下の3つが挙げられます。
- 寝床を頻繁に移動し、被害が点在する
- 餌場を複数持ち、毎晩巡回している
- 季節によって行動範囲が変化する
キツネvsアライグマ!夜行性の狩りの実態
キツネは夕方から夜明けまでの時間帯に狩りを行いますが、アライグマはもっと深い夜に活動します。午後8時から午前2時までが最も活発な時間帯なんです。
狩りの方法も全く異なります。
キツネは鋭い嗅覚を頼りに獲物を追いかけ回して捕まえます。
一方アライグマは、器用な手先を使って思いがけない方法で狩りをするんです。
例えば、こんな違いが見られます。
- キツネは走って追いかける、アライグマは待ち伏せして捕まえる
- キツネは地上で狩りをする、アライグマは木に登って鳥の巣を襲う
- キツネは一気に仕留める、アライグマは少しずつ時間をかけて捕まえる
それはアライグマが獲物を狙っているサインかもしれません。
ハクビシンとの「食害レベル」を徹底比較
ハクビシンは果実だけを食べる程度ですが、アライグマは作物を根こそぎ倒してしまいます。農作物への被害は、ハクビシンの約3倍にもなるんです。
その被害の特徴を見てみましょう。
ハクビシンは熟した果実だけを食べ、茎や葉はそのまま残します。
でもアライグマは違います。
作物を見つけると根からひっくり返し、周辺の土も掘り返してしまうんです。
被害の違いは一目瞭然です。
- ハクビシンは実だけを食べる、アライグマは根こそぎ倒す
- ハクビシンは1本の木から食べる、アライグマは畑全体を荒らす
- ハクビシンは熟した実を選ぶ、アライグマは青いうちから食べ始める
- ハクビシンは食べ残しが少ない、アライグマは踏み荒らして無駄にする
被害の大きさが段違いなのです。
アライグマ対策の5つのポイント

- 柵の上部を内側45度に曲げる!侵入防止の鉄則
- 庭に砂場を作って「足跡観察」で行動を把握!
- 生姜のすりおろしを散布!強い刺激臭で撃退
- アルミホイルで木の幹を保護!果樹への被害を防止
- ワイヤーメッシュを地面に敷く!掘り起こし対策の決定版
柵の上部を内側45度に曲げる!侵入防止の鉄則
アライグマの侵入を防ぐ最も効果的な方法は、柵の上部を内側に45度曲げることです。「どうしても柵を乗り越えられない!」とアライグマが諦めてしまうほど、この方法は効果的なんです。
柵を登ろうとした時に、体重で後ろに引っ張られてしまうため、よじ登りが物理的に不可能になります。
具体的な設置方法には、以下のポイントがあります。
- 柵の高さは地上から1メートル以上を確保
- 上部の曲げる長さは30センチメートル程度が目安
- 支柱は2メートルおきに設置して強度を保つ
- 金網は目の間隔が2センチ以下のものを使用
そこで庭木や植え込みで柵を隠すと、見た目も良く、なおかつ防犯効果も高まります。
ちなみに、アライグマは器用な手先を使って柵をゆすったり引っ張ったりするので、設置後1週間は毎日点検することをおすすめします。
がたがたと揺れる柵があれば、すぐに補強が必要です。
庭に砂場を作って「足跡観察」で行動を把握!
アライグマの行動パターンを知る一番確実な方法は、庭に砂場を作って足跡を観察することです。「どこから侵入してくるのかさっぱり分からない…」そんなお悩みも、足跡観察で解決できます。
アライグマの足跡は前足が人の赤ちゃんの手形のような形で、後ろ足は少し細長い特徴があります。
効果的な砂場の作り方は以下の通りです。
- 細かい砂を3センチの厚さで敷く
- 範囲は1メートル四方が目安
- 柵の周辺や物置の近くなど複数箇所に設置
- 雨よけの屋根を付けると足跡が長持ち
足跡の数が多い場所は要注意です。
ころころと転がした跡があれば、その場所で餌を探していた証拠。
このように、足跡からアライグマの行動が手に取るように分かるんです。
生姜のすりおろしを散布!強い刺激臭で撃退
生姜のすりおろしは、アライグマの鋭い嗅覚を刺激して寄せ付けない、自然な撃退方法です。「薬品は使いたくないけど、効果的な方法はないかしら」という方におすすめなのが、この生姜を使った対策。
アライグマは鼻が敏感で、生姜の強い刺激を特に嫌がります。
すりおろした生姜から出る辛み成分が、むんむんと鼻をつく刺激を放つため、アライグマはその場所に近づくことができなくなってしまうんです。
効果的な使い方は以下の通りです。
- 生姜はすりおろして生の状態で使用
- 侵入されやすい場所に10センチおきに置く
- 週に2回程度の交換が必要
- 雨の後はすぐに取り替える
ぴりぴりとした刺激が1週間程度持続するので、定期的な交換で継続的な効果が期待できます。
アルミホイルで木の幹を保護!果樹への被害を防止
果樹の幹にアルミホイルを巻くことで、アライグマの木登りを効果的に防ぐことができます。「せっかく育てた果物が全部食べられちゃう…」そんな悩みも、このアルミホイル作戦で解決。
アライグマは鋭い爪で木をよじ登ろうとしますが、つるつるしたアルミホイルでは爪が引っかからず、登ることができません。
効果的な設置方法をご紹介します。
- 地上から高さ2メートルまで巻く
- アルミホイルは二重に重ねる
- 上下を針金で固定して外れ防止
- 月1回の点検で破れをチェック
また、雨風で傷んだ部分はすぐに補修することで、より効果が高まるというわけです。
ワイヤーメッシュを地面に敷く!掘り起こし対策の決定版
アライグマの掘り起こし被害を防ぐには、地面にワイヤーメッシュを敷くのが効果的です。「畑が掘り返されて、せっかくの野菜が台無しに…」という被害も、この方法なら防げます。
アライグマはずんずんと地面を掘り進もうとしますが、硬いワイヤーメッシュに阻まれると、諦めて別の場所を探すようになります。
設置する際の重要なポイントは以下の通りです。
- メッシュの目の間隔は2センチ以下
- 端は15センチほど折り曲げて地中に埋める
- 複数枚をつなぐ時は5センチ以上重ねる
- 土と密着させることが重要
むしろ、土が流れ出すのを防ぐ効果もあるんです。
定期的に土の状態を確認して、隙間ができていたらすぐに補修しましょう。
アライグマ対策で注意すべき重要事項

- 繁殖期は2月?8月!巣作りの兆候を見逃すな
- 単独と思いきや群れで行動!被害は一気に拡大
- 追い払い作戦は逆効果!攻撃性が高まる危険性
繁殖期は2月?8月!巣作りの兆候を見逃すな
アライグマの繁殖期は2月から8月までと長期にわたります。「天井から物音がするけど、まあ大丈夫かな」なんて見逃していると大変なことに。
巣作りの初期サインを見逃さないことが重要です。
巣作りの兆候は以下の3つです。
- 夜中にガタガタと天井裏から物音がする
- 換気口や屋根の隙間に獣の毛が引っかかっている
- 建物の周りで不自然な糞の跡が見つかる
特にメスは子育て中に非常に攻撃的になるため、巣作りを許してしまうと対処が難しくなってしまうんです。
単独と思いきや群れで行動!被害は一気に拡大
アライグマは一匹だけで行動しているように見えても、実は群れで動いていることが多いのです。「今日は一匹しか見なかったから大丈夫」なんて安心は禁物。
被害の特徴は以下の3つです。
- 同じ場所に複数の足跡が残っている
- 一晩で収穫前の果物がごっそりなくなる
- 庭の土が広範囲にわたって掘り返されている
一匹を見かけたら、必ず仲間がいると考えて対策を立てましょう。
追い払い作戦は逆効果!攻撃性が高まる危険性
アライグマを見かけたからといって、むやみに追い払おうとするのは危険です。「棒を振り回して追い払えば二度と来ないだろう」なんて考えは大間違い。
追い払い行動が逆効果となる理由は以下の3つです。
- 追い払われた個体が強い警戒心を持つようになる
- 追い込まれると反撃してくる可能性が高まる
- 一時的に逃げても必ず別の侵入経路を探してくる