アライグマの性格は獰猛?【餌や子育て時は特に危険】攻撃性は通常の3倍!遭遇時の対処法

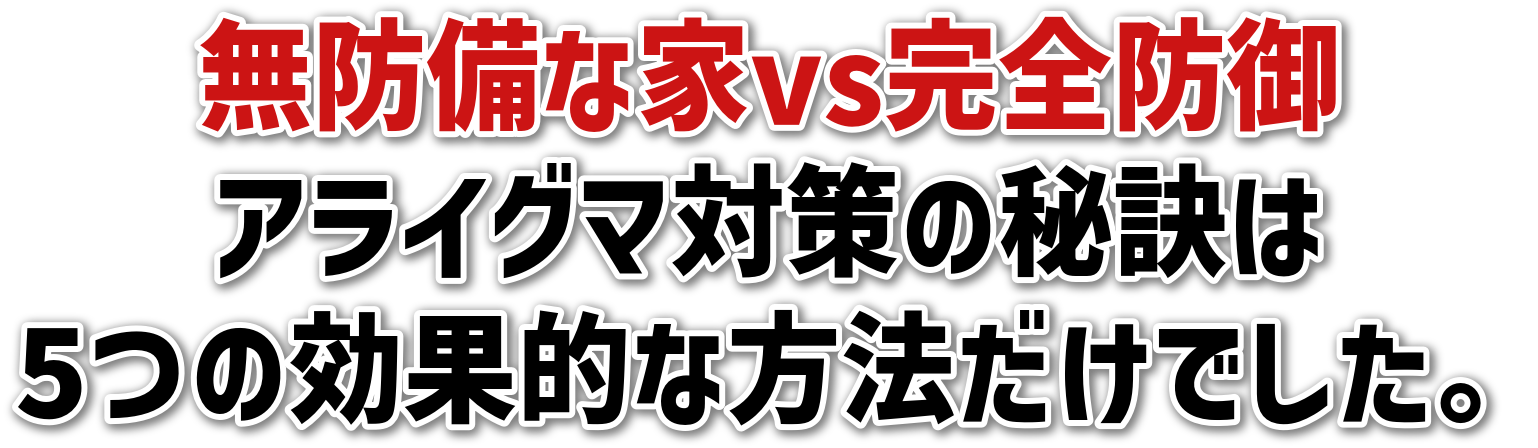
【疑問】
アライグマはいつ一番危険なの?
【結論】
餌場確保と子育て時期に攻撃性が通常の3倍に増加します。
特に巣から30メートル以内の範囲では、母親の警戒心が極端に高まり突然の攻撃を仕掛けてくる可能性があります。
アライグマはいつ一番危険なの?
【結論】
餌場確保と子育て時期に攻撃性が通常の3倍に増加します。
特に巣から30メートル以内の範囲では、母親の警戒心が極端に高まり突然の攻撃を仕掛けてくる可能性があります。
【この記事に書かれてあること】
アライグマは見た目はかわいらしいのに、実は 獰猛な性格の持ち主 なんです。- アライグマは特に餌場確保と子育て時期に獰猛性が増す
- 巣から30メートル以内は母親の警戒が最も強いエリア
- 日没後2時間は最も危険な時間帯として要注意
- 春と夏の出産期は特に攻撃性が高まる時期
- 5つの効果的な対策で侵入と遭遇を防止可能
「まさか襲ってくることはないでしょう?」そんな油断は大変危険です。
特に餌場の周辺や子育て中は、通常の3倍もの攻撃性を見せることも。
巣から30メートル以内では 一瞬の隙も見逃さない警戒心 を持ち、人への攻撃をためらいません。
危険を避けるためには、まずアライグマの本当の性格を理解することが大切です。
この記事では、アライグマの獰猛な性質と、その対策方法をわかりやすく解説します。
【もくじ】
アライグマの性格と獰猛性を知る

- 餌場確保や子育て時は特に危険!攻撃性が3倍に
- 巣から30メートル以内は「母親の警戒エリア」に注意
- 餌付けはNG!攻撃性が急上昇して危険な事態に
餌場確保や子育て時は特に危険!攻撃性が3倍に
アライグマの攻撃性は、餌場の確保や子育て時期に通常の3倍にまで高まります。「この場所は私の餌場よ!」とばかりに、アライグマは餌場を死守しようとします。
特に夜間、生ゴミ置き場や果樹園での遭遇には要注意。
まるで「ここは譲れないわ」という母親のように、自分の餌場を必死に守る習性があるのです。
怖いのは、その攻撃の激しさ。
鋭い爪と強力な顎を武器に、一度の攻撃で深い傷を負わせる可能性があります。
アライグマの攻撃パターンには以下の特徴があります。
- 背後からの不意打ち攻撃が得意
- 威嚇行動なしでの突然の襲いかかり
- 複数での集団攻撃
- 執着心が強く、一度の追い払いでは諦めない
- 餌を見つけると警戒心を完全に失う
人を餌の提供者として認識し、餌をもらえないとストレスで凶暴化してしまうんです。
巣から30メートル以内は「母親の警戒エリア」に注意
巣の周辺では、アライグマの母親の攻撃性が極限まで高まります。「我が子を守るためなら何でもする!」という母親の本能が、アライグマを最も危険な状態に変えるのです。
特に巣から30メートル以内は要注意。
この範囲を「母親の警戒エリア」と呼びます。
巣の近くでは以下の危険な行動が見られます。
- 警告なしでの突然の攻撃
- 威嚇時の攻撃力が通常の2倍以上
- 追いかけ回して執拗に攻撃
- 子育て中は昼間でも活動する
子育て期間は約2か月。
この間は特に注意が必要です。
思わぬところに巣があることも。
物置や屋根裏、木の上など、人の生活圏との距離が近いところに作られるのが特徴なんです。
餌付けはNG!攻撃性が急上昇して危険な事態に
「かわいそうだから」と餌付けをすると、アライグマの攻撃性が急激に高まってしまいます。野生動物なのに人に慣れすぎてしまうと、まるで「ご飯くれないの?」とばかりに人に近づいてくるように。
そして餌をもらえないとがっかり。
その繰り返しでストレスが蓄積され、突然の凶暴化につながるのです。
餌付けによる危険な変化は以下の通りです。
- 人との距離感を完全に失う
- 餌をもらえないとストレスで攻撃的に
- 餌場として覚えた場所に執着
- 子どもにも警戒心なく近づく
- 餌を求めて住宅に侵入
「餌をくれる人は安全」という学習をしてしまい、その結果として人との危険な接触が増えてしまうというわけです。
危険な行動と季節による変化

- 獰猛化の前兆は「うなり声」と「毛を逆立てる行動」
- 日没後2時間は「最も獰猛で危険な時間帯」に
- 春と夏の出産期は「攻撃性がピーク」に到達
獰猛化の前兆は「うなり声」と「毛を逆立てる行動」
アライグマが攻撃を仕掛ける前には、必ず警告のサインを出します。うなり声を上げ、全身の毛を逆立てて威嚇する姿は、危険が迫っている証です。
- まずは低いうなり声を出し始めます
- 次に全身の毛をもじゃもじゃと逆立て、体を大きく見せます
- そして後ろ足で立ち上がり、前足を広げて威嚇します
- 最後に耳を後ろに倒し、うろうろと落ち着きなく動き回ります
特に、うなり声が大きくなってきたら、すぐさま離れましょう。
アライグマは警告なしに突然襲いかかることはありません。
必ず前触れがあるんです。
日没後2時間は「最も獰猛で危険な時間帯」に
日が沈んでから2時間が、アライグマの活動のピークです。この時間帯は特に警戒が必要になります。
お腹をすかせて活発に動き回るため、攻撃性も高まっているんです。
- 日没直後は巣から出てきて周囲を警戒します
- 30分後から本格的な餌探しを始めます
- 2時間以内が最も活発で危険な時間帯です
もしも作業が必要な場合は、明るい照明を用意して、周囲に注意を払いながら行うことが大切です。
春と夏の出産期は「攻撃性がピーク」に到達
春から夏にかけての出産期は、アライグマが最も危険になる時期です。子育て中の母親は普段の3倍も攻撃的になってしまいます。
- 春の出産期は巣作りで警戒心が強まります
- 夏の子育て期は餌の確保に必死で攻撃性が増します
- 巣の周辺30メートルは特に危険なエリアになります
子育て中の母親は、少しの刺激でも激しく反応してしまうということです。
アライグマとの危険な遭遇比較

- アライグマvs野良猫!縄張り意識は2倍以上の差
- アライグマvs小型犬!攻撃力に圧倒的な差
- 春の攻撃性vs夏の攻撃性!子育て時期が要注意
アライグマvs野良猫!縄張り意識は2倍以上の差
野良猫との縄張り争いでは、アライグマが圧倒的に強い立場を示します。野良猫の縄張り意識も強いものですが、アライグマはその2倍以上の強さで縄張りを主張するんです。
「ここは私の場所!」という意識が極めて高く、特に餌場での排他性が目立ちます。
縄張りの広さを比べても、その差は歴然です。
野良猫が半径50メートルほどの範囲を縄張りとするのに対し、アライグマは半径100メートル以上もの範囲を「自分の庭」と考えています。
餌場での争いになると、その差が如実に表れます。
- 野良猫:うなり声で威嚇してから攻撃
- アライグマ:威嚇なしで突然襲いかかる
- 野良猫:逃げ道を確保してから戦う
- アライグマ:相手を追い詰めて徹底的に排除
アライグマの強烈な縄張り意識は、他の動物たちの生活圏をどんどん狭めていくというわけです。
アライグマvs小型犬!攻撃力に圧倒的な差
小型犬とアライグマが対峙した場合、その戦いは一方的になります。アライグマの攻撃力は小型犬の約2倍。
鋭い爪と強力な顎を武器に、相手を圧倒します。
「かわいそうに思えるほど力の差がある」と表現する方も。
体格差以上に恐ろしいのが、戦い方の違いです。
- 小型犬:吠えて威嚇してから攻撃を仕掛ける
- アライグマ:静かに近づいて不意打ちを仕掛ける
- 小型犬:飼い主の存在で大胆になる
- アライグマ:人の存在を全く気にしない
「うちの子は大丈夫」と過信は禁物です。
体重10キロ以下の小型犬は、アライグマにとって格好の標的になってしまいます。
春の攻撃性vs夏の攻撃性!子育て時期が要注意
春と夏では、アライグマの攻撃性に大きな違いが見られます。春は出産に向けた準備期。
巣作りと出産に集中するため、攻撃性は通常の2倍程度です。
「とにかく安全な環境を確保したい」という本能が働くんです。
一方、夏は子育ての最盛期。
攻撃性は春の1.5倍になり、通常の3倍にまで跳ね上がります。
- 巣の周辺30メートル以内は絶対警戒区域に
- 餌場確保のための争いが激化
- 子育ての後半でも警戒心は持続
この母親としての本能が、夏のアライグマを最も危険な存在に変えてしまうのです。
ぴりぴりした様子で警戒する母親の姿は、春の穏やかな雰囲気からは想像もできないほどの変化です。
アライグマ対策の5つの重要ポイント

- 風車設置で「威嚇と音」による撃退効果!
- 竹串を斜め45度に配置!侵入防止の効果
- アルミホイルの反射で「不安と警戒心」を刺激!
- コーヒーかすの香りで「警戒レベル」アップ!
- トゲのある植物で柵を強化!侵入防止に効果的
風車設置で「威嚇と音」による撃退効果!
風車の動きと音で、アライグマに不安と警戒心を与えることができます。アライグマは動くものに警戒心が強い動物です。
特に突然動き出す物体には「キイッ」という警戒の声を出して逃げ出すほど、敏感に反応するんです。
この習性を利用した風車による対策は、とても効果的です。
例えば、近所の山田さんの場合「大きな風車を庭に置いたら、それまで毎晩のように来ていたアライグマが、ぴたりと来なくなった」そうです。
風車の設置には、いくつかの重要なポイントがあります。
- 直径30センチ以上の大きな羽根を選ぶ
- 地面から1メートルの高さに設置する
- 複数の風車を3メートル間隔で配置する
- カラフルな色の風車を選んで視覚的効果を高める
でもここで注意したいのは、強風で風車が壊れないよう、天気予報をこまめにチェックすること。
風の強い日は一時的に取り外すのがおすすめです。
竹串を斜め45度に配置!侵入防止の効果
竹串を地面に斜めに刺すことで、アライグマの通り道を効果的に封鎖できます。アライグマは歩きやすい場所を好む習性があります。
「ふかふか」した土や「つるつる」した地面なら大喜びで歩き回るのですが、とがったものが刺さりそうな場所は本能的に避けるんです。
竹串の設置方法は以下の通りです。
- 15センチ間隔で竹串を配置する
- 地面に対して45度の角度で刺す
- 竹串の長さは20センチ以上を選ぶ
- 地面から10センチほど出るように刺す
でも実は、この方法はアライグマの習性をうまく利用した賢い対策なんです。
竹串が地面から斜めに突き出ているのを見ると「ここは歩きにくそう」「危なそう」という警戒心が働き、自然と遠回りするようになります。
ただし、設置場所には注意が必要です。
子どもやペットが近づく場所は避け、庭の奥や物置の周りなど、人があまり立ち入らない場所を選びましょう。
また、定期的に竹串が抜けかかっていないかを確認することも大切です。
アルミホイルの反射で「不安と警戒心」を刺激!
光を反射するアルミホイルの動きで、アライグマに強い警戒心を与えることができます。夜行性のアライグマは、突然の光の変化に敏感です。
「キラキラ」と不規則に光る物体を見ると「何かが動いている」と感じ取り、警戒心が高まるんです。
アルミホイルの設置方法は、以下のようにします。
- 幅5センチの細長い帯状に切る
- 長さは30センチ程度に揃える
- 紐で吊るして風で揺れるようにする
- 複数の高さに取り付ける
この動きと音の組み合わせが、アライグマにとって「何か危険なものがいる」という錯覚を引き起こすんです。
ただし、雨の日は効果が弱まってしまいます。
そのため、屋根のある場所に設置したり、雨の後は新しいものに取り替えたりする工夫が必要です。
「毎週取り替えるのは面倒」という声もありますが、費用がほとんどかからない方法なので、続けやすい対策といえます。
コーヒーかすの香りで「警戒レベル」アップ!
乾燥させたコーヒーかすの香りは、アライグマの鋭い嗅覚を刺激して警戒心を高めます。アライグマは人の匂いに敏感な動物です。
「コーヒーかすには人の生活の匂いが強く残っている」と感じ取り、その場所を危険な区域だと認識するんです。
効果的な使い方は以下の通りです。
- 天日でしっかり乾燥させる
- 侵入経路に沿って帯状に散布する
- 2日おきに新しいものと交換する
- 雨の後は必ず追加散布をする
まさに、台所から出る廃棄物を有効活用できる一石二鳥の対策方法といえるでしょう。
ただし、気をつけたいのは散布する量です。
多すぎると逆効果になることも。
一度の散布は、縦10センチ、横2メートル程度の帯状にとどめておくのがコツです。
トゲのある植物で柵を強化!侵入防止に効果的
柵にトゲのある植物を這わせることで、アライグマの侵入を効果的に防ぐことができます。アライグマは肉球が敏感で、痛みを特に嫌う動物です。
「チクチク」とした感触に触れただけで「ここは危険」と判断し、別の場所を探すようになります。
おすすめのトゲのある植物は以下の通りです。
- 野ばら(トゲが鋭く、生育が早い)
- サンザシ(枝が密集して這い上がりにくい)
- からまつ(細かいトゲが無数にある)
- さるとりいばら(丈夫な茎で絡みつく)
「伸びすぎて近所に迷惑をかけないように」「枯れた部分は取り除いて見た目を整える」といった基本的な管理を心がけましょう。
植物が成長して柵全体を覆うまでには時間がかかりますが、一度育ってしまえば長期的な効果が期待できます。
「庭の見た目も良くなって一石二鳥」という声も多く聞かれます。
アライグマとの危険な接近を避ける

- 突然の攻撃に要注意!距離は最低5メートル確保
- 危険な「餌場での遭遇」を回避するポイント
- 夜間の庭作業は要注意!予期せぬ遭遇に警戒を
突然の攻撃に要注意!距離は最低5メートル確保
アライグマとの安全な距離は最低でも5メートル。これを守らないと、突然の攻撃を受ける危険があります。
「まさか襲ってこないだろう」という考えは禁物です。
アライグマは予告なしで突進してくることがあり、鋭い爪と歯で深い傷を負わせます。
特に注意が必要なのは以下の場面です。
- 木の近くを通るとき(木の上に潜んでいる可能性)
- 物置の周辺(巣として使われている可能性)
- 生ゴミ置き場の付近(餌場として認識している可能性)
すぐにその場から離れましょう。
危険な「餌場での遭遇」を回避するポイント
餌場での遭遇は最も危険です。アライグマは餌場を必死に守ろうとするため、普段の3倍の攻撃性を見せます。
「ごはんの時間だから大丈夫」なんて考えは通用しません。
- 生ゴミは必ず蓋付きの容器に入れる
- ペットの餌は日没前に片付ける
- 果樹の実は放置せず早めに収穫する
- 野菜くずは堆肥箱に入れてしっかり蓋をする
夜間の庭作業は要注意!予期せぬ遭遇に警戒を
夜間の庭作業中に、ひっそりと近づいてくるアライグマ。「うー」といううなり声が聞こえたら要注意です。
暗闇での遭遇は特に危険で、アライグマの方が圧倒的に有利です。
作業時は以下の点に気をつけましょう。
- 懐中電灯を必ず持ち歩く
- 物陰や暗がりをこまめに照らす
- 物音がしたらすぐに屋内に避難する
- 作業時間は日没前に済ませる