アライグマの侵入経路をチェック【隙間3センチあれば侵入可能】夜間と寒冷期に侵入が3倍増

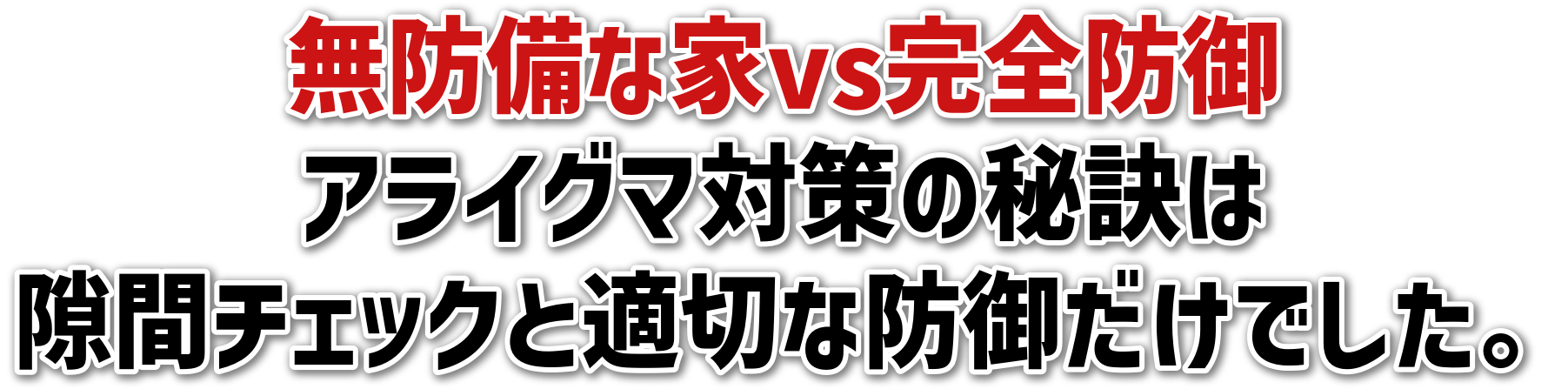
【疑問】
アライグマはどんな場所から家に侵入してくるの?
【結論】
換気口、雨どい、屋根裏の隙間が主な侵入経路で、特に地上から2メートル以内の換気口からの侵入が最も多いです。
ただし、頭部が入る3センチ程度の隙間があれば体を変形させて侵入できるため、建物全体の点検が必要です。
アライグマはどんな場所から家に侵入してくるの?
【結論】
換気口、雨どい、屋根裏の隙間が主な侵入経路で、特に地上から2メートル以内の換気口からの侵入が最も多いです。
ただし、頭部が入る3センチ程度の隙間があれば体を変形させて侵入できるため、建物全体の点検が必要です。
【この記事に書かれてあること】
アライグマが家に侵入する経路、知っていますか?- 隙間3センチがあれば家屋に侵入可能な高い身体能力
- 換気口と雨どいが最も狙われやすい侵入経路
- 気温15度以下になると侵入の試みが急増
- 日没後2時間が最も要警戒な時間帯
- 物理的な防御と忌避材を組み合わせた効果的な対策方法
実は、わずか3センチの隙間があれば、まるで忍者のように体を器用に変形させて侵入してしまうんです。
しかも、日が暮れてから2時間後や気温が下がる時期には、侵入の試みが3倍以上に増加。
「うちは大丈夫」と思っていても、換気口や雨どいなど、思わぬ場所が侵入口になっているかもしれません。
アライグマの好む侵入経路と、その対策方法を詳しく解説していきます。
【もくじ】
アライグマの侵入経路と対策ポイント

- 家屋への侵入に使われる「隙間3センチ」の危険性!
- 家屋の弱点となる「換気口と雨どい」に要注意!
- 木材やプラスチックの建材は「要警戒ゾーン」に認定!
家屋への侵入に使われる「隙間3センチ」の危険性!
アライグマは体を器用にくねらせて、わずか3センチの隙間から侵入できます。「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と驚く方も多いはず。
でも、実はこれが住宅被害の一番の原因なんです。
頭部が入る大きさがあれば、アライグマは体を自在に変形させて侵入してしまいます。
「たかが3センチ、大丈夫でしょ」と思っていると、とんでもない事態に。
四角い穴なら一辺3センチ、丸い穴なら直径8センチあれば、体をくにょくにょと曲げながら中に入ってくるんです。
特に注意が必要なのは以下の場所です。
- 壁と屋根の接合部分にできた小さなすき間
- 古くなって緩んだ外壁のパネルの隙間
- 雨どいの取り付け部分のわずかな隙間
- 経年劣化でできた建材のヒビや割れ目
一度侵入に成功すると、その経路を覚えて何度も使用するため、小さな隙間も見過ごさないことが大切です。
「こんな小さな穴、気にしなくていいや」は禁物。
早めの対処で被害を防ぎましょう。
家屋の弱点となる「換気口と雨どい」に要注意!
換気口と雨どいは、アライグマが最も狙う侵入経路です。特に地上から2メートル以内にある換気口は要注意。
「うちは換気口に網があるから安心」と思っていても、実は危険がひそんでいます。
換気口の網は、アライグマの鋭い爪で簡単に破られてしまいます。
がりがりと音を立てながら、目の粗い網をあっという間に破壊。
さらに困ったことに、雨どいを木登りの要領で器用によじ登り、屋根裏への侵入経路を作ってしまうんです。
アライグマの侵入を防ぐためには、以下の対策が効果的です。
- 目の細かいステンレス製の網に交換する
- 雨どいにすべり止めの板を取り付ける
- 換気口の周りに金属製のカバーを設置する
- 雨どいと壁の間に隙間を作らないよう固定する
「ちょっとぐらいガタついていても」は危険信号。
しっかりと固定して、アライグマの通り道を遮断しましょう。
木材やプラスチックの建材は「要警戒ゾーン」に認定!
木材やプラスチック製の建材は、アライグマにとって格好の侵入口となります。「頑丈そうに見えるから大丈夫」と思っていても、実は要注意。
アライグマの鋭い爪と強い顎の力で、がりがりと削られてしまうんです。
特に古くなった木材は、アライグマの格好のターゲットに。
腐食した部分をかりかりと削り、どんどん穴を広げていきます。
プラスチック製の換気カバーも、がじがじと噛んで壊されてしまいます。
以下の建材は特に注意が必要です。
- 雨で劣化した軒下の木材
- 古くなったプラスチック製の換気カバー
- 腐食が始まっている木製の外壁パネル
- ひびが入った樹脂製の建材
建材の状態を定期的にチェックして、劣化が見られたらすぐに交換することが大切です。
「もう少し大丈夫」は、アライグマを招き入れる危険なサインなんです。
季節と時間帯による侵入リスク

- 秋と冬に「侵入件数が急増」する理由とは!
- 日没後2時間の「特に要注意な時間帯」に注目!
- 気温15度以下で「侵入の試み」が3倍に!
秋と冬に「侵入件数が急増」する理由とは!
寒さを避けるため、アライグマの住宅侵入は秋から冬にかけて急増します。特に10月から11月の気温低下時期が要注意です。
暖かい住処を探して、次のような行動をとります。
- 気温が下がり始める夕方から夜にかけて、建物の周りをうろうろと下見
- 雨の日は雨宿りを兼ねた侵入が増加し、晴れの日の2倍に
- 特に出産を控えたメスが暖かい巣作り場所を必死に探索
- 寒くなると食べ物も少なくなるため、生活ごみなども狙って接近
日没後2時間の「特に要注意な時間帯」に注目!
日が沈んでから2時間が最も危険です。この時間帯にアライグマの活動が活発化し、侵入の試みが集中します。
夜行性の特徴をよく理解して、以下のような時間帯別の対策が必要です。
- 日没直後は周辺の下見や探索行動が増加
- 日没1時間後から本格的な侵入行動を開始
- 日没2時間後までが最も警戒が必要な時間帯
- 真夜中になると活動は徐々に落ち着いてくる
気温15度以下で「侵入の試み」が3倍に!
気温が15度を下回ると、アライグマは暖かい場所を必死に探し始めます。寒さが厳しくなるにつれて、侵入を試みる回数が急激に増えていきます。
温度によって行動が変化する特徴をつかんでおきましょう。
- 気温15度以下で侵入の試みが増加開始
- 気温10度以下で2倍に急増
- 気温5度以下になると3倍まで跳ね上がる
- 氷点下では建物の隙間を必死に探り続ける
侵入パターンを徹底比較

- 地上からの侵入vs高所からの侵入「70%対30%」!
- 単独行動vs群れでの行動「圧倒的な差」に注目!
- 昼間vs夜間の侵入「95%が夜間に集中」!
地上からの侵入vs高所からの侵入「70%対30%」!
アライグマの住宅侵入は、地上からが圧倒的に多いのです。全体の70パーセントが地上からの侵入で、残りの30パーセントが高所からの侵入です。
「どうして地上からの侵入が多いんだろう?」と思われる方も多いはず。
実は理由がちゃんとあるんです。
地上からの侵入が多い理由は、アライグマの探索行動の特徴にあります。
まずは地面の近くをくんくんと嗅ぎ回り、建物の弱点を探していきます。
特に建物の角から1メートル以内の範囲を、がっつり調べるのが特徴です。
- 換気口からの侵入が最も多く全体の40パーセント
- 建材の腐食部分からの侵入が全体の20パーセント
- 基礎と外壁の隙間からの侵入が全体の10パーセント
「これなら簡単に入れそう」という場所を見つけると、そこを重点的に攻撃します。
高所からの侵入は手間がかかるため、わざわざ上を目指すことは少ないんです。
ただし、地上からの侵入を防がれると、とたんに高所からの侵入を試みるようになります。
賢いですね。
単独行動vs群れでの行動「圧倒的な差」に注目!
アライグマの侵入は、なんと85パーセントが単独行動なんです。群れでの行動は極めて少なく、驚くべき差が見られます。
「群れで行動する動物じゃないの?」と思われるかもしれません。
でも、実は違うんです。
単独行動が多い理由は、侵入時の危険を分散させる本能があるからです。
ぞろぞろと群れで行動すれば目立ってしまいますよね。
そこで、こっそりと一匹で行動することで、見つかるリスクを減らしているんです。
- 単独での侵入が全体の85パーセント
- 母子での侵入が全体の14パーセント
- 3頭以上の群れでの侵入は全体の1パーセント未満
ただし、子育て中の母親は例外です。
子どもと一緒に行動する必要があるため、14パーセントを占めています。
昼間vs夜間の侵入「95%が夜間に集中」!
アライグマの侵入は、ほとんどが夜間に集中します。なんと95パーセントが夜の侵入なんです。
昼と夜で、こんなにはっきりと差が出る理由があります。
それは、アライグマの目が夜行性に特化しているから。
暗闇でも3メートル先まではっきりと見えるんです。
特に真夜中の0時から2時の間が狙い目です。
この時間帯に全体の60パーセントが集中します。
理由は人間の活動が最も少ない時間帯だからです。
- 夜間の侵入が全体の95パーセント
- 0時から2時の侵入が全体の60パーセント
- 昼間の侵入は全体の5パーセントのみ
もし昼間にアライグマを見かけたら要注意です。
餌付けされている可能性が高く、人を恐れない危険な個体かもしれません。
5つの効果的な対策方法

- 古い靴下と「木酢液の活用」で侵入防止!
- ペットボトルの反射光で「威嚇効果」をアップ!
- 竹串で「物理的な防御ライン」を構築!
- アルミホイルの音と光で「警戒心」を刺激!
- 腐ったみかんの皮で「柑橘系の香り」を放出!
古い靴下と「木酢液の活用」で侵入防止!
身近な材料で効果的な対策ができます。古い靴下と木酢液を組み合わせることで、アライグマの侵入を防ぐことができるんです。
「もったいないから取っておいた靴下が、まさか役立つとは!」そんな声が聞こえてきそうです。
実は、アライグマは強い匂いを嫌う習性があるため、木酢液を染み込ませた靴下を侵入可能性のある場所に設置すると、とても効果的なのです。
具体的な設置方法は次の通りです。
- 靴下に木酢液を染み込ませる(目安は靴下1枚に対して50ミリリットル)
- 換気口の周り、雨どいの下、建物の角など侵入されやすい場所に設置
- 3日おきに木酢液を追加して効果を持続
- 雨に濡れないよう、軒下など覆いのある場所を選んで設置
- 靴下自体は2週間に1回の交換がおすすめ
それでいてアライグマには「ここは危険だぞ」という強い警告となるわけです。
ペットボトルの反射光で「威嚇効果」をアップ!
空のペットボトルが、思いがけない威力を発揮します。水を入れて日光に当てることで、アライグマを寄せ付けない光の防御壁を作れるんです。
アライグマは光の反射に敏感な生き物。
「きらきら」と不規則に動く光は、彼らにとって「何か危険なものがいるかも」という警戒心を呼び起こすのです。
効果的な設置方法をご紹介します。
- 透明なペットボトルに水を8分目まで入れる
- 建物の周りに2メートル間隔で複数設置
- 日光が当たる場所を選んで設置(影になる場所は避ける)
- ボトルが倒れないよう、地面に20センチ程度埋める
- 水は週1回の交換で清潔に保つ
確かに夜間は光の反射が弱まりますが、月明かりでもわずかに反射するため、まったく意味がないわけではありません。
とはいえ、夜間対策としては他の方法と組み合わせるのがよいでしょう。
台風など強風時は一時的に撤去することも忘れずに。
竹串で「物理的な防御ライン」を構築!
竹串という身近な道具で、アライグマの侵入を防ぐ強力な防御線が作れます。竹の先端が鋭いため、アライグマは近づくことすら警戒するんです。
「竹串って、あの料理で使うやつ?」はい、その通りです。
実は竹串には、アライグマを寄せ付けない2つの重要な特徴があります。
まず、鋭い先端が警戒心を引き起こすこと。
次に、地面に斜めに刺すことで、アライグマの通り道に物理的な障壁を作れることです。
効果的な設置方法をご紹介します。
- 竹串を地面に対して45度の角度で刺す
- 間隔は15センチ程度で、連続して設置
- 先端の高さは安全のため地上5センチまでに抑える
- 雨どい周辺や建物の角など、侵入されやすい場所を重点的に守る
- 地面が柔らかい日を選んで設置作業を行う
竹の香りも寄せ付けない効果があるため、一石二鳥というわけです。
アルミホイルの音と光で「警戒心」を刺激!
アルミホイルをくしゃくしゃに丸めて設置するだけで、アライグマの警戒心を刺激できます。「がさがさ」という予期せぬ音と、月明かりに照らされて光る表面が、彼らの接近を防ぐんです。
実はアライグマは、見慣れない物が動いたり音を立てたりすると、とても警戒します。
アルミホイルは風で揺れるたびに「かさかさ」と音を立て、不規則に光を反射するため、格好の威嚇道具となるわけです。
具体的な活用法は次の通りです。
- 30センチ四方のアルミホイルをゆるく丸める
- 針金で固定し、風で飛ばされないようにする
- 建物の周りに1メートル間隔で設置
- 雨どいの下や換気口の近くは特に重点的に
- 表面が汚れたら新しいものと交換する
朝には回収して、夕方に再び設置する方法もありです。
腐ったみかんの皮で「柑橘系の香り」を放出!
みかんの皮を活用した驚きの対策方法があります。腐らせて干したみかんの皮から放たれる強い香りが、アライグマを遠ざける効果を発揮するんです。
「腐ったみかんなんて、ちょっと気持ち悪い…」と思われるかもしれません。
でも、これには科学的な根拠があるのです。
みかんの皮に含まれる成分が腐敗する過程で、アライグマが本能的に避ける強い香りに変化していきます。
実践的な活用方法をご紹介します。
- みかんの皮を3日間ほど常温で置く
- 天日で完全に乾燥させる
- 網袋に入れて侵入されやすい場所に吊るす
- 雨に濡れない場所を選んで設置
- 週1回の交換で効果を維持
ただし、近所の方への配慮として、建物の裏側など、目立たない場所での実施をおすすめします。
侵入経路の確認と予防策

- 建物の角から「1メートル以内」が最重要チェック地点!
- 雨どい周辺は「強度低下」に要注意!
- 建物と樹木の距離は「2メートル以上」確保が鉄則!
建物の角から「1メートル以内」が最重要チェック地点!
建物の角は、アライグマが最も念入りに調べる場所です。目の前の建物の角をじっくり見てみると「あれ?こんなところにヒビが…」と気づくことも。
建物の角は雨風にさらされやすく、建材が劣化しやすい特徴があります。
特に気を付けたいのは地面から手の届く高さの部分。
- 壁と土台の接合部分のすき間
- 外壁材のひび割れや欠け
- 配管まわりの穴やすき間
- 建材の継ぎ目の緩み
小さな傷でも見つけたらすぐに補修を。
「まあ、大丈夫かな」と放っておくと、あっという間に侵入口になっちゃうんです。
雨どい周辺は「強度低下」に要注意!
雨どいの周辺は、建物の中でも特に注意が必要な場所なんです。雨どいを支える金具の部分は、アライグマが足場として使いやすい形状になっています。
「ガタガタッ」という物音が夜中に聞こえたら要注意。
- 雨どいと壁の接合部分のゆるみ
- 支え金具のぐらつき
- 壁材の腐食や変色
- コーキング材の劣化
「少しぐらい」が命取り。
支え金具1か所のゆるみが、思わぬ侵入口を作ってしまうことも。
建物と樹木の距離は「2メートル以上」確保が鉄則!
建物の周りにある樹木は、アライグマにとって格好の足場になります。「せっかくの木だから」と近くに植えたままにしていると、ツタをつたって建物に近づかれちゃいます。
枝の剪定は欠かせない作業です。
- 建物に触れている枝の除去
- 壁面を這うツタの撤去
- 果樹の植え替えや剪定
- 低木の刈り込み
ぎりぎりセーフと思っても、風で枝がしなって建物に触れることも。
定期的な手入れをお忘れなく、というわけです。