アライグマは屋根からも侵入する【雨どい伝いに登って侵入】3センチの隙間から年2回繁殖期に要注意

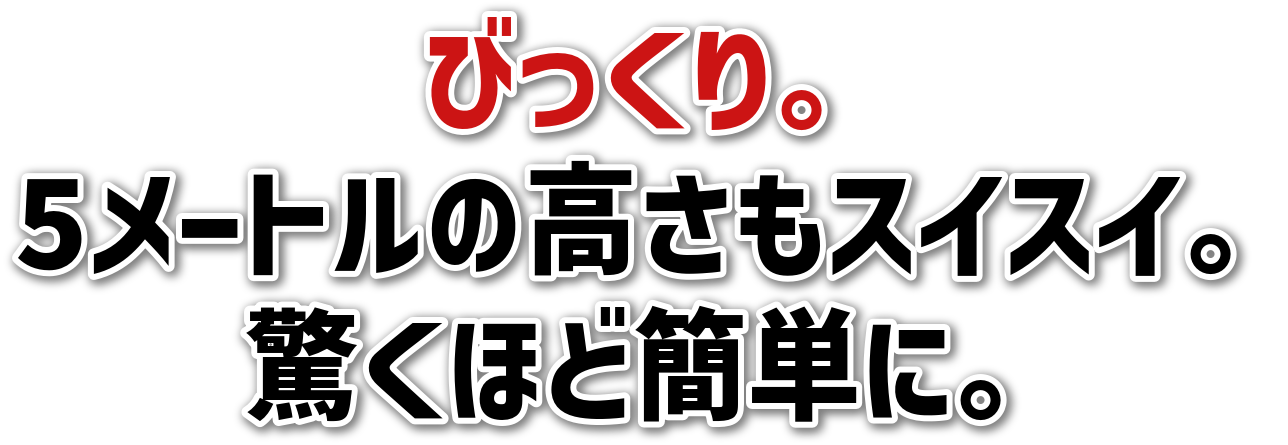
【疑問】
アライグマの屋根からの侵入を見逃さないためのポイントは?
【結論】
雨どいを伝った侵入が最も多く、垂直でも5メートルまで簡単に登れます。
ただし、春と秋の繁殖期に侵入が増加するため、この時期は特に注意が必要です。
アライグマの屋根からの侵入を見逃さないためのポイントは?
【結論】
雨どいを伝った侵入が最も多く、垂直でも5メートルまで簡単に登れます。
ただし、春と秋の繁殖期に侵入が増加するため、この時期は特に注意が必要です。
【この記事に書かれてあること】
家の屋根からアライグマの物音が聞こえると、誰もが不安になるもの。- 雨どいを伝って垂直に5メートルまで簡単に登れる運動能力
- 屋根に到達後は瓦の隙間を利用して時速10キロで移動
- 春と秋の繁殖期には屋根からの侵入が3倍に増加
- 3センチ以上の隙間があれば確実に侵入される危険性
- 雨どい周辺への防鳥スパイクの設置で効果的に侵入を防止
実は、アライグマは雨どいを伝って家屋に侵入する巧妙な手口を持っています。
「まさか、あの高さまで登れるはずない…」と思っていませんか?
なんと、前足で雨どいをつかみ、後ろ足で蹴りながら、垂直な壁でもすいすいと5メートルの高さまで登れるのです。
しかも、わずか3センチの隙間があれば侵入できてしまうため、春と秋の繁殖期には特に要注意。
屋根裏で子育てを始められる前に、効果的な対策を知っておきましょう。
【もくじ】
アライグマの屋根からの侵入被害が急増中

- 雨どいを利用した「巧妙な侵入手口」に要注意!
- 5メートルの高さまで「スイスイと昇る」驚きの運動能力
- 雨どい周辺の設置物は「足場として利用」されるNG行動
雨どいを利用した「巧妙な侵入手口」に要注意!
アライグマは雨どいを格好の侵入経路として狙っています。わずか3センチの隙間があれば、建物内に簡単に侵入できてしまうのです。
「どうしてウチの屋根に上れるんだろう?」そう思われている方も多いはず。
実は雨どいは、アライグマにとって絶好の昇り降り用の通路になってしまうんです。
前足で雨どいをがっちりと挟み込み、後ろ足で壁を蹴って「よいしょ、よいしょ」と上っていきます。
まるで消防士が火災現場で使う縦穴のような感覚で、スイスイと昇っていくのです。
特に要注意なのが、以下の3つのポイントです。
- 軒下と雨どいの接合部分の隙間
- 雨どいと外壁の間にできたわずか3センチの隙間
- 雨どいの継ぎ目部分の緩みや劣化
雨どいさえあれば、どんな屋根でも侵入される可能性があるのです。
特に注意が必要なのは春と秋。
繁殖期に入ると、雨どいを使った侵入が急増します。
暖かい巣作りの場所を必死で探しているんです。
5メートルの高さまで「スイスイと昇る」驚きの運動能力
アライグマは信じられないほどの運動能力を持っています。垂直の雨どいでも、なんと5メートルの高さまでスイスイと上ってしまうのです。
その登り方がとても特徴的です。
まず前足で雨どいをしっかりと挟み込みます。
「ギュッ」と力を入れて、体重を支えながら上昇していくんです。
後ろ足は壁を器用に蹴って、体を押し上げる力を生み出します。
- 前足の握力は成人男性の3倍以上
- 指先は人間のような器用さで細かい動きが可能
- 体重を支えながら片手で物をつかむ高度な技も
「ただの小動物でしょ?」なんて侮っていると大変。
2階建て住宅の屋根も、まるで公園の遊具のように軽々と上ってしまいます。
雨の日でも関係ありません。
むしろ雨で濡れた雨どいの方が、前足でしっかりと掴めるため、より素早く上れてしまうことも。
雨どい周辺の設置物は「足場として利用」されるNG行動
アライグマは周囲の物を賢く利用して、雨どいに到達します。物干し竿や庭木、エアコンの室外機など、私たちの生活に欠かせない物が、思わぬ「踏み台」になってしまうのです。
特に以下の設置物には要注意です。
- 雨どいの近くに置かれた物置や収納庫
- 壁に沿って伸びた背の高い庭木や植木
- 高さ1メートル以上の固定された構造物
- ベランダに置かれた大型の植木鉢
アライグマは複数の足場を器用に渡り歩きながら、少しずつ高度を上げていきます。
まるで忍者のように、建物の特徴を見事に活用してしまうんです。
さらに困るのが、一度成功した侵入経路を記憶する高い学習能力。
「ここから登れば屋根に行ける」というルートを覚えてしまうと、繰り返し同じ経路で侵入を試みます。
だからこそ、雨どい周辺の環境整備が重要なんです。
屋根での移動能力と行動パターン

- 垂直な雨どいでも「前足で挟んで簡単に昇降」する特徴
- 瓦の隙間に「爪をひっかけて時速10キロ」で移動可能
- 春と秋の「出産期に侵入が増加」する生態的特徴
垂直な雨どいでも「前足で挟んで簡単に昇降」する特徴
アライグマは前足で雨どいをしっかりと挟み込み、垂直な壁面でも器用に昇り降りします。その姿はまるで消防士のように素早く、驚くべき身のこなしなんです。
- 前足の力が人間の握力の3倍以上と強く、雨どいをがっちりと掴めます
- 後ろ足で壁面を蹴りながら、ぐんぐんと上昇していきます
- 尾を使って絶妙なバランスを取り、垂直な雨どいでも5メートルまで楽々と登れます
- 降りるときは逆さまの姿勢でもスイスイと移動できます
瓦の隙間に「爪をひっかけて時速10キロ」で移動可能
アライグマは鋭い爪を瓦と瓦の間にひっかけながら、屋根の上を自由自在に動き回ります。その動きはまるで忍者のように素早く、屋根の形状を問わずに移動できてしまいます。
- 四肢を大きく広げて体重を分散させながら移動します
- 瓦の表面の細かな凹凸も足場として利用できます
- 最大で時速10キロという驚くべき速さで動き回れます
- 勾配の急な屋根でも、爪をひっかけてよじ登れてしまうんです
春と秋の「出産期に侵入が増加」する生態的特徴
アライグマの屋根への侵入は、春と秋の出産期に特に増加します。この時期は子育てに適した暖かく安全な場所を必死で探しているのです。
- 春は3月から5月、秋は8月から10月が出産のピーク
- 母親は一度に3頭から5頭の子供を産みます
- 子育ての時期は約2か月間も屋根裏に居座り続けます
- 巣作りのために断熱材をかじったり、天井に穴を開けたりしてしまいます
- 夜間は餌を探しに外出するため、出入りが頻繁になってしまうんです
屋根からの侵入経路と被害の比較
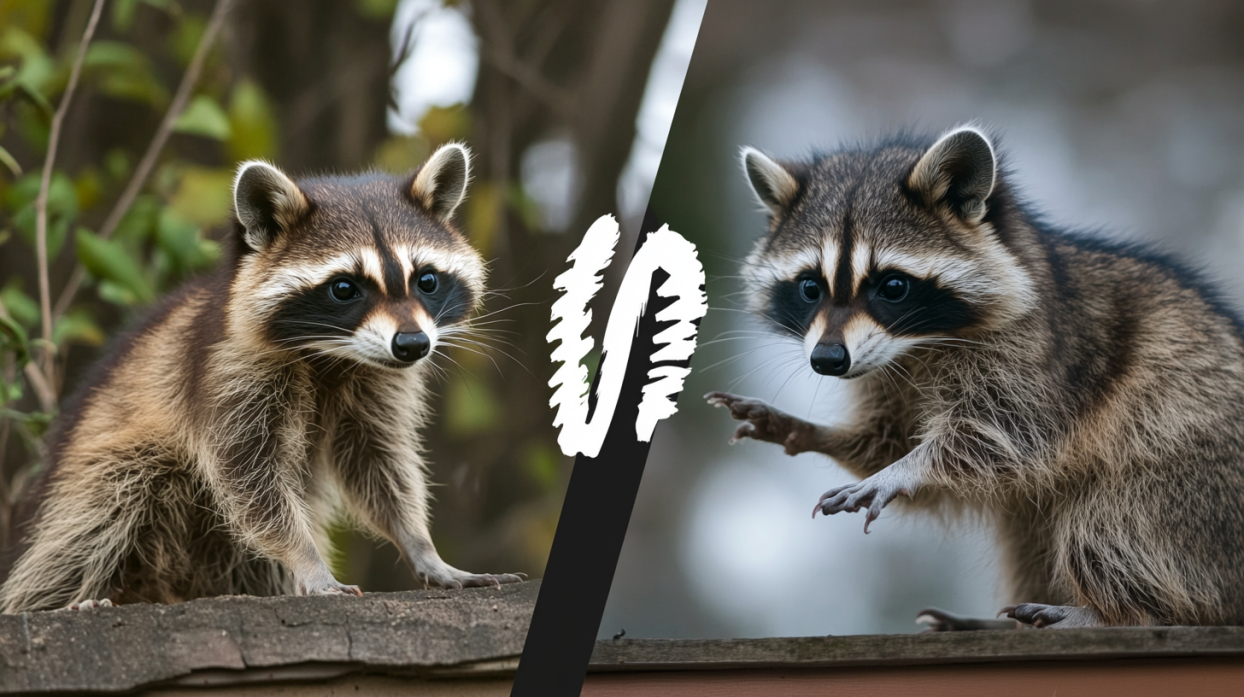
- 雨どい経由vs壁伝いの侵入!3倍の発生頻度に警戒
- 地上からの侵入と屋根からの侵入!発見の遅れに注意
- 換気口と雨どいの対策費用!3倍のコスト差に驚愕
雨どい経由vs壁伝いの侵入!3倍の発生頻度に警戒
壁を直接よじ登るよりも、雨どい経由での侵入が実に3倍も多いのです。「どうしてこんなに差があるの?」と思われるかもしれません。
その理由は、雨どいがアライグマにとって格好の「はしご」になっているからです。
まるで消防士が消防車のポールを滑り降りるように、アライグマは雨どいを自在に上り下りします。
前足で雨どいをがっちりと挟み込み、後ろ足で蹴り上げながら、するすると上っていくのです。
雨どいの特徴的な構造が、アライグマの侵入をお手伝いしているような状況になっています。
- 縦樋が垂直な固定物として最適な足場に
- 横樋が屋根裏への移動通路として利用される
- L字やT字の接合部が休憩ポイントとして重宝される
- 表面の凹凸が爪をひっかける場所として最適
特に注意が必要なのは、雨どいと壁の間に隙間がある場合です。
この隙間は、アライグマの前足が完璧なホールドとして使えてしまうんです。
地上からの侵入と屋根からの侵入!発見の遅れに注意
屋根からの侵入は、地上からの侵入に比べて発見が遅れやすく、気付いたときには大きな被害になっていることが多いのです。「まさか屋根から入ってくるとは」という油断が、被害を大きくしてしまう原因です。
地上からの侵入なら、庭や玄関周りの足跡やフンなどの痕跡ですぐに気付けます。
でも屋根からの侵入は違います。
- 足跡が屋根の上にしか残らず見つけにくい
- フンや爪痕が雨で流されやすいため証拠が残りにくい
- 侵入音が風や雨の音とまぎらわしい
- 屋根裏での生活痕が見えない場所にできる
でも、屋根裏で「ガタガタ」という音が聞こえたら要注意です。
すでに住み着いている可能性が高いので、すぐに対策を始める必要があります。
換気口と雨どいの対策費用!3倍のコスト差に驚愕
換気口への対策は金網を取り付けるだけで済みますが、雨どいへの対策は建物全体に関わるため、費用が3倍以上かかってしまうのです。「そんなにお金がかかるの?」と驚かれるかもしれません。
具体的な対策費用の差を見てみましょう。
- 換気口:金網による防護で済むため費用は抑えめ
- 雨どい:建物全体の周囲に対策が必要で費用増大
- 設置作業:高所での危険な作業で人件費も割高
- メンテナンス:定期的な点検や補修で維持費も必要
「天井裏でごそごそ」という不気味な音に悩まされることもなくなり、長い目で見れば費用対効果は十分なんです。
屋根からの侵入を防ぐ5つの対策方法

- 滑りやすい「ブリキ板で雨どいを巻き付ける」即効性のある方法
- 防鳥スパイクを「雨どいの両側20センチ間隔」で設置
- 「月1回のワセリン塗布」で雨どいを滑りやすく維持
- 反射テープを「螺旋状に巻き付けて」夜間の接近を抑制
- 「柑橘系オイルを週2回散布」する匂いでの撃退法
滑りやすい「ブリキ板で雨どいを巻き付ける」即効性のある方法
薄いブリキ板で雨どいを巻き付けることで、アライグマの爪がかりをなくし、侵入を防ぐことができます。「これなら自分でもできそう!」と思った方も多いのではないでしょうか。
実は、ブリキ板を使った対策は手軽さと効果の両方を兼ね備えた優れた方法なんです。
まずは準備するものをご紹介します。
- 幅30センチのブリキ板
- ステンレス製のネジと固定具
- 防錆スプレー
- 軍手
雨どいの周りにブリキ板をくるっと巻きつけて、両端を固定具でしっかり留めるだけ。
「つるつる」した表面がアライグマの爪をすべらせ、よじ登りを防いでくれます。
ただし、取り付けの際は以下の点に気をつけましょう。
- 雨どいの排水機能を妨げない位置に取り付ける
- 強風で外れないよう、30センチごとに固定具を追加する
- edges(端)は指を切らないよう、折り曲げて処理する
これで雨や雪にも負けない、長持ちする対策の完成です。
防鳥スパイクを「雨どいの両側20センチ間隔」で設置
防鳥スパイクを雨どいの両側に取り付けることで、アライグマの侵入を物理的に防ぐことができます。このスパイクは、見た目以上に効果てきめんです。
アライグマが「いてっ!」と思わず手を引っ込めたくなる、確実な侵入防止効果を発揮します。
設置のコツは間隔と向きです。
- 両側20センチ間隔で取り付け
- スパイクの先端を45度上向きに調整
- 雨どいの上端から1メートルは必ず設置
でも大丈夫です。
このスパイクは鳥やアライグマを傷つけない設計で、ただ不快に感じさせるだけなんです。
取り付けの際は以下の注意点を忘れずに。
- 樋掃除の妨げにならない位置を選ぶ
- 錆びにくいステンレス製を選択する
- 定期的なぐらつきチェックを行う
「がたがた」と音がする箇所があれば、すぐに固定し直しましょう。
「月1回のワセリン塗布」で雨どいを滑りやすく維持
ワセリンを塗布することで雨どいの表面を滑りやすくし、アライグマの侵入を防ぐことができます。「えっ、そんな簡単なもので効果があるの?」と思われるかもしれません。
でも実は、ワセリンの持続的な効果は侮れないんです。
まずは塗り方のポイントをご紹介します。
- 雨どい表面の汚れを落としてから塗布
- 薄く均一に伸ばすことがコツ
- 縦方向に一定の力で塗る
「にゅるっ」と手が滑って登れなくなるため、諦めて別の場所を探すようになるわけです。
効果を持続させるには、以下の管理が重要です。
- 月1回の塗り直しを忘れずに
- 雨の多い時期は2週間ごとに点検
- 汚れが目立つ箇所は早めに再塗布
反射テープを「螺旋状に巻き付けて」夜間の接近を抑制
反射テープを雨どいに巻き付けることで、夜行性のアライグマの警戒心を刺激し、接近を防ぐことができます。テープの巻き方がとても重要です。
「くるくる」と螺旋状に巻くことで、光の反射角度が変化し、より効果的な威嚇効果が得られます。
具体的な設置方法をご紹介します。
- 幅5センチの反射テープを使用
- 20センチ間隔で螺旋状に巻く
- テープの端はしっかり固定
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 3か月ごとの貼り替えを忘れずに
- 汚れや剥がれは早めに補修
- 雨どいの排水機能を妨げない位置に
反射が強すぎる場合は、設置角度を少し調整してみましょう。
「柑橘系オイルを週2回散布」する匂いでの撃退法
アライグマの嫌う柑橘系のオイルを散布することで、匂いによる撃退効果が期待できます。実は、アライグマは柑橘系の強い香りが大の苦手。
「むっ」とする刺激的な匂いに、本能的な警戒心を示すんです。
効果的な使用方法は以下の通りです。
- 雨どい周辺に20センチ間隔で散布
- 週2回の定期的な散布が基本
- 夕方の散布が最も効果的
持続的な効果を得るために、以下の点に気をつけましょう。
- 雨天後は必ず再散布を行う
- 原液は10倍に薄めて使用
- 散布箇所を記録して管理
「自然な方法で撃退したい」という方におすすめです。
屋根からの侵入対策で失敗しないための注意点

- 「子育て中の可能性」を考慮した慎重な行動を!
- 「3センチ以上の隙間」を徹底的に塞ぐ重要性
- 雨どい周辺の「定期的な清掃と点検」が決め手に
「子育て中の可能性」を考慮した慎重な行動を!
アライグマが屋根裏で子育てをしている可能性があるため、むやみに追い払おうとするのは危険です。「何か物音がするから、さっさと追い出してしまおう」という考えは禁物。
子育て中のアライグマは普段の3倍も攻撃的になり、威嚇してきます。
屋根裏からガサゴソと音が聞こえる場合は、以下の点に注意が必要です。
- 朝方と夕方に物音が増える場合は子育ての可能性が極めて高い
- 特に春と秋は出産のピーク時期なので要注意
- 子育て中は「餌を守るぞ!」という本能から凶暴性が増している
- 威嚇する声が聞こえたら、すぐにその場から離れる
「3センチ以上の隙間」を徹底的に塞ぐ重要性
アライグマは体の割に驚くほど小さな隙間から侵入できます。「こんな狭い隙間からは入れないだろう」という考えは大きな間違い。
なんと、わずか3センチの隙間があれば、体を押し込んで入り込んでしまうのです。
屋根の隙間対策では以下の場所を重点的に確認しましょう。
- 軒下の端の部分にできた隙間
- 瓦のズレによって生じた屋根材の間の隙間
- 破損して穴が開いている箇所
- 換気口や通気口の周囲の緩んだ部分
雨どい周辺の「定期的な清掃と点検」が決め手に
雨どいの周辺は定期的な点検と手入れが欠かせません。放っておくと、思わぬ侵入口になってしまうんです。
「面倒だから後回しに」は禁物。
特に以下のポイントをしっかりチェックしましょう。
- 雨どいと外壁の接合部分のゆるみをこまめに確認
- 落ち葉や土がたまると足場として利用されるので清掃を忘れずに
- サビや腐食による新たな隙間の発生を早期発見
- 雨どいを支える金具のぐらつきがないか定期確認