アライグマが床下にいる時の対処法【換気口からの侵入に要注意】檜チップと二重ネットで5つの撃退術

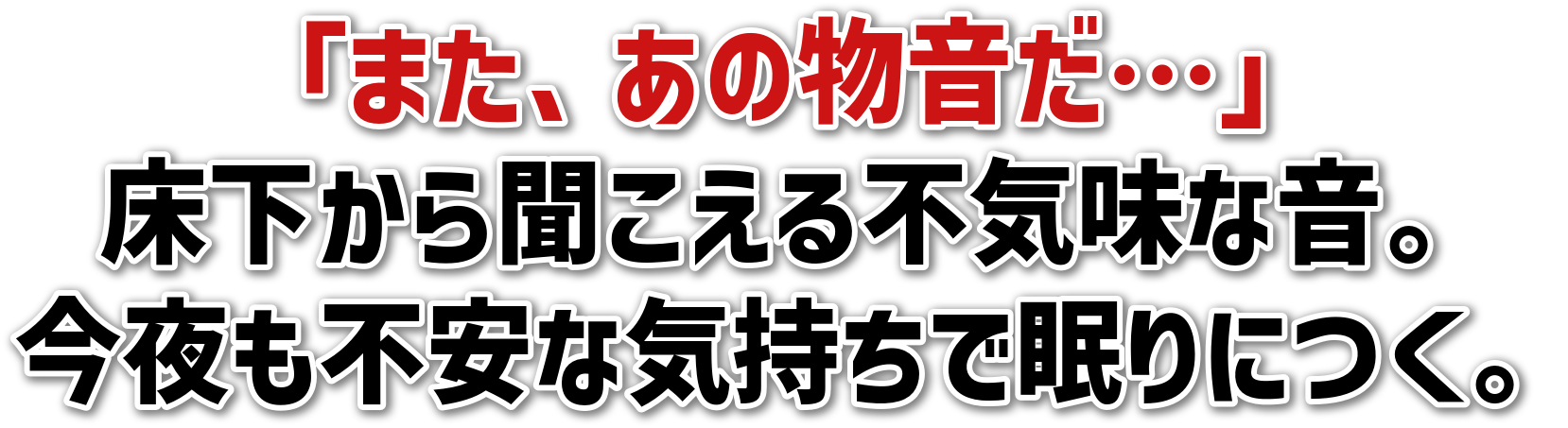
【疑問】
床下から物音がするけど、本当にアライグマなの?
【結論】
夜間の引っかく音や走り回る音、特有の獣臭が換気口から漂えば、アライグマの可能性が極めて高いです。
ただし、自力での追い払いは危険なので、まずは侵入経路となる換気口の防護を優先してください。
床下から物音がするけど、本当にアライグマなの?
【結論】
夜間の引っかく音や走り回る音、特有の獣臭が換気口から漂えば、アライグマの可能性が極めて高いです。
ただし、自力での追い払いは危険なので、まずは侵入経路となる換気口の防護を優先してください。
【この記事に書かれてあること】
真夜中、床下から「ガタガタ」という物音が聞こえてきませんか?- 換気口の3センチの隙間からアライグマが侵入する実態
- 床下での電線被覆の損傷による火災リスクの深刻さ
- 繁殖期と備蓄期で異なる被害パターンの特徴
- 檜チップと二重ネットによる効果的な対策方法
- 床下収納扉の完全密閉と換気口の補強による予防策
これはアライグマが床下に侵入している可能性が高い証拠です。
見過ごすと深刻な被害に発展する恐れがあるため、早めの対策が必要です。
アライグマは換気口のわずか3センチの隙間から侵入し、電線を齧って火災を引き起こしたり、断熱材を巣材にして暖房効率を低下させたりします。
「このままでは家が危ない…」そんな不安を解消するため、檜チップと二重ネットを使った効果的な対策方法をご紹介します。
【もくじ】
床下で聞こえるアライグマの気配と侵入経路

- 換気口から侵入!アライグマの狙う隙間は3センチ
- 暗闇を味方につける「アライグマの夜行性」に注目
- 床下侵入は深夜が危険!自力撃退はNG
換気口から侵入!アライグマの狙う隙間は3センチ
わずか3センチの隙間があれば、アライグマは換気口から床下に侵入できてしまいます。「家の中に入られるなんて、どこかに大きな穴があるはず」と思っている方も多いのですが、それは大きな誤解なんです。
アライグマの体は意外とやわらかく、頭が入る大きさの隙間があれば体も通り抜けられます。
換気口の金網が古くなって錆びていたり、端が少しめくれていたりすると、そこを足掛かりにして金網を広げていきます。
「カリカリ」「ガリガリ」という音が聞こえたら要注意。
金網を噛んで広げている合図かもしれません。
特に注意が必要なのは、建物の北側や東側の換気口です。
なぜなら、こちらは人目につきにくい場所なので、アライグマも警戒せずに作業できるからです。
- 換気口の端が少しでもめくれている
- 金網に錆びが目立つ
- ネジが緩んでガタガタしている
- 昔から点検していない
「まだ大丈夫かな」と様子見をしていると、気づいた時には床下に住み着いてしまっているかもしれません。
暗闇を味方につける「アライグマの夜行性」に注目
アライグマは夜行性の動物で、暗闇の中でも物の輪郭がくっきり見えます。床下は昼でも暗いため、アライグマにとっては天国のような環境なんです。
目の構造が特殊で、暗闇でも3メートル先まではっきり見通せます。
これは、月明かりや街灯の光さえあれば、床下の中を自由に動き回れるということ。
人間の目が不自由な夜中に、アライグマは得意げに活動しているわけです。
「カサカサ」「トコトコ」という足音が聞こえてくるのは、ちょうど人間が就寝する頃。
夜の静けさの中で、床下を我が物顔で歩き回っています。
- 日没直後から活動開始
- 真夜中が活動のピーク
- 明け方に活動終了
- 昼間は床下で熟睡
「夜中に物音がするけど、朝になると静か」という場合は、典型的なアライグマの行動パターンかもしれませんよ。
床下侵入は深夜が危険!自力撃退はNG
深夜0時から午前2時の間が、アライグマの床下侵入が最も多い時間帯です。この時間、人間は熟睡していることが多く、アライグマにとっては絶好のチャンス。
「ガサゴソ」という物音で目が覚めても、焦って自力で追い払おうとするのは危険です。
なぜなら、アライグマは追い詰められると凶暴化する性質があるからです。
暗闇の中で興奮状態のアライグマと対峙すれば、噛みつかれたり引っかかれたりする可能性が高まります。
- 夜中の物音でも決して慌てない
- 暗闇での追い払いは絶対に避ける
- 懐中電灯を床下に向けると逆効果
- 寝室は床下から離れた場所を選ぶ
むしろ、夜間は床下に近づかないようにして、翌朝の明るい時間帯に状況を確認する方が安全です。
「これなら自分でも何とかできそう」と思っても、アライグマの力は侮れません。
被害の進行と深刻化するリスク

- 電線被覆の損傷で火災の危険性が急上昇
- 断熱材が巣材に!暖房効率が激減
- 糞尿被害で土台が腐食!家屋の寿命に影響
電線被覆の損傷で火災の危険性が急上昇
床下の電線被覆が損傷すると、漏電による火災の危険性が高まります。アライグマは電線の被覆を好んで齧り、深刻な事態を引き起こしてしまうんです。
被害の特徴は以下の3つです。
- 被覆が裂かれてむき出しになった電線がショートを起こす
- 齧られた電線同士が接触して発火の原因に
- 被覆を巣材として集めるため、広範囲に被害が広がる
分電盤付近は要注意です。
かじられた跡を見つけたら、すぐに対処が必要になります。
放置すると被害は日に日に広がり、最悪の場合は建物全体を焼失することも。
床下からこげた臭いがする場合は特に危険な状態です。
断熱材が巣材に!暖房効率が激減
アライグマは床下の断熱材を巣作りの材料として使います。その結果、暖房効率が大きく低下してしまうのです。
被害の進行は驚くほど早いもの。
- ふわふわの断熱材を好んでばりばりと裂く
- 巣材として集めた断熱材を床下の広い範囲に散らかす
- 暖房効率が50パーセントも低下する事例も
- 電気代が3倍近くに跳ね上がる
足元からの寒さが気になり始めたら、すでに断熱材が大きく損傷している可能性が。
壁をつたう冷気も要注意です。
糞尿被害で土台が腐食!家屋の寿命に影響
床下での糞尿被害は家屋の寿命を縮める原因となります。アライグマは決まった場所で排泄する習性があり、その場所に糞尿が集中するのです。
被害の特徴を見てみましょう。
- 糞尿に含まれる酸性の成分が木材を腐らせる
- 土台や柱がじわじわと劣化していく
- 湿気との相乗効果で腐食が加速
- 異臭の原因にもなり居住環境が悪化
じめじめした床下環境だと、腐食の進行が早まってしまいます。
季節と時間帯による被害の特徴

- 春の繁殖期vs秋の備蓄期の被害パターン
- 雨の日の滞在時間は晴れの日の3倍に
- 夜間の出入りvs日中の休息場所利用
春の繁殖期vs秋の備蓄期の被害パターン
春と秋では、アライグマの床下利用の目的が大きく異なります。春の繁殖期は母親が子育ての場所として床下を使い、秋は冬に向けた食料の備蓄場所として利用するのです。
春の繁殖期には、「赤ちゃんが生まれたわ!」とばかりに、母親が断熱材を引き裂いて巣材を集めます。
この時期の被害は子育てのための住処作りが中心です。
「早く巣材を集めないと!」と母親が焦る3月下旬から4月上旬は特に被害が深刻になります。
一方、秋の備蓄期は様子が変わります。
- 果物や木の実を床下の隅に集める
- 備蓄場所を確保するために新しい穴を掘る
- 食べ残しが腐って異臭を放つ
- 周辺の餌場と床下を頻繁に行き来する
これが秋の床下被害の特徴というわけです。
雨の日の滞在時間は晴れの日の3倍に
天気によってアライグマの行動は大きく変化します。晴れの日は餌場と床下を頻繁に往復しますが、雨の日は床下での滞在時間が3倍以上に延びてしまうのです。
「雨に濡れるのはいやだなぁ」とばかりに、ずっと床下で過ごすアライグマ。
その間もごそごそと動き回るため、被害は着実に進行していきます。
- 電線の被覆を齧って巣材にする
- 床下の柱や土台を爪で傷つける
- 糞尿による汚染が一箇所に集中する
長雨が続くと床下が完全な住処と化してしまい、「ここが私の家よ」とばかりに居座ってしまいます。
夜間の出入りvs日中の休息場所利用
アライグマの床下利用は、時間帯によってはっきりと分かれています。夜は活発に出入りを繰り返し、日中はじっとりと休息をとるのです。
「さあ、餌を探しに行こう!」と、日没後2時間が最も活発な時間帯。
この時間帯は床下と餌場を何度も往復します。
- 換気口からこっそり出て行く
- 餌を見つけては持ち帰る
- 床下で食事をして休憩する
- また餌場へと向かう
でも油断は禁物。
「人が近づいてきた!」と感じると、急に攻撃的な態度に変わることも。
日中の床下点検は危険が伴うというわけです。
アライグマ対策の5つの効果的な方法

- 檜のチップ散布で「嫌がる香り」を活用!
- 銅線の二重ネットで換気口を完全ガード
- 重曹散布で足跡確認と侵入防止を両立
- 床下点検口の周囲にアルミホイル設置
- 柑橘系アロマオイルで嗅覚を刺激!
檜のチップ散布で「嫌がる香り」を活用!
床下に檜のチップを散布することで、アライグマの嫌う強い香りで侵入を防ぐことができます。香りの強い檜のチップは、アライグマの繊細な嗅覚を刺激して忌避効果を発揮します。
「この場所は危険かもしれない」という警戒心を引き起こすため、床下への侵入を諦めさせる効果があるんです。
散布する際は、次の3つのポイントを押さえましょう。
- 換気口から1メートル以内の範囲に、厚さ3センチ程度に敷き詰める
- 床下全体に均一に散布せず、侵入されやすい場所に集中的に配置する
- 湿気対策として2週間に1回は新しいチップと交換する
実は檜の香り成分は徐々に揮発するため、1回の散布で2週間ほど効果が持続します。
まるで森の中にいるような清々しい香りは、人にとっても心地よく、害虫の予防効果も期待できるというわけです。
散布する時期は、アライグマの活動が活発になる春と秋がおすすめ。
特に3月から5月の繁殖期前に散布すると、巣作りを諦めさせる効果が高くなります。
床下をアライグマの住処にされる前の予防対策として、とても効果的な方法なんです。
銅線の二重ネットで換気口を完全ガード
換気口に銅線でできた目の細かいネットを二重に取り付けることで、アライグマの侵入を物理的に防ぐことができます。なぜ銅線なのでしょうか。
それはアライグマの鋭い歯でも噛み切りにくく、爪でも引き剥がしにくい特徴があるからです。
「普通の金網なら噛み切られちゃうかも」という心配は無用です。
効果的な設置方法は次の通りです。
- 目の大きさが5ミリ四方以下のネットを選ぶ
- 外側と内側で網目の向きをずらして二重に設置する
- ネットの端は3センチ以上折り返して固定する
通気性を確保するため、目の細かすぎるネットは避けるべきです。
「完全に塞いじゃえば安心!」と思いがちですが、それでは床下の湿気対策ができなくなってしまいます。
また、ネットの固定にはステンレス製のネジを使用することをおすすめします。
なぜなら、普通の鉄製のネジは錆びて劣化するため、時間とともにグラグラになってしまうからです。
がっちりと固定することで、アライグマの力強い引っ張りにも負けない頑丈な防御ができるというわけ。
重曹散布で足跡確認と侵入防止を両立
重曹を床下収納の入り口周辺に散布することで、アライグマの足跡を確認しながら侵入も防げます。重曹には2つの大きな効果があります。
1つは足跡がくっきり残るため、侵入の有無がすぐに分かること。
もう1つは、アライグマの繊細な足裏が粉の感触を嫌がって近づかなくなることです。
効果的な散布方法は以下の通りです。
- 床下収納の入り口から30センチ四方に薄く広げる
- 粉の厚さは5ミリ程度を目安にする
- 湿気で固まる前に3日おきに交換する
足跡の大きさや形から、成獣か子どもかの判別ができます。
例えば、前足の幅が6センチを超える大きな足跡なら成獣、3センチ程度の小さな足跡なら子どもと分かるんです。
また、足跡の方向から侵入経路も特定できます。
「ここから入ってきているんだ」と分かれば、その場所を重点的に対策できるというわけです。
さらに重曹には消臭効果もあり、アライグマの残す独特の臭いも軽減できます。
床下点検口の周囲にアルミホイル設置
床下点検口の周囲にアルミホイルを貼ることで、光の反射とホイルの触感でアライグマを警戒させることができます。アライグマは光る物を警戒する習性があり、特に月明かりで反射するアルミホイルを不気味に感じます。
まるで水面のきらめきを警戒するように、近づくことを躊躇するんです。
効果的な設置方法をご紹介します。
- 点検口の周囲50センチの範囲に、しわを寄せて貼り付ける
- 表面のしわは大きめにして光の乱反射を増やす
- 端は補強テープで固定して剥がれを防ぐ
「めんどくさいな」と思うかもしれませんが、破れた部分から侵入される可能性があるので、定期的な確認は欠かせません。
この方法は、玄関先や庭先など、アライグマが頻繁に現れる場所にも応用できます。
光を反射する不安定な地面は、警戒心の強いアライグマにとって近寄りがたい空間となるんです。
柑橘系アロマオイルで嗅覚を刺激!
換気口の周りに柑橘系のアロマオイルを染み込ませた布を設置することで、アライグマの鋭敏な嗅覚を刺激して侵入を防ぐことができます。アライグマは柑橘系の強い香りを特に苦手とします。
「みかんやレモンの皮を置けばいいの?」と思われるかもしれませんが、生の果物は逆に誘引効果があるので要注意。
アロマオイルなら餌として認識されることはありません。
効果的な設置方法は次の通りです。
- 不織布に3滴程度染み込ませる
- 換気口から20センチ以内に設置する
- 雨の当たらない場所を選んで配置する
特に雨天時は香りが弱まりやすく、効果も低下します。
また、アロマオイルは原液のまま使わず、必ず不織布などに染み込ませて使用しましょう。
香りの強さは、人間が「ほのかに感じる」程度で十分です。
アライグマの嗅覚は人間の7倍以上も敏感なので、控えめな香りでも十分な忌避効果が得られるというわけです。
被害予防のための重要ポイント
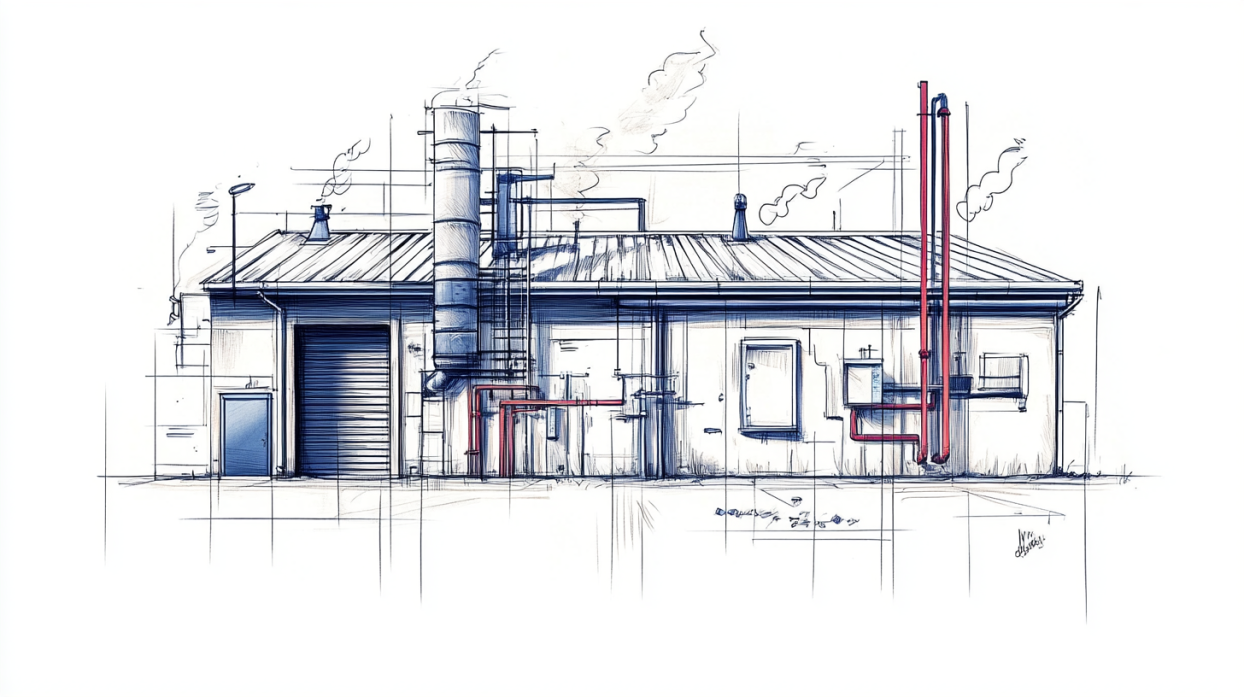
- 換気口の補強は通気性と強度がカギ!
- 床下収納の扉は完全密閉が必須
- 敷地内の果樹や生ごみは即撤去
換気口の補強は通気性と強度がカギ!
換気口の補強には、通気性を保ちながら強度を確保することが最も重要です。「換気口を完全に塞いでしまえば安全なのに」と思いがちですが、それは大きな間違いなんです。
湿気がこもって土台が腐ってしまうため、適切な通気は必要不可欠です。
対策のポイントは以下の3つです。
- 目の細かい銅線のネットを二重構造で取り付ける
- ネットの四隅をステンレス製の金具で固定する
- 3か月ごとにネットの緩みや破損を点検する
これはアライグマが金網を噛んでいる証拠です。
補強が不十分な場合、たった一晩で侵入されることも。
床下収納の扉は完全密閉が必須
床下収納の扉は、わずかな隙間も見逃さない徹底的な密閉が必要です。アライグマは3センチの隙間があれば侵入できる器用さを持っているんです。
「カタカタ」という扉の音は、すでに侵入を試みている証拠かもしれません。
対策として以下の点に気をつけましょう。
- 扉の四隅に隙間テープを貼る
- 留め金は二重ロック式に交換する
- 扉の周りに防護板を設置する
扉が完全に閉まらないままでは、いつの間にか巣を作られてしまいます。
敷地内の果樹や生ごみは即撤去
アライグマを寄せ付けない環境作りの第一歩は、餌となる果樹や生ごみの撤去です。「庭木なんて関係ないでしょ」と思うかもしれませんが、実はこれが重要なポイントなんです。
アライグマは敷地内の食べ物を求めてやってきます。
以下の対策を心がけましょう。
- 果樹は収穫前の実をこまめに摘む
- 生ごみは蓋付きの容器に保管する
- 落ち葉の下の虫や小動物も餌になるため掃除する