アライグマの巣はどこにある?【物置や屋根裏が巣の定番】周辺環境と季節で巣の場所が変化!

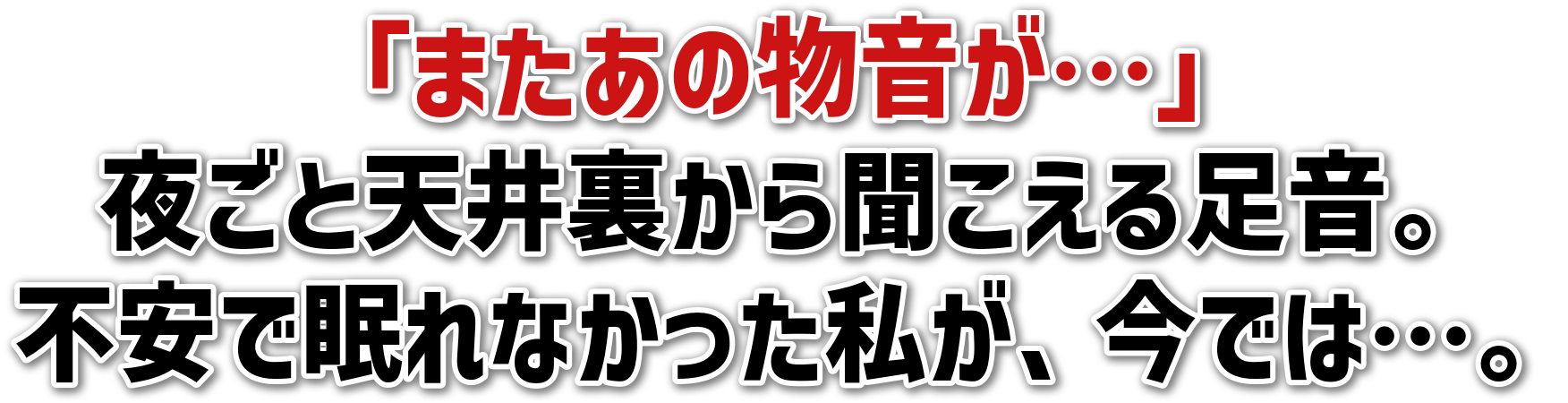
【疑問】
アライグマはどんな場所に巣を作りやすいの?
【結論】
物置や屋根裏など、日当たりが悪く人目につきにくい高所を好んで巣にします。
ただし、餌場から100メートル圏内で複数の逃げ道が確保できる場所を選ぶ特徴があります。
アライグマはどんな場所に巣を作りやすいの?
【結論】
物置や屋根裏など、日当たりが悪く人目につきにくい高所を好んで巣にします。
ただし、餌場から100メートル圏内で複数の逃げ道が確保できる場所を選ぶ特徴があります。
【この記事に書かれてあること】
「物置の中からガサガサという音が聞こえる…」「屋根裏から子どもの泣き声のような音が…」こんな不安な夜を過ごしていませんか?- アライグマは物置や屋根裏に巣を作る習性がある
- 巣の大きさは直径50センチほどの円形で入口は小さい
- 巣は餌場から100メートル圏内に作られる
- 季節によって巣の場所が変化する特徴がある
- 巣への5つの効果的な対策方法で撃退可能
- 子育て中の巣への対策は時期を慎重に選ぶ必要がある
実はこれ、アライグマが巣作りを始めている可能性が高いんです。
巣を放置すると建物が破壊される恐れも。
でも安心してください。
アライグマの習性を知れば、効果的な対策が見えてきます。
巣の作られやすい場所や特徴を把握して、賢く撃退する方法をご紹介します。
【もくじ】
アライグマの巣の場所と特徴を把握しよう

- 物置や屋根裏に「繁殖用の巣」を作る習性に注目!
- 巣は直径50センチ!入口は15センチの小さな穴に注意
- 巣の中をのぞくのは危険!子育て中は特に要注意
物置や屋根裏に「繁殖用の巣」を作る習性に注目!
アライグマは人家の物置や屋根裏を巣として選ぶ習性があり、特に断熱材の近くを好みます。「この辺りなら巣作りにぴったりね」とでも考えているのか、アライグマは周囲の環境を細かくチェックしながら巣作りの場所を決めるんです。
選ぶ条件は実に厳密で、まるで不動産を探すように慎重です。
- 人目につきにくい暗い場所であること
- 雨風を防げる屋根があること
- 断熱材があり温かい場所であること
- 天井裏や物置の奥など、奥まった場所であること
「子どもを育てるなら、この場所が一番安全ね」という具合です。
巣作りの前には必ず下見を行い、夜間に何度も周辺を偵察します。
建物の強度や人の生活音、光の有無まで確認する徹底ぶり。
このように入念な準備を経て、ようやく巣作りが始まるというわけです。
巣は直径50センチ!入口は15センチの小さな穴に注意
アライグマの巣は、直径50センチメートルの円形で、入口はわずか15センチメートルの小さな穴。この小ささが見つけにくさの原因です。
巣の構造は実に巧妙。
まるで建築の専門家のように、機能性と快適さを兼ね備えた空間を作り上げます。
- メインの入口は高さ2メートル以上の場所に作られる
- 非常口として複数の出入り口を確保
- 入口は下向きに掘られ、雨水が入りにくい構造
- 内部は寝床・子育て・餌保管の3つのスペースに区分け
「寒い夜も快適に過ごせそう」とでも考えたのか、保温性にもこだわっているんです。
巣の入口は目立たないよう慎重に作られ、時には建材をかじって穴を広げることも。
このため、家屋への被害が深刻になることも少なくありません。
巣の中をのぞくのは危険!子育て中は特に要注意
巣の中をのぞき込むことは絶対に避けましょう。特に子育て中のアライグマは警戒心が強く、攻撃的になります。
「子どもを守らなきゃ」という母性本能が強く働くため、普段は警戒心が強いアライグマがさらに危険な存在に。
巣に近づくだけでガルルッと低い唸り声を上げて威嚇してきます。
- 子育て中は半径50メートル以内を縄張りとして警戒
- 巣の近くでは鋭い歯で攻撃してくる可能性大
- 子どもがいる場合は特に攻撃性が高まる
- 巣の確認は必ず日中の静かな時間帯に
「この子たちを守るためなら何でもする」という母親の強い意志が、時として人への攻撃的な行動となって現れるんです。
アライグマが巣を作りやすい環境の特徴

- 日当たりの悪い場所に「隠れ家」を作る習性
- 餌場から100メートル圏内に巣を作る特徴
- 複数の逃げ道を確保できる場所を選ぶ傾向
日当たりの悪い場所に「隠れ家」を作る習性
アライグマは薄暗く人目につきにくい場所を好んで巣を作ります。建物の北側や木々に囲まれた場所が特にお気に入り。
巣作りに適した環境には、次のような特徴があるんです。
- 日光が直接当たらない場所で、一日中ほとんど明るくならないスペース
- 建物の陰になっていて、近所から見えづらい隠れた場所
- 雨風をしのげる屋根や壁があり、外敵から身を守りやすい環境
- 人の出入りが少なく、静かでひっそりとした空間
特に断熱材の近くは、すぐに巣が作られやすい要注意ポイントなのです。
餌場から100メートル圏内に巣を作る特徴
アライグマは餌場の近くに巣を作る習性があります。餌を探しに行く時のことを考えて、効率よく行動できる場所を選ぶんです。
- 生ゴミ置き場や果樹園から100メートル以内の場所を選ぶ
- 水場までの距離が50メートル以内になるよう計算して巣を作る
- 畑や池がある民家の物置や屋根裏を特に好んで選ぶ
- 夜間に餌を探しに行きやすい環境かどうかをしっかり確認
複数の逃げ道を確保できる場所を選ぶ傾向
アライグマはぱぱっと逃げられる道筋を確保できる場所を選びます。周囲の環境をよく観察して、安全な巣作りの場所を決めているんです。
- 建物の角や段差を利用して、すばやく方向転換できる場所
- 木々や塀が連なり、とんとん飛び移れる環境がある場所
- 排水管や雨どいがあり、さっと逃げ込める構造になっている場所
- 高さ2メートルまでの範囲に、3方向以上の逃げ道がある環境
アライグマの巣の比較と分析

- 物置vs屋根裏!巣として選ばれやすいのは後者
- 高所の巣vs地上の巣!安全性は高所が圧倒的
- 春の巣vs秋の巣!季節で変わる巣の条件
物置vs屋根裏!巣として選ばれやすいのは後者
アライグマが巣作りに選ぶ場所は、物置よりも屋根裏の方が圧倒的に多いのです。「なぜ屋根裏が好まれるのかしら?」という疑問に答えていきましょう。
屋根裏は、アライグマにとって3つの大きな魅力があります。
- 断熱材があるため、真夏も真冬も温度が安定している
- 天井裏の構造材で体を休めやすく、寝床作りが簡単
- 人の目につきにくく、外敵の侵入もほとんどない
梁と梁の間にすっぽりと体が収まり、断熱材をほぐして柔らかな寝床が作れるからです。
一方、物置は人の出入りが多く、道具の出し入れでガタガタと音が響きます。
「こんな落ち着かない場所では子育てもできない!」とアライグマも考えるのでしょう。
ただし、倉庫のように広くて人の出入りが少ない物置は、巣として選ばれることもあります。
高所の巣vs地上の巣!安全性は高所が圧倒的
アライグマの巣作りでは、地上より高所が選ばれる傾向にあります。その理由は安全性にあるんです。
高所の巣には、地上では得られない4つの利点があります。
- 犬や猫などの天敵から身を守りやすい
- 見晴らしが良く、危険を素早く察知できる
- 雨や風の影響を受けにくい
- 子育ての際に外敵から赤ちゃんを守れる
「建物の方が天候に左右されないし、餌場にも近いもの」というわけです。
地上の巣は、イタチやキツネなどの天敵に襲われやすく、雨で巣が水浸しになることも。
そのため、やむを得ない場合を除いて地上に巣を作ることは少ないんです。
「せっかく作った巣が台無しになっちゃう」というのは、アライグマにとって大きなストレスなのです。
春の巣vs秋の巣!季節で変わる巣の条件
アライグマの巣作りは季節によって大きく変化します。春と秋では、まるで別の生き物かと思うほど巣の条件が変わるんです。
春の巣作りでは、こんな特徴が見られます。
- 暖かく乾燥した場所を選ぶ
- 巣の入口を南向きに作る
- 柔らかい布や紙を集めて産室を作る
- 巣の周囲を頑丈に固める
「お腹いっぱいになれる場所が近くにないと困る」というわけで、果樹園や菜園の近くに作られることが多いんです。
面白いことに、春の巣は長期滞在型なのに対し、秋の巣は仮設住まいのような作りになります。
「春は子育てに専念したいから丈夫な巣を」「秋は餌を求めて移動が多いから簡易な巣で十分」というように、季節に応じて巣作りの方針をしっかり変えているのです。
アライグマの巣を5つの対策で撃退

- 巣の周囲に「強い香り」で寄せ付けない工夫
- 光と音の組み合わせで警戒心を刺激する方法
- 足音が気になる地面で接近を防ぐテクニック
- 天敵の存在を匂いで感じさせる裏技
- 巣の周辺に不快な環境を作る具体策
巣の周囲に「強い香り」で寄せ付けない工夫
アライグマは強い香りが大の苦手。梅酢や柑橘系の香り、にんにくなどの刺激臭を上手に活用することで、巣作りを効果的に防ぐことができます。
「この場所は危険そうだな」とアライグマに思わせることが大切なんです。
特に効果的なのが、梅酢に古着を浸して巣の周囲に設置する方法です。
香りを使った対策には、次のような種類があります。
- 梅酢を染み込ませた古着を2メートルおきに設置(週1回の交換が必要)
- みかんやレモンの皮を乾燥させて巣の周囲に散布(3日おきに交換)
- にんにくを熱湯で溶かして巣の周辺に散布(2日おきの散布が必要)
- ミントの鉢植えを巣の出入り口付近に配置(定期的な水やりが必要)
「香りが弱くなってきたかな」と感じたら、すぐに新しいものと交換しましょう。
また、雨が降ると効果が弱まってしまうので、屋根のある場所に設置するのがおすすめです。
「せっかく設置したのに効果がない」というケースの多くは、香りが薄れてしまっているのが原因なんです。
光と音の組み合わせで警戒心を刺激する方法
アライグマは光と音の変化に敏感です。この習性を利用して、巣作りをあきらめさせることができます。
「人がいるぞ!」とアライグマに思わせるのが効果的。
光と音を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。
具体的な対策方法をご紹介します。
- アルミホイルを広げて設置(光の反射と足音で警戒心を刺激)
- 風鈴を複数設置(不規則な音で警戒心を高める)
- センサー式のライトを設置(突然の光で驚かせる)
- ラジオを小さな音量で夜間に流す(人の気配を演出)
「キラキラ」と反射する光と、「チリンチリン」という不規則な音で、アライグマの警戒心を最大限に刺激します。
ただし、近隣への配慮も忘れずに。
音が大きすぎると苦情の原因になってしまいます。
また、強風で飛ばされないよう、しっかりと固定することも大切です。
「効果があるからといって、やりすぎは禁物」というわけです。
足音が気になる地面で接近を防ぐテクニック
アライグマは静かに近づくことを好む動物です。足音が響く地面をうまく作ることで、巣への接近を効果的に防ぐことができます。
「カサカサ」「ジャリジャリ」という音が鳴る地面は、アライグマにとって大きなストレス。
この習性を利用して、巣への接近を諦めさせましょう。
効果的な地面作りの方法をご紹介します。
- 砂利を敷き詰める(直径2メートル以上の範囲に必要)
- 松ぼっくりを散らす(50個以上を地面に配置)
- 重曹を撒く(足跡が付きやすい地面に)
- 乾燥した落ち葉を厚めに敷く(歩くと音が鳴る)
「ジャリッ」という足音が気になって、アライグマは近づきたがりません。
ただし、範囲が狭いと迂回されてしまうので、巣の周囲を広めに覆うことが大切です。
また、これらの材料は定期的な補充が必要です。
雨で流されたり、風で飛ばされたりするので、「少なくなってきたかな」と思ったら追加しましょう。
特に重曹は雨に弱いので、天気の良い日に撒き直すことをおすすめします。
天敵の存在を匂いで感じさせる裏技
アライグマは天敵の存在を察知すると、その場所を避けるようになります。この習性を利用して、巣への接近を防ぐことができるんです。
「ここは危険な場所だ」とアライグマに思わせることが重要です。
特に効果的なのが、猫の存在を匂いで感じさせる方法です。
具体的な対策をご紹介します。
- 使用済みの猫砂を巣の近くに置く(雨に濡れない場所に設置)
- 猫の毛を集めて巣の周囲に撒く(風で飛ばないよう固定)
- 猫の食器を空のまま置く(餌は置かない)
- 猫用の爪とぎを設置(猫の縄張り感を演出)
「匂いがきつければ効果が高い」と考えがちですが、それは大きな間違い。
自然な天敵の気配を演出することが、より効果的なんです。
また、これらの対策は2日おきの交換が必要です。
匂いが薄れると効果も弱まってしまうので、こまめな管理を心がけましょう。
巣の周辺に不快な環境を作る具体策
アライグマは快適な環境を求める動物です。巣の周辺を不快な環境にすることで、新たな巣作りを防ぐことができます。
「この場所は住みにくそうだな」とアライグマに感じさせることが大切です。
複数の対策を組み合わせることで、より高い効果が期待できます。
不快な環境を作る方法をご紹介します。
- タバスコを染み込ませた布を置く(3日おきの交換が必要)
- 竹串を地面に立てる(10センチ間隔で設置)
- 防鳥網を張る(隙間を作らないよう注意)
- 木酢液を散布する(週2回の散布が必要)
ただし、散布する際は手袋を着用し、皮膚に直接触れないよう注意が必要です。
また、これらの対策は建材を傷める可能性があるので、使用する場所には気を付けましょう。
「効果があるから」と言って、むやみに使うのは禁物というわけです。
アライグマの巣への注意と配慮事項

- 巣の確認は「日中の静かな時間帯」を選択!
- 子育て中の巣への対策は時期を慎重に判断
- 巣の撤去後は必ず消毒と補修を実施!
巣の確認は「日中の静かな時間帯」を選択!
巣の確認作業は、アライグマが休んでいる昼間の静かな時間帯に行うのがポイントです。物音を立てずそっと近づきましょう。
「きっと今なら大丈夫」と油断して急に大きな音を立ててしまうと、驚いたアライグマが攻撃的になってしまいます。
巣の確認時は次の3つの点に気をつけましょう。
- 朝9時から午後3時までの間を選ぶ
- 物を落としたりガタガタ音を立てたりしない
- 懐中電灯はソッと照らし、チカチカさせない
「あっ、面白そう!」と近づいていって危険な目に遭うことも。
子育て中の巣への対策は時期を慎重に判断
巣の中で子育てをしているときは、アライグマの警戒心がとても強くなっています。子育て中の巣に近づくと、母親が「子どもを守らなきゃ!」と攻撃的になり危険です。
子育て期の見分け方は以下の特徴で分かります。
- 夜中にキュッキュッという子どもの鳴き声
- 巣の出入りが活発になる
- 周辺に餌の食べ残しが増える
母親の攻撃性が高まっているんです。
巣の撤去後は必ず消毒と補修を実施!
アライグマの巣を撤去したら、跡地の消毒と補修が重要です。「もう来ないだろう」と放っておくと、また新しい巣を作られてしまいます。
巣の跡地には次のような対策が必要なんです。
- 消毒液での念入りな清掃と乾燥
- 隙間や穴の完全な埋め合わせ
- 断熱材の交換や電気配線の点検