アライグマを寄せ付けない方法とは【誘引物を徹底排除】3センチの隙間と香りで完全対策!

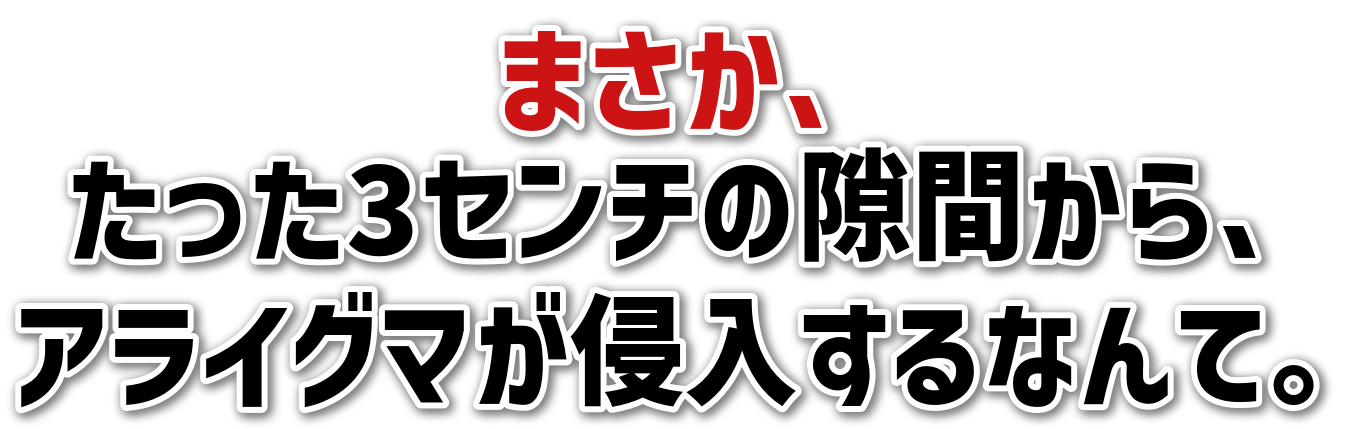
【疑問】
アライグマを完全に寄せ付けないためには何から始めるべき?
【結論】
まずは庭や建物周辺の誘引物を徹底的に排除することから始めます。
ただし、誘引物の排除と同時に3センチ以上の隙間も塞いで、物理的な侵入防止策も講じる必要があります。
アライグマを完全に寄せ付けないためには何から始めるべき?
【結論】
まずは庭や建物周辺の誘引物を徹底的に排除することから始めます。
ただし、誘引物の排除と同時に3センチ以上の隙間も塞いで、物理的な侵入防止策も講じる必要があります。
【この記事に書かれてあること】
アライグマの被害に困っていませんか?- 誘引物の排除から始める基本的な環境整備
- 侵入経路となる3センチの隙間の徹底的な封鎖
- 日没後2時間の警戒時間帯に重点を置いた対策
- 柑橘系の香りと音を活用した5つの心理的撃退法
- 物置やデッキ下の定期的な点検による予防策
庭に足跡を見つけたり、物置が荒らされたりと、厄介な事態に頭を抱えている方も多いはず。
でも、実はアライグマは意外と臆病な動物なんです。
「もう困り果てて…」という方も、正しい対策を知れば簡単に寄せ付けなくすることができます。
今回は、誘引物の管理から建物の隙間対策まで、アライグマを撃退するための具体的な方法をくわしく解説します。
日没後の2時間が特に重要なポイントですよ。
【もくじ】
アライグマを寄せ付けない環境作り

- 誘引物の「徹底排除」が最重要ポイント!
- 敷地内の落下果実は「即日撤去」が基本!
- 生ゴミの放置は「絶対にNG」の習慣!
誘引物の「徹底排除」が最重要ポイント!
アライグマを引き寄せる原因の9割は、餌となるものの放置です。まずはこれらの誘引物を完全になくすことから始めましょう。
「どうしてまた来るんだろう?」と頭を悩ませている方も多いはず。
実は、私たちが気づかないうちに餌場を作ってしまっているんです。
アライグマが喜ぶ誘引物には、主に次の3つがあります。
- 生ゴミや食べ残し
- ペットフードの置き忘れ
- 果樹の実や野菜くず
「昼間に片付ければいいや」という考えはとても危険。
アライグマは夜行性なので、日没後に餌を探して活発に動き回るからです。
誘引物の管理は毎日の習慣づけが大切です。
夕方になったら必ずチェックする項目を決めておきましょう。
例えば、「ごろごろ」と物音がしたら、それはアライグマが餌を探している合図。
すぐに原因を特定して対策を取る必要があります。
「めんどくさいなぁ」と思っても、毎日の小さな積み重ねが大切。
誘引物を完全になくせば、アライグマは自然と別の場所へ移動していきます。
敷地内の落下果実は「即日撤去」が基本!
落下した果実は、アライグマにとって格好のごちそう。放置すれば必ず寄ってくるので、見つけたらすぐに片付けましょう。
みかんやりんごなどの果樹がある庭では、特に気を付けたいポイントがあります。
- 熟した実は早めに収穫
- 落ちた実は毎日拾い集める
- 腐った実は土に埋めない
アライグマの嗅覚は非常に優れていて、たった1個の果実の匂いでも遠くから感知できるんです。
果樹の管理は収穫2週間前が特に重要。
この時期は実が柔らかくなり始め、アライグマが最も興味を示す時期なのです。
「ぽとり」と音がしたら要注意。
夜間に探しに来る前に、必ず片付けておきましょう。
庭の果樹は見た目の良さだけでなく、実をつける時期の管理も考えて植えることが大切です。
手が回らないようなら、思い切って伐採することも検討しましょう。
生ゴミの放置は「絶対にNG」の習慣!
生ゴミの管理の甘さは、アライグマを呼び寄せる大きな原因です。「臭いくらいなら」と放置すると、とんでもないことになってしまいます。
生ゴミ対策で特に気を付けたい時間帯は、夕方から夜明けまで。
アライグマは日没後2時間が最も活発になるため、この時間帯の生ゴミは絶対に外に置かないようにしましょう。
具体的な対策方法を見てみましょう。
- 密閉容器での保管を徹底
- 生ゴミネットは夜間禁止
- コンポストは蓋付きを使用
- 魚や肉の生ゴミは冷凍保存
それはアライグマが生ゴミを漁っている証拠かもしれません。
一度でも餌にありつけると、アライグマは毎日のように訪れるようになります。
「ここに餌があるはず」という学習をしてしまうので、生ゴミの管理は絶対に手を抜かないことが大切なんです。
建物周辺の環境整備のポイント

- 侵入経路となる「3センチの隙間」をチェック!
- 物置やデッキ下は「高頻度点検」が重要!
- 屋根裏への「進入口」を完全封鎖!
侵入経路となる「3センチの隙間」をチェック!
アライグマは体の割に小さな隙間から侵入できます。わずか3センチの隙間があれば、頭が入る場所には必ず体が通れてしまうんです。
建物の周りを点検する際は、以下の場所を重点的に確認しましょう。
- 換気口や通気口まわりの目の細かい金網の破れ
- 壁と床の接合部分にできたわずかな隙間
- 屋根と外壁の間のすき間や破損箇所
- 古くなって緩んだ軒下の板
見落としがちな場所なので、懐中電灯を使ってじっくりと確認します。
隙間を見つけたら、金網や板で塞いで対策を。
物置やデッキ下は「高頻度点検」が重要!
物置やデッキの下は、アライグマの格好の隠れ家になります。まずは物置の周りやデッキの下を毎日のようにチェック。
足跡や糞の有無をこまめに確認することが大切です。
- 物置の床下や壁際の隙間をくまなくチェック
- デッキ下の暗がりをライトで照らして確認
- 柱や支柱の腐食による穴や隙間を点検
- 基礎部分の地面との間の空間をチェック
すぐに隙間を塞いで、侵入を防ぎましょう。
屋根裏への「進入口」を完全封鎖!
屋根裏は暖かく乾燥した空間なので、アライグマが巣作りに使いたがる場所なんです。特に春先は要注意。
以下のポイントを重点的に点検して、しっかり対策しましょう。
- 軒天井の破損箇所や劣化した部分
- 雨どいと外壁の接合部分のゆるみ
- 屋根の通気口まわりの金網の状態
- 棟板金のずれや浮き上がり
アライグマは力が強いので、簡単な応急処置では突破されてしまいます。
時間帯と場所での比較

- 日中vsライトアップ時の行動パターン!
- 庭と物置の被害率に大きな差!
- 収穫前と収穫後で活動量が激変!
日中vsライトアップ時の行動パターン!
アライグマの活動は日没後2時間がピークです。日中とライトアップ時では、その行動パターンが大きく変わります。
「お昼は静かなのに、夜になるとごそごそ音がする」という経験はありませんか?
実は日中、アライグマは物陰でじっとしているんです。
日中の行動は最小限。
木の上や物置の中でうとうと過ごしています。
ところが日没を迎えると、様子ががらりと変わります。
- 日中(午前6時〜午後6時):ほとんど動かず、物陰で休息
- 日没直後(午後6時〜8時):活動を開始し、周辺を探索
- 夜間(午後8時〜深夜0時):最も活発に行動
- 未明(深夜0時〜午前6時):活動は徐々に低下
「そろそろ動き出すかな」と警戒を緩めた瞬間を狙って行動を開始します。
この時間帯は警戒を強める必要があります。
ライトアップ時は逆に警戒心が強まり、物陰に隠れる傾向が。
でも慣れてくると、明るい場所でも平気で行動するようになってしまいます。
庭と物置の被害率に大きな差!
アライグマの被害は、庭と物置で大きな差が出ます。実は物置の被害率は庭の3倍以上なんです。
「庭は時々荒らされる程度だから大丈夫」なんて油断は禁物。
物置を放置していると、あっという間に住みついてしまいます。
被害の特徴を見てみましょう。
- 庭の被害:果実の食害、植物の踏み荒らし、地面の掘り返し
- 物置の被害:天井裏への侵入、断熱材の破壊、配線の切断
- 被害の頻度:庭は週1〜2回、物置は連日
それは物置が「隠れ家として最適」だからです。
「ここなら安心して子育てができる」とアライグマは考えているんです。
特に春先は要注意。
「子育ての季節だから、安全な場所を探しているはず」という心理を理解して、早めの対策が必要です。
収穫前と収穫後で活動量が激変!
果樹の実りは、アライグマの活動量を左右する重要な要素です。収穫前と収穫後では、その行動パターンが劇的に変化します。
収穫2週間前になると、アライグマの活動が急増。
「もうすぐ実がなる」と察知して、毎晩のように姿を見せるようになります。
具体的な変化をみてみましょう。
- 収穫2週間前:1日3〜4回の侵入を繰り返す
- 収穫適期:夜間中ずっと周辺をうろつく
- 収穫後1週間:侵入回数が1日1回程度に減少
- 収穫後2週間:ほとんど姿を見せなくなる
甘い香りに誘われて、普段の警戒心を忘れてしまうことも。
「今のうちに食べておかないと」という焦りから、夜明け前まで執着することもあります。
特に収穫3日前が最も危険。
完熟直前の果実に執着し、何度追い払っても戻ってくる状態になります。
アライグマを寄せ付けない5つの裏技

- 柑橘系の香りで「縄張り意識」を刺激!
- 防犯ライトで「警戒心」を引き出す!
- 風鈴の音で「不安感」を与える!
- トゲのある植物で「物理的な防御」を!
- コーヒーかすで「嫌悪感」を演出!
柑橘系の香りで「縄張り意識」を刺激!
柑橘系の香りには、アライグマの警戒心を引き出し、縄張り意識を刺激する効果があります。特にレモンとみかんの皮は、アライグマが本能的に避けたがる成分を含んでいます。
「この場所は危険かもしれない」とアライグマに思わせることが大切なんです。
庭や物置の周りに、乾燥させた柑橘類の皮を置くだけで、すぐに効果が表れ始めます。
具体的な活用方法をご紹介します。
- レモンの皮を天日干しにして、玄関や窓際に2日おきに置き換える
- みかんの皮を細かく刻んで、物置の周囲にふりかける
- 柑橘系の果物の皮を網袋に入れて、庭の要所に吊るす
- 果物の皮を乾燥させて粉末にし、侵入されやすい場所に散布する
「これなら簡単にできそう!」と思っても、放置すると逆効果になってしまいます。
天気予報をこまめにチェックして、雨の日は屋内に取り込むようにしましょう。
「毎日やるのは面倒くさいな」という方には、ゆずの皮がおすすめ。
ゆずは他の柑橘類と比べて、香りが長持ちするという特徴があります。
週に1回の交換で十分な効果を発揮してくれますよ。
防犯ライトで「警戒心」を引き出す!
突然の明るい光は、夜行性のアライグマにとって最も警戒する要素の一つです。防犯ライトを効果的に設置すれば、アライグマの警戒心を最大限に引き出すことができます。
アライグマの行動習性に合わせた設置がポイント。
「きっと高い位置が効果的なはず」と思いがちですが、それは大きな間違い。
アライグマの目線の高さ、つまり地上から30〜50センチメートルの位置に設置するのが効果的なんです。
具体的な設置のコツをご紹介します。
- 物置や庭木の周りに、地面から40センチメートルの高さで設置
- 明るさは800〜1000ルーメンを選び、まぶしさで威嚇
- センサーの反応範囲を5メートル以内に設定し、確実に作動させる
- 複数のライトを設置する場合は、光が交差するように配置
この時間帯はアライグマが最も活発に活動する時間なので、確実にライトが作動する状態を保っておくことが大切です。
「電気代が気になるな」という方には、ソーラー式がおすすめ。
昼間の太陽光で充電できるので、維持費を抑えながら効果的な対策が可能です。
ただし曇りや雨の日が続くと充電不足で明るさが落ちるので、そんなときは予備の電池式ライトを併用するといいでしょう。
風鈴の音で「不安感」を与える!
不規則な音は、アライグマの警戒心を刺激する効果があります。特に風鈴の澄んだ音色は、アライグマの敏感な聴覚を刺激し、強い不安感を与えることができます。
ただし、風鈴の設置場所と高さが重要です。
「できるだけ高い位置がいいはず」と考えがちですが、それは大きな誤り。
アライグマの耳の高さ、つまり地上から50センチメートルほどの位置に設置するのが効果的なんです。
設置のコツをご紹介します。
- 物置の軒下や庭木の枝に、地面から50センチメートルの高さで吊るす
- 複数の風鈴を3メートルほどの間隔で配置し、音の死角を作らない
- ガラス製の風鈴を選び、澄んだ高い音色を活用する
- 風の通り道を考慮して、適度に音が鳴る場所を選ぶ
夜間の音が気になる場合は、日没後に短めの紐に付け替えることで、音を抑えることができます。
「ご近所迷惑になるかも」と心配な方は、昼間だけ設置する方法もありますよ。
「風が弱い日は効果が薄れそう」という方には、風鈴と一緒にすずらんテープを取り付けるのがおすすめ。
わずかな風でもひらひらと動いて、視覚的な威嚇効果も期待できます。
トゲのある植物で「物理的な防御」を!
トゲのある植物は、アライグマに対する自然な防御壁として機能します。特にバラやヒイラギは、鋭いトゲが侵入を物理的に防ぐだけでなく、視覚的な威嚇効果も高いんです。
植え付けの位置が効果を左右します。
「庭全体に植えれば安心」と思いがちですが、それは逆効果。
アライグマの侵入経路に的を絞って植えることで、より確実な防御が可能になります。
効果的な植栽方法をご紹介します。
- 窓の下に連続して植え、侵入路を完全に遮断する
- 物置の周りを囲むように配置し、隠れ場所をなくす
- フェンスに這わせて、よじ登りを防止する
- 庭の境界線に沿って列状に植え、防御ラインを作る
放置して伸び過ぎると、逆にアライグマの隠れ家になってしまうことも。
春と秋の年2回、しっかりと剪定を行いましょう。
「手入れが大変そう」という方には、這性バラがおすすめ。
地面を這うように広がる性質があり、剪定の手間が比較的少なくて済みます。
フェンスの下部に植えれば、自然な防御帯が作れますよ。
コーヒーかすで「嫌悪感」を演出!
コーヒーかすの強い香りには、アライグマを遠ざける効果があります。敏感な嗅覚を持つアライグマは、コーヒーかすの苦みのある香りを不快に感じ、その場所を避けるようになるんです。
設置方法が効果を大きく左右します。
「そのまま地面に置けば十分」と考えがちですが、それでは効果は半減。
防水加工した容器に入れて設置することで、香りを長持ちさせることができます。
活用方法をご紹介します。
- 古い靴下にコーヒーかすを詰めて、侵入口付近に吊るす
- 網袋に入れて物置の軒下に設置し、雨よけをする
- プランターの土に混ぜ込み、長期的な効果を狙う
- 防水容器に入れて庭の要所に配置する
「せっかく置いたのに効果が薄い」という場合は、水分で香りが弱まっている可能性が高いんです。
2日に1回は新しいものと交換して、常に強い香りを保ちましょう。
「面倒な作業は避けたい」という方には、市販の園芸用土に混ぜ込む方法がおすすめ。
雨に濡れても効果が長持ちし、1週間に1回の交換で十分な効果を発揮してくれます。
失敗しないための重要ポイント

- ペットフードの「放置厳禁」を徹底!
- 侵入防止策の「設置位置」に要注意!
- 雨樋は「定期清掃」で対策を!
ペットフードの「放置厳禁」を徹底!
ペットフードの放置は、アライグマを引き寄せる最大の原因です。「えさの匂いがするぞ」とすぐに気づかれてしまうため、細心の注意が必要です。
特に夕方からの管理が重要で、日没前には必ず屋内に片付けましょう。
屋外で与える場合は、以下の3つのポイントを意識します。
- 食べ終わったらすぐに容器を回収
- こぼれた分は床からていねいに拭き取る
- 給餌場所は毎回水で洗い流す
侵入防止策の「設置位置」に要注意!
防護ネットや金網の設置位置が不適切だと、かえってアライグマの足場になってしまいます。「これで完璧!」と思っても、ずれてすき間ができていては逆効果なんです。
設置時は以下の項目に気をつけましょう。
- 建物の壁から10センチ以上離して設置
- 地面との間は3センチ以下に調整
- 支柱はぐらつかないよう深く埋める
- ネットの端は必ず固定具で留める
雨樋は「定期清掃」で対策を!
雨樋はアライグマの重要な侵入経路となります。「落ち葉が詰まってるな」と放置していると、足場として活用されてしまうのです。
月1回は以下のポイントを確認しましょう。
- 落ち葉や土でつまりがないか点検
- 継ぎ目の緩みをしっかり補修
- 支持金具の破損がないか確認
- 樋受け金具の固定状態をチェック