アライグマのフンから分かること【新鮮なフンは要警戒】記録と対策で被害を防ぐ!

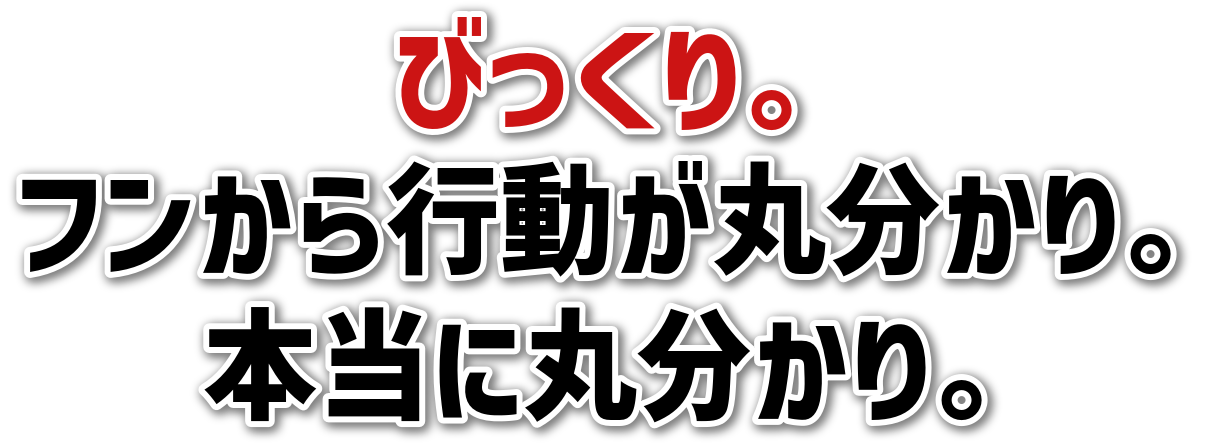
【疑問】
アライグマのフンを見つけたらすぐにできる対策は?
【結論】
フンの周囲に小麦粉を撒いて足跡を確認し、移動経路を特定できます。
ただし、雨の日は砂を代用して同様の効果が得られます。
アライグマのフンを見つけたらすぐにできる対策は?
【結論】
フンの周囲に小麦粉を撒いて足跡を確認し、移動経路を特定できます。
ただし、雨の日は砂を代用して同様の効果が得られます。
【この記事に書かれてあること】
庭や畑でフンを見つけたけれど、これって本当にアライグマのもの?- アライグマの新鮮なフンは要警戒レベルの重要なサイン
- 縄張り主張のためのフンは10メートル間隔で見つかる
- 食べ物の残渣からアライグマの活動範囲が分かる
- 5つの実践的な対策で効果的な被害予防が可能
- フンの記録と観察は最低2週間の継続が必要
そんな疑問を抱えている方も多いはず。
実は、アライグマのフンには見逃せない重要な情報が隠されているんです。
フンの新鮮さや場所から、活動範囲やねぐらの位置まで分かってしまうため、対策の決め手となります。
「このフン、昨日はなかったはずなのに…」と気になったら要注意。
今回は、フンから読み取れる手がかりと、すぐに実践できる対策方法をご紹介します。
【もくじ】
アライグマのフンの基本的な特徴

- 新鮮なフンは黒くてツヤのある「円筒形」が特徴!
- フンから分かる「食べ物」と活動場所の関係!
- 素手でフンを触るのは「寄生虫感染」の危険!
新鮮なフンは黒くてツヤのある「円筒形」が特徴!
新鮮なアライグマのフンは、長さ3〜4センチの円筒形で、表面がつるつるとしたツヤのある黒色が特徴です。まるで小さな筒状のチョコレートのような形をしていますが、決して触ってはいけません。
新鮮なフンほど黒みが強く、水分を含んでいるためツヤツヤと光っているんです。
大きさは犬のフンの半分程度で、表面にはゴツゴツとした凸凹があります。
「これって本当にアライグマのフン?」と迷ったときは、次の3つのポイントをチェックしましょう。
- 円筒形で両端が丸みを帯びている
- 表面にブツブツとした突起がある
- 独特の酸っぱい臭いがする
新鮮なフンを見つけたら要注意です。
「昨晩、アライグマが活動していた」という証拠になっちゃいます。
フンから分かる「食べ物」と活動場所の関係!
アライグマのフンを割ってみると、食べた物の残りかすでその子の行動範囲が分かってしまうんです。例えば、カキの種がたくさん入っているフンを見つけたら「ご近所のカキの木が狙われている!」というわけです。
フンの中身は季節によってもガラリと変わります。
- 春:タケノコの繊維や小動物の骨片が多い
- 夏:ブドウやイチジクなどの果物の種が目立つ
- 秋:ドングリやクリなどの殻が増える
- 冬:小魚の骨や虫の殻が多く見られる
フンの中身を見れば、どの季節にどんな場所で食事をしているのかが丸分かりです。
被害が出る前に、食べ物のある場所を重点的に警戒することができます。
素手でフンを触るのは「寄生虫感染」の危険!
新鮮そうなフンを見つけても、絶対に素手では触らないようにしましょう。アライグマのフンには危険な寄生虫が潜んでいるんです。
「ちょっとくらいなら…」という軽い気持ちが大変なことに。
アライグマのフンには、次のような危険が潜んでいます。
- 回虫などの寄生虫が含まれている
- 細菌による感染症の危険がある
- 乾燥したフンでも寄生虫は生存している
まるで危険物を扱うような気持ちで慎重に。
観察が終わったら、手袋はビニール袋に入れてしっかり密閉し、すぐに捨てましょう。
「念のため」と思って二重に手袋をするくらいの用心深さがちょうどいいくらいです。
アライグマのフンの場所選び

- 高い場所に置かれた「縄張り主張」のフン!
- フンは必ず「10メートル間隔」で見つかる!
- フンの位置から「ねぐらまでの距離」が判明!
高い場所に置かれた「縄張り主張」のフン!
アライグマは自分の縄張りを主張するため、必ず目立つ高い場所にフンを置きます。木の根元や大きな石の上、倉庫の角など、わざと目につく場所を選んでいるんです。
フンの周辺をよく観察すると、縄張りの範囲が見えてきます。
- 木の上や石の上など、地面より10センチ以上高い場所を好む
- 人が通りやすい場所の近くにわざと目立つように置く
- 倉庫や物置の角など、建物の端に集中して見つかる
- フンの置き場所は毎日同じ場所を使う習性がある
フンは必ず「10メートル間隔」で見つかる!
アライグマは決まった間隔でフンを置く習性があります。よく通る道沿いに10メートルごとにポツポツと見つかるのが特徴です。
この間隔は縄張りの主張と関係があり、複数のフンが見つかれば、その一帯がアライグマのなわばりだと分かります。
- 10メートル前後の等間隔でフンを置く
- 道沿いにまっすぐ一列に並んでいる
- フンの数が3個以上見つかれば確実な縄張り
- 繁殖期は間隔が5メートルに縮まることもある
フンの位置から「ねぐらまでの距離」が判明!
フンの位置には重要な意味があります。ねぐらから50メートル以内の範囲に複数のフンが見つかれば、その近くに巣があるというわけです。
特に朝一番に見つかる新鮮なフンは、ねぐらの場所を特定する重要な手がかりになります。
- ねぐらから半径50メートル以内にフンを置く
- 新鮮なフンほどねぐらに近い場所に置かれる
- フンの数が集中している場所がねぐらの目印
- 巣穴の周辺は特に数が多くなっています
足跡とフンの違いから見る活動範囲

- 足跡vs新鮮なフン「どちらが信頼できる?」
- 爪跡とフンで「活動エリア」の広さに違い!
- 食べ跡とフンで「被害場所」を特定!
足跡vs新鮮なフン「どちらが信頼できる?」
アライグマの痕跡を探すなら、足跡よりも新鮮なフンの方が信頼できる手がかりです。足跡はすぐに消えてしまいますが、フンは長く残るからです。
「足跡を見つけた!でも雨が降ったらすぐに消えちゃった…」なんて経験はありませんか?
実はフンの方が、はるかに確実な痕跡なんです。
足跡は雨で流されたり、風で砂が被さったりして、すぐにふわっと消えてしまいます。
でも新鮮なフンは3日から1週間はそのまま残るため、アライグマの行動を追跡するのに最適なんです。
フンには次のような特徴があります。
- 黒くてつやつやした表面が特徴的
- 円筒形で表面がでこぼこしている
- 独特の酸っぱい臭いがする
- 乾燥すると表面がぼろぼろになる
「まだ近くにいるかも!」と警戒しながら、周囲をしっかり確認してみましょう。
アライグマは日没後2時間以内に同じ場所に戻ってくる習性があるため、新鮮なフンの発見は活動時間帯を知る重要な手がかりとなります。
爪跡とフンで「活動エリア」の広さに違い!
アライグマの爪跡とフンを比べると、フンの方が広い範囲で見つかります。これは、フンが縄張りの目印として使われているためです。
爪跡はごりごりと木の幹に残されますが、その数は意外と少なめ。
一方でフンは、一日に3〜4個も残されるんです。
しかも、活動範囲全体に広がって見つかります。
「なぜフンの方が多いの?」それは、アライグマが自分の縄張りを主張するためなんです。
フンには、次のような特徴があります。
- 10〜15メートルおきに見つかる
- 活動範囲の端から端まで点々と並ぶ
- 目立つ場所に置かれやすい
- 毎日新しいものが追加される
爪跡だけでは分からない活動エリアの全体像が見えてくるというわけです。
食べ跡とフンで「被害場所」を特定!
アライグマは食べた場所の近くに必ずフンを残します。この習性を利用すれば、被害場所の特定が簡単になります。
「庭の果物が荒らされている…」そんな時は、まずフンを探してみましょう。
アライグマは食事の後、10メートル以内の場所にフンを残す習性があるんです。
フンの中身を見れば、何を食べたのかもはっきり分かります。
- 果物の種がたくさん含まれている
- 昆虫の殻が混ざっている
- 小動物の骨片が見つかる
- 季節の食材が反映される
このように、フンと食べ跡をセットで確認することで、どこで何を食べているのか、ばっちり特定できます。
被害対策も的確に行えるようになりますよ。
アライグマのフンを見つけたら実践する5つの対策

- フンの位置を「見取り図」に記録する!
- フンの周囲に「小麦粉」を撒いて足跡確認!
- 新聞紙で「夜間の活動時間」を特定!
- 砂をまいて「移動経路」を可視化!
- 落ち葉で「フンの新鮮さ」を判別!
フンの位置を「見取り図」に記録する!
フンを見つけたら、まずは庭の見取り図に位置を書き込んでいきましょう。記録を続けることで、アライグマの行動パターンが見えてきます。
「あれ?ここにもフンが…」と見つけるたびに位置を記録していくと、アライグマの活動範囲がはっきりと見えてきます。
見取り図には以下の情報を書き込むのがおすすめです。
- フンを見つけた日付と時間
- フンの大きさと数
- フンの新鮮さ(つやつやか乾燥か)
- 周辺の目印となる物(木や石など)
でも、これには重要な理由があるんです。
アライグマは決まった場所に繰り返しフンを置く習性があります。
そのため、見取り図を作ることで、次のような大切な情報が分かってくるんです。
- よく通る道筋や休憩場所
- 餌場として狙われている場所
- ねぐらに向かう方向
- 縄張りの境界線
「こんな細かい作業、面倒くさいなぁ」と感じるかもしれません。
でも、きちんと記録することで、被害を防ぐための効果的な対策が打てるようになるというわけです。
フンの周囲に「小麦粉」を撒いて足跡確認!
アライグマの行動範囲を知るなら、フンの周りに小麦粉を撒くのが効果的です。足跡がくっきり残るため、移動方向が一目で分かります。
小麦粉は直径1メートルの円を描くように薄く撒きます。
「どのくらいの量を撒けばいいの?」という疑問には、次の3つのポイントで答えられます。
- 地面が白く色づく程度の薄さ
- 足跡がはっきり付く程度の厚さ
- 風で飛ばされない程度の量
足跡の向きから、アライグマがどの方向から来て、どの方向へ去ったのかが分かります。
「こんな簡単な方法でいいの?」と思うかもしれませんが、意外と正確な情報が得られるんです。
また、小麦粉の上に残された足跡には、アライグマの数や大きさまで記録されています。
たとえば、大小の足跡が混在している場合は親子連れの可能性が高く、繁殖期に入っているサインかもしれません。
この方法は雨の日には使えませんが、晴れた日なら手軽に試せる方法です。
小麦粉は台所にあるものを少量使うだけでいいので、費用もかからないのがうれしいところ。
新聞紙で「夜間の活動時間」を特定!
アライグマのフンの上に新聞紙を被せておくと、夜間の活動時間が分かります。その時間を知れば、効果的な対策を打てるようになります。
具体的な方法は、とても簡単です。
夕方、フンの上に新聞紙を軽く被せておきましょう。
「これだけでいいの?」と思うかもしれませんが、この単純な方法がとても役立つんです。
- 新聞紙がそのままなら、まだ活動していない
- 新聞紙がめくれていたら、その場所を通過した
- 新聞紙が破れていたら、その場所で立ち止まった
アライグマは決まった時間に同じ場所を通る習性があるので、数日間続けることで活動時間が見えてきます。
ただし、この方法で気をつけたいポイントがあります。
- 新聞紙は風で飛ばされない重さに
- 雨の日は水に濡れない素材に変更
- 新聞紙は毎日新しいものに取り替え
- 夜間の天気も記録しておく
例えば、夜の8時頃に活動していることが分かれば、日没直後から見回りを始めるといった具合です。
砂をまいて「移動経路」を可視化!
フンの周りに砂をまくと、アライグマの足跡がはっきりと残ります。これで移動経路を簡単に把握できるんです。
砂まきのコツは、直径2メートルの円を描くように薄く撒くことです。
厚すぎても薄すぎてもいけません。
- 地面が隠れる程度の薄さ
- 足跡が付きやすい湿り気
- 雨で流されない程度の量
- 表面を平らに整える
「へぇ、こんな方向から来てたんだ」と驚くことも。
足跡の特徴から分かることは実に多いんです。
- 移動時の歩く速さ
- 立ち止まった場所
- 餌を探した跡
- 仲間の数
この情報を基に、柵や忌避剤を効果的に設置していけるというわけです。
落ち葉で「フンの新鮮さ」を判別!
フンの周りに落ち葉を敷き詰めることで、フンがいつ置かれたのかが分かります。これはとても正確な方法なんです。
実践方法は、次の手順で行います。
- フンの周り1メートルに落ち葉を敷く
- 落ち葉は重ならないよう薄く広げる
- 風で飛ばされそうな葉は除く
- 雨に濡れた葉は使わない
落ち葉の上に置かれたフンは新しく、落ち葉の下にあるフンは古いものと判断できるんです。
この方法で分かることは他にもあります。
- 活動頻度の変化
- 縄張りの拡大傾向
- フンの数の増減
- 季節による変化
簡単にできて、しかも正確な情報が得られる、とても便利な方法というわけです。
アライグマのフンを発見時の注意点

- 子育て期は「フンの数」が3倍に増加!
- フンの記録は「最低2週間」継続が必須!
- 近隣住民と「情報共有」で被害を防止!
子育て期は「フンの数」が3倍に増加!
春から夏にかけての子育て期には、フンの数が驚くほど増えます。「あれ?昨日はこんなにフンがなかったのに…」と感じたら要注意。
母親アライグマは子育ての拠点を確保するため、周辺により多くのフンを残すようになるんです。
- 普段は1日3〜4個のフンが、子育て期には1日10個以上に
- フンの大きさも通常より1.5倍ほど大きくなる
- フンの位置が高い場所に集中して見つかるように
- 特に巣に近い場所では、まとめて見つかることも
フンの記録は「最低2週間」継続が必須!
フンの位置や数の記録は、ぱらぱらと見つけた時だけメモするのではダメです。毎日決まった時間に確認して、きちんと記録を取る必要があります。
「めんどくさいなぁ」と思っても、最低2週間は継続することが大切。
- 朝のうちに前日のフンを確認して記録
- 新しいフンは黒くてつやつやしているのが特徴
- 見つけた場所に目印の棒を立てて比較
- 雨の日でも欠かさず確認を続けること
近隣住民と「情報共有」で被害を防止!
アライグマのフンを見つけたら、すぐに近所の方々に知らせましょう。「ご近所に話すのは気が引けるなぁ」と思うかもしれませんが、一軒だけの対策では効果が限られてしまいます。
アライグマは複数の家を行き来する習性があるからです。
- フンの発見場所と日時を地図に記録
- 朝の見回り時間を住民で統一
- フンの特徴や見分け方を共有
- 被害の兆候があった場所を教え合う