アライグマの感染症の種類は?【6種類の危険な病気あり】リスク度と予防法で対策を
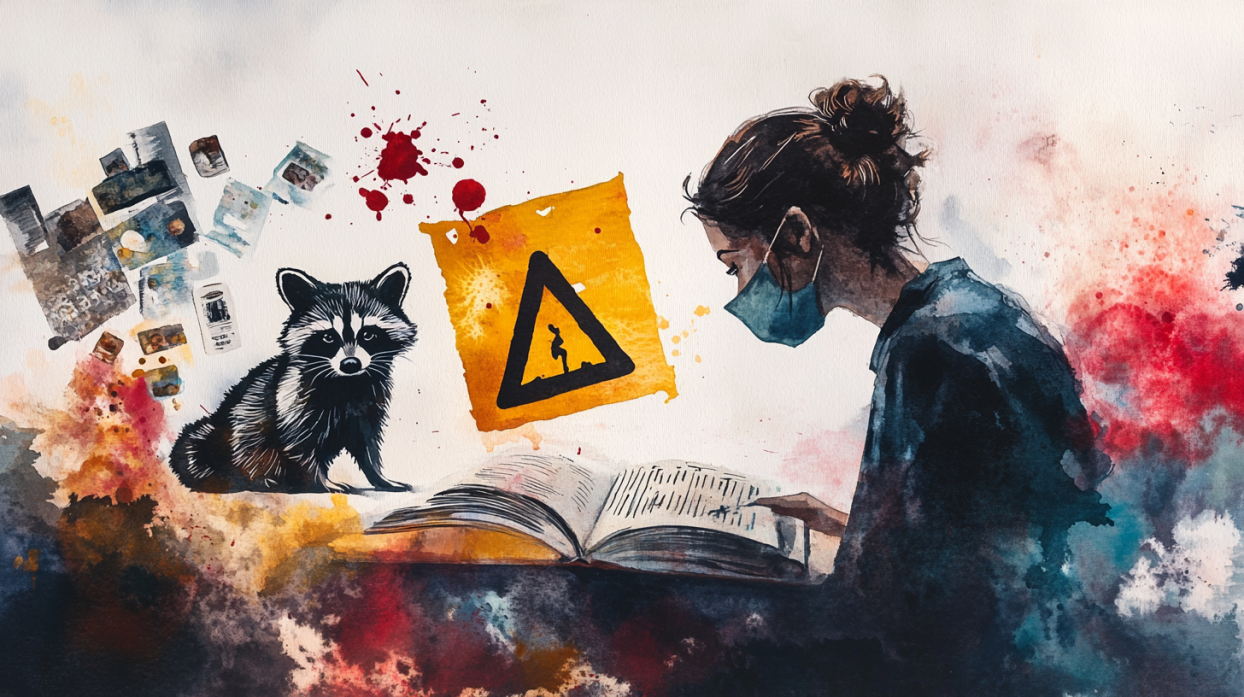
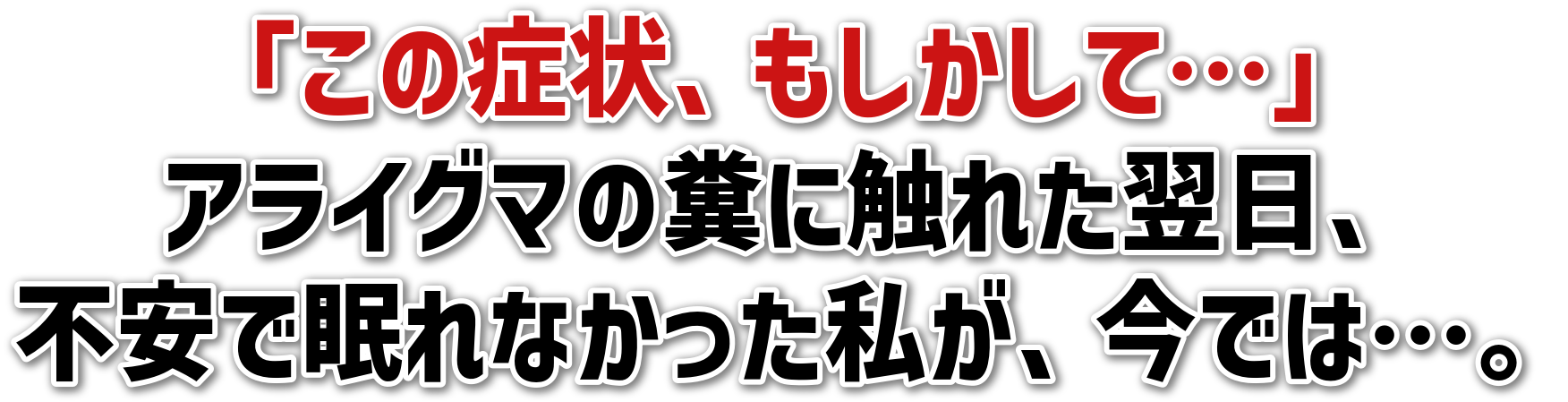
【疑問】
アライグマの感染症はどれくらい危険なの?
【結論】
アライグマ回虫症は脳に重篤な障害を引き起こし、発症すると死亡率が高く完治が困難な状態になります。
ただし、適切な予防措置を講じることで感染リスクを大幅に下げることができます。
アライグマの感染症はどれくらい危険なの?
【結論】
アライグマ回虫症は脳に重篤な障害を引き起こし、発症すると死亡率が高く完治が困難な状態になります。
ただし、適切な予防措置を講じることで感染リスクを大幅に下げることができます。
【この記事に書かれてあること】
アライグマが媒介する感染症は、危険度が高く命にも関わる病気が含まれています。- アライグマが媒介する6種類の危険な感染症の詳細と発症リスク
- 最も危険なアライグマ回虫症の症状と予防法
- 接触状況による感染リスクの比較データと対策方法
- 感染症から身を守る5つの具体的な予防策
- 子どもや高齢者に向けた感染症対策の重要ポイント
「まさか自分が感染するなんて…」と思っているあなた、実は誰もが感染リスクにさらされているかもしれません。
感染力が強く、治療が難しい6種類の病気について、しっかりと理解しておくことが大切です。
「感染症のことは知っていたけど、どう予防すればいいの?」そんな不安を解消するため、接触状況による感染リスクの違いや、効果的な予防法をくわしく解説します。
【もくじ】
アライグマの感染症は6種類!種類と特徴を把握

- 6種類の感染症とそれぞれの発症リスク!一覧表で解説
- アライグマ回虫症が最も危険!致死率の高さに警戒
- 素手での糞処理はNG!感染リスクが極めて高い理由
6種類の感染症とそれぞれの発症リスク!一覧表で解説
アライグマから感染する可能性がある病気は主に6種類あり、それぞれの危険度が異なります。まずは代表的な感染症を見ていきましょう。
「どんな病気があるのかしら?」と不安になりますよね。
アライグマが媒介する主な感染症には、次の6つがあります。
- アライグマ回虫症:最も危険度が高く、脳に重篤な障害を引き起こします
- 狂犬病:発症すると助かる確率が低く、2週間以内に症状が出現します
- レプトスピラ症:高熱と筋肉痛が特徴で、2〜14日で発症します
- サルモネラ症:下痢や腹痛、発熱などが現れ、1〜3日で発症します
- エーリキア症:発熱やだるさが続き、1〜2週間で症状が出現します
- 重症熱性血小板減少症候群:高熱と血小板減少が特徴で、4〜15日で発症します
「大丈夫かな?」と思っても油断は禁物。
アライグマとの接触後は体調の変化に気を配る必要があります。
アライグマ回虫症が最も危険!致死率の高さに警戒
アライグマが媒介する感染症の中で、最も警戒が必要なのがアライグマ回虫症です。この病気は、まるで密かに忍び寄る影のように危険です。
アライグマの糞に含まれる回虫の卵が体内に入ると、じわじわと症状が進行していきます。
「たかが回虫」と侮ってはいけません。
- 脳に寄生して重い障害を引き起こします
- 発症すると完治が極めて難しくなります
- 子どもが感染すると特に重症化しやすいです
- 治療費用が100万円を超えることもあります
「もう大丈夫かな」と思った頃に突然症状が出ることもあるんです。
頭痛やめまい、視力障害などが現れたら要注意。
まるで体の中で回虫がうろうろしているかのような不快感に襲われることも。
早期発見が治療の決め手になります、というわけです。
素手での糞処理はNG!感染リスクが極めて高い理由
アライグマの糞を見つけたとき、絶対に素手で触れてはいけません。なぜなら、糞には目に見えない危険がいっぱい。
まるで細菌の巣くつのような状態なんです。
「ちょっとくらいなら…」という気持ちが大きな失敗のもと。
- 寄生虫の卵が大量に含まれています
- 病原体の数が尿よりも5倍以上多いです
- 乾燥した糞からも感染する可能性があります
- 手についた病原体が口に入ると重症化しやすいです
- 皮膚の傷から侵入することもあります
必ずゴム手袋を着用し、ちょっとでも肌に触れないよう注意深く行います。
処理後は手袋もビニール袋に入れて密閉し、しっかりと手を洗いましょう。
「面倒くさい」と思っても、これが命を守る大切な作業なんです。
感染リスクを下げる4つの予防法

- 家屋の開口部を完全に封鎖!侵入経路の遮断が基本
- 手袋と消毒液の正しい使い方!予防の三原則
- 繁殖期の春から夏は要注意!活動が活発に
家屋の開口部を完全に封鎖!侵入経路の遮断が基本
アライグマから感染症を防ぐ第一歩は、家屋への侵入を防ぐことです。すき間を見つけて家の中に入り込もうとするアライグマの習性を理解し、きっちりと対策を立てましょう。
- 換気口や通気口は金網で覆い、すき間なくしっかりと固定
- 屋根裏への出入り口は板材で完全にふさぎ、釘でがっちり固定
- 雨どいの周辺はトゲトゲした板を取り付けて、よじ登りを防止
- 物置や納屋の扉は隙間テープを貼って、すき間をぴったりと密閉
手袋と消毒液の正しい使い方!予防の三原則
アライグマの痕跡を見つけたときは、適切な防護具と消毒で身を守りましょう。うっかり素手で触れてしまうと、あっという間に感染してしまうんです。
- 二重手袋の着用:内側にゴム手袋、外側に革手袋をつけてしっかりガード
- 消毒液の選択:アルコール濃度70%以上のものを使い、まんべんなく噴霧
- 手洗いの徹底:石けんで30秒以上もみ洗いし、流水でじっくりすすぎ
- 使用後の処理:手袋は外側が内側に触れないよう丁寧に脱いで密封処分
繁殖期の春から夏は要注意!活動が活発に
春から夏にかけては、アライグマの活動が最も活発になる時期。子育ての準備で家屋に侵入しようとする個体が急増し、接触の危険性がぐんと高まります。
- 3月から5月は巣作りのため、物置や屋根裏をうろうろと物色
- 6月から8月は子育て中で、餌を求めて庭や物置を頻繁に往来
- 夜明け前と日没後は特に活発で、建物の周りをそわそわと徘徊
- 雨の日の後は餌を探しに出てくることが多く、ごみ置き場に注意
接触時の危険度を比較

- 直接接触vs間接接触!リスクは10倍の差
- 成獣vs子アライグマ!発症率は3倍以上の開き
- 糞と尿でリスク度を比較!病原体量に5倍の差
直接接触vs間接接触!リスクは10倍の差
アライグマとの接触方法によって、感染症にかかるリスクは大きく変わってきます。噛まれたり引っかかれたりする直接接触は、糞尿による間接接触と比べて感染リスクが10倍以上も高くなります。
「え、そんなに差があるの?」と驚かれるかもしれません。
実は、直接接触の場合は病原体が傷口から直接体内に入り込むため、感染しやすいんです。
具体的な危険度の違いを見てみましょう。
- 噛まれる:感染リスク極めて高い(病原体が唾液から直接侵入)
- 引っかかれる:感染リスク非常に高い(爪に付着した病原体が傷口から侵入)
- 糞との接触:感染リスク中程度(手洗いで予防可能)
- 尿との接触:感染リスク比較的低い(すぐに洗い流せば安全)
アライグマの歯は鋭くとがっていて、「ガブッ」と深い傷になりやすいため、病原体が血管に直接入り込んでしまうことも。
このため、噛まれた場合は必ず医療機関を受診する必要があります。
成獣vs子アライグマ!発症率は3倍以上の開き
アライグマの年齢によっても、感染症のリスクは大きく異なります。成獣は子アライグマと比べて感染症の発症率が3倍以上も高くなることが分かっています。
これには明確な理由があるんです。
成獣は体内の病原体の量が多く、さらに攻撃性も強いため、接触した際の危険度がぐっと高まります。
年齢による違いをより詳しく見てみましょう。
- 成獣:体重8キロ以上で力も強く、傷も深くなりやすい
- 若獣:体重4〜7キロで警戒心が強く、予測不能な行動をとる
- 子アライグマ:体重3キロ以下で比較的おとなしいが油断は禁物
たとえ子アライグマでも、「キャッ」という鳴き声で親を呼び寄せる可能性があるからです。
糞と尿でリスク度を比較!病原体量に5倍の差
アライグマの糞と尿では、含まれる病原体の量に大きな違いがあります。糞には尿の5倍以上もの病原体が含まれているため、取り扱いには特に注意が必要です。
糞には寄生虫の卵や多くの細菌が含まれており、「うっかり触ってしまった」というだけで感染の可能性があるんです。
一方、尿は病原体の量が比較的少なく、すぐに水で洗い流せば感染リスクを抑えられます。
それぞれの特徴を詳しく見てみましょう。
- 糞:寄生虫の卵が大量に含まれ、乾燥しても感染力が持続
- 尿:病原体量は少なめだが、水たまりとなって残留する
- 糞尿が混ざった場所:両方の危険性があり、最も注意が必要
水分を含んでいる新鮮な糞は、乾燥した古い糞よりも病原体が活発で、感染リスクが高くなっているというわけ。
アライグマ感染症から身を守る5つの対策

- 柑橘系アロマオイルの活用!玄関マットに数滴が効果的
- 換気扇周りのメッシュ設置!侵入経路を物理的に遮断
- 庭木の1メートルまでの枝打ち!隠れ場所を排除
- ゴミ置き場への5キロ以上の重石設置!物理的な防衛
- 生ごみの熱湯処理!匂い対策で誘引防止
柑橘系アロマオイルの活用!玄関マットに数滴が効果的
アライグマは柑橘系の香りを嫌うため、玄関マットに数滴たらすだけで侵入を防げます。「匂いだけで本当に効果があるの?」と思われるかもしれません。
実は、アライグマの鼻は人間の20倍以上も敏感なんです。
特に柑橘系の香りは、まるで強力な壁のように感じるため、玄関近くには寄り付かなくなります。
具体的な使い方のポイントは3つあります。
- 玄関マットの四隅に、みかんやレモンの精油を2〜3滴ずつたらす
- 雨の日は効果が薄れるため、軒下に置いて雨よけを作る
- 週に2回程度の補充で、効果を維持できる
人間の鼻では、ほんのりと爽やかな香りを感じる程度です。
むしろ玄関周りが良い香りになって、一石二鳥なんです。
また、玄関マット以外にも、庭の境界線や物置の周りにも活用できます。
ただし、香りが強すぎると逆効果。
さらさらっと数滴たらす程度が、ちょうど良い塩梅です。
換気扇周りのメッシュ設置!侵入経路を物理的に遮断
換気扇の周りに目の細かいワイヤーメッシュを設置すれば、アライグマの侵入を確実に防げます。侵入防止のコツは、メッシュの選び方と取り付け方にあります。
メッシュの網目は1センチ未満のものを選びましょう。
「そんなに細かくなくても大丈夫では?」と思われるかもしれません。
でも、アライグマの手先はとても器用。
隙間があれば、ぐいぐいと広げて侵入してしまうんです。
効果的な設置方法は以下の3つです。
- 換気扇の外周から10センチ以上はみ出すサイズのメッシュを用意
- ステンレス製のネジで8か所以上をしっかり固定
- メッシュの端を内側に折り込んで、鋭利な部分をなくす
「がたがた」「ずれてる」「隙間ができてる」といった異常がないかチェック。
早めの補修で、すきま知らずの防御を維持しましょう。
庭木の1メートルまでの枝打ち!隠れ場所を排除
庭木の下枝を地上1メートルまで刈り込むことで、アライグマの隠れ場所をなくし、接近を防げます。木の下枝は、アライグマにとって絶好の休憩所。
「まさか、うちの庭木が隠れ家に?」と思われるかもしれません。
しかし、茂みの中なら人目を気にせずのんびりできるため、アライグマは木陰を大好きなんです。
効果的な枝打ちの方法は、以下の3つがポイントです。
- 地上から高さ1メートルまでの枝を根元からすっきり刈る
- 幹と幹の間も見通しよく整える
- 剪定した枝は放置せず、その日のうちに片付ける
2メートル以上の間隔があれば、アライグマも警戒して近寄りにくくなります。
「でも、見た目が寂しくなりそう」という心配も。
そんな時は背の低い花を植えて彩りを添えましょう。
ただし、剪定は春先や秋口がおすすめ。
真夏の剪定は木にとってかなりの負担になってしまいます。
木の健康と防犯、両方に配慮した timing で作業を進めましょう。
ゴミ置き場への5キロ以上の重石設置!物理的な防衛
重さ5キロ以上の重石をゴミ箱の上に置けば、アライグマの侵入を物理的に防げます。「そんな重たい石、必要なの?」と思われるかもしれません。
でも、アライグマの腕力は侮れません。
両手で持ち上げる力は3キロまでなので、5キロ以上あれば、びくともしないんです。
効果的な重石の選び方と使い方は以下の通りです。
- 平らな面があるレンガや石材を選ぶ
- ゴミ箱の中央部分に安定よく置く
- 複数の軽い石より、1つの重い石が効果的
ただし、留め具が緩いタイプは、器用な手先で簡単に外されてしまうことも。
がっちりした作りの物を選びましょう。
また、ゴミ箱の周りは1メートル以上の空間を確保することも大切です。
物が散らばっていると、それを足場にされて重石を押しのけられる可能性も。
整理整頓が、防衛の基本なんです。
生ごみの熱湯処理!匂い対策で誘引防止
生ごみを捨てる前に熱湯をかけることで、アライグマを引き寄せる匂いを大幅に抑制できます。「えっ、そんな手間かけるの?」と思われるかもしれません。
でも、アライグマの嗅覚は人間の20倍以上。
数日前の生ごみの匂いでも、はるか遠くから感知できてしまうんです。
効果的な処理方法は以下の3つです。
- 沸騰直後の熱湯をたっぷりとかける
- 水気をしっかり切ってから密閉袋に入れる
- 週2回以上の定期的な収集日に出す
これらは匂いが強烈なため、アライグマを引き寄せやすいんです。
熱湯をかけた後、みかんの皮を一緒に入れると、より効果的。
柑橘系の香りで、匂い消しが完璧になります。
また、生ごみは必ず収集日の朝に出すようにしましょう。
前日の夜に出すと、夜行性のアライグマの活動時間と重なってしまいます。
朝一番の新鮮なうちに回収してもらうのが、一番の対策なんです。
感染症予防の重要ポイント

- 子どもと高齢者は感染に注意!免疫力の差が影響
- 感染症の症状は3日以上続くと要注意!即受診を
- 周辺住民への注意喚起!感染リスクの共有が大切
子どもと高齢者は感染に注意!免疫力の差が影響
子どもと高齢者は免疫力が低いため、アライグマの感染症に特に注意が必要です。「うちの子は外遊びが大好きだから心配…」という声も多いですよね。
- 子どもは手洗いの習慣が十分でないため、外遊び後は必ず石けんで丁寧に手を洗わせましょう
- 高齢者は免疫力が低下していることが多く、感染すると重症化しやすい傾向があります
- 特に気を付けたい場所は砂場や公園の植え込み周辺。
アライグマの糞が残っている可能性が高いんです
感染症の症状は3日以上続くと要注意!即受診を
アライグマの感染症は早期発見が重要です。発熱やだるさが3日以上続く場合は要注意。
すぐに病院を受診しましょう。
- 発熱が3日以上続く場合は要注意。
ぐったりした感じが取れないときは特に危険信号です - 目のかすみや頭痛が出たら、アライグマ回虫症の可能性も考えられます
- めまいや筋肉の痛みが続く場合は、レプトスピラ症の疑いも。
すぐに受診しましょう
早めの受診がとても大切なんです。
周辺住民への注意喚起!感染リスクの共有が大切
アライグマの感染症対策は、地域全体で取り組むことが重要です。「うちの庭で見かけた」という情報は、すぐに周りに伝えましょう。
- アライグマの糞を見つけたら、近所の人にも知らせることが大切。
特に小さな子どもがいる家庭には必ず伝えましょう - 地域の掲示板や回覧板を活用して、出没情報を共有することがおすすめ
- みんなで声を掛け合い、庭や公園での不審な形跡にも注意を払いましょう
感染症予防は地域の大切な課題なのです。