アライグマが犬を襲う危険性は?【体格差2倍以内なら要注意】散歩時間の変更と5つの対策で安全確保!

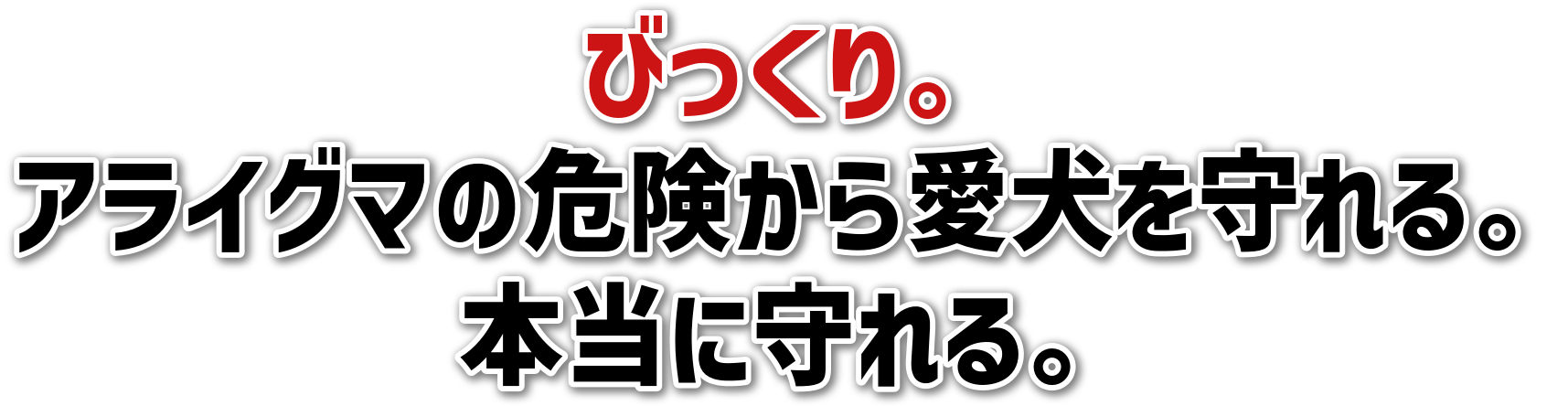
【疑問】
アライグマから愛犬を守るための最も重要なポイントは?
【結論】
散歩時間を日没後2時間を避けて設定することです。
ただし、雨天時は日中でも活動が活発になるため、天候に応じた時間帯の調整も必要です。
アライグマから愛犬を守るための最も重要なポイントは?
【結論】
散歩時間を日没後2時間を避けて設定することです。
ただし、雨天時は日中でも活動が活発になるため、天候に応じた時間帯の調整も必要です。
【この記事に書かれてあること】
愛犬との楽しい散歩中に、突如としてアライグマと遭遇してしまったら…。- アライグマは体格差2倍以内の犬なら攻撃する可能性が高い
- 握力20キロと2センチの鋭い犬歯を持つ
- 日没後2時間が最も危険な時間帯
- 春秋の繁殖期と夏の子育て期は特に警戒が必要
- 5つの実践的な対策で愛犬を守れる
「まさか襲われることなんてない」と思っていませんか?
実は、体格差が2倍以内なら愛犬が命の危険にさらされるほど危険なのです。
アライグマは前足の握力が20キロもあり、2センチの鋭い犬歯で一瞬のうちに相手を倒してしまいます。
「どうすれば愛犬を守れるの?」そんな飼い主さんの不安を解消するため、散歩時間の見直しと5つの具体的な対策方法をご紹介します。
【もくじ】
アライグマが犬を襲う危険性とは

- 体格差2倍以内の犬なら「圧倒的な攻撃力」で襲われる!
- アライグマの前足の握力「20キロ」と鋭い犬歯に要注意!
- 愛犬を抱き上げての逃走は「最悪の選択」でNG!
体格差2倍以内の犬なら「圧倒的な攻撃力」で襲われる!
アライグマは見た目以上の強さを持ち、体格差が2倍以内の犬なら襲われる危険性が極めて高いのです。「うちの犬は大丈夫かしら?」と思われる方も多いはず。
実は体重8キロのアライグマでも、その攻撃力は中型犬に匹敵します。
アライグマの狙い方は実に巧妙で、まるで格闘技の達人のよう。
- 瞬時に飛びかかり、首筋を狙って噛みつく
- 相手が倒れこんだ際に、むんずと腹部を攻撃
- 群れで現れた場合は、がばっと前後から挟み撃ち
一度襲いかかると、相手が動かなくなるまで攻撃をやめないという特徴があります。
「小型犬なら逃げ足が速いから安心」と思っても大間違い。
アライグマは意外と足が速く、すたすたと追いかけてくるんです。
じつは野生のアライグマは警戒心が強く、普段は人や犬を避けて通ります。
しかし餌場を荒らされたと感じたり、子育て中だったりすると豹変。
その時は体格差2倍以内の犬なら、容赦なく襲いかかってくるというわけです。
アライグマの前足の握力「20キロ」と鋭い犬歯に要注意!
アライグマの攻撃力の秘密は、体重8キロとは思えない握力20キロの前足と、ぎらりと光る2センチの鋭い犬歯にあります。想像してみてください。
お米の2キロ袋を10個分の力で、がっちりと相手をつかむ力です。
その上、まるでナイフのような鋭い歯で、ばりっと噛みつかれるのです。
「そんなバケモノみたいな力を持っているなんて…」と驚かれる方も多いはず。
アライグマの攻撃の特徴は以下の通りです:
- 前足でがっしりと相手を捕まえ、逃げられないように固定
- 鋭い犬歯でばっくりと急所を狙って一気に噛みつく
- 爪を立てながらごりごりと引っ掻き、皮膚を裂く
相手が反応する間もなく、にゃっと襲いかかり、一撃で大きなダメージを与えてしまいます。
まるで忍者のような素早さと、相撲取りのような握力、そして剣士のような切れ味を持ち合わせているのです。
このように複数の武器を組み合わせた攻撃は、犬にとって極めて危険。
油断は禁物です。
愛犬を抱き上げての逃走は「最悪の選択」でNG!
アライグマに遭遇した際、多くの飼い主が無意識にしてしまう「愛犬を抱き上げる」という行動。実はこれが最も危険な選択なのです。
なぜダメなのか、具体的に見てみましょう:
- 抱き上げた瞬間に愛犬が不安定な体勢になり、より攻撃を受けやすくなる
- 飼い主の胸の位置まで愛犬が持ち上げられ、アライグマの得意な高さになってしまう
- 愛犬が暴れると、飼い主もろとも転倒するリスクが高まる
しかし実は、愛犬の本能的な回避行動を妨げてしまうのです。
犬は自分の足で逃げる方が、はるかに安全に対処できます。
正しい対応は、リードを短く持って愛犬を自分の反対側に位置させること。
そしてゆっくりと後ずさりしながら、最低でも5メートルの距離を確保します。
この時、決して走って逃げないことが重要。
アライグマの狩猟本能を刺激してしまうからです。
アライグマからの防衛態勢を強化

- アライグマの出没時間は「日没後2時間」がピーク!
- アライグマの生息圏は「半径100メートル」以内に集中
- 庭のドッグフードは「即刻撤去」が鉄則!
アライグマの出没時間は「日没後2時間」がピーク!
アライグマの活動は日没直後から活発化し、特に日没後2時間が最も危険です。時期による活動時間の違いを把握しておくと、愛犬との散歩時間を適切に設定できます。
- 夏場は午後7時以降が最も危険な時間帯
- 冬場は午後4時台から活動を開始
- 雨の日は活動時間が前倒しになり、日没前から行動開始
この時期は日中の散歩がおすすめです。
冬場も日が短いため、午後3時までの散歩時間帯なら安全に過ごせるというわけ。
アライグマの生息圏は「半径100メートル」以内に集中
アライグマは自宅から100メートル以内の範囲に巣を作る習性があります。一度、巣を作ると長期間その場所を生活拠点にするため、愛犬との散歩コースの見直しが必要です。
- 物置や倉庫の周辺は巣になりやすい場所
- 木の上や屋根裏も好んで利用する場所
- 水場の近くは餌場として頻繁に出没
ガサガサと物を動かす音がしたら要注意。
木の上からも突然飛び降りてくることがあるので、頭上にも注意が必要なんです。
庭のドッグフードは「即刻撤去」が鉄則!
庭に置きっぱなしのドッグフードは、アライグマを引き寄せる強力な誘引物になります。においに敏感なアライグマは、ドッグフードの香りを遠くからかぎ分けます。
- 食べ残しは必ず室内に持ち込む
- 給餌は決まった時間に決まった場所で
- 食器は使用後すぐに洗浄
- 保管は密閉容器を使用
サッとキレイに洗って室内に片付けましょう。
においが残っていると、それだけでアライグマを呼び寄せてしまうというわけです。
時期による危険度の変化を把握

- 春と秋の「繁殖期」vs夏の「子育て期」の危険度!
- 雨の日の「昼間の活動」vs晴れの日の「夜間の活動」!
- 朝の「散歩時」vs夕方の「餌場探し」の遭遇率!
春と秋の「繁殖期」vs夏の「子育て期」の危険度!
アライグマの攻撃性は時期によって大きく変化し、特に春と秋の繁殖期、そして夏の子育て期には危険度が最大になります。「もうすぐ春だから、少しずつ暖かくなってきて散歩が楽しみ」なんて思っていませんか?
実は、この時期こそ要注意なんです。
春と秋の繁殖期のアライグマは、普段の2倍以上の攻撃性を見せます。
特に危険なのは、以下の3つの時期です。
- 3月〜4月の春の繁殖期:オスが縄張り争いで特に攻撃的に
- 6月〜8月の子育て期:子どもを守るメスが警戒心むき出しに
- 9月〜10月の秋の繁殖期:2回目の繁殖で再び攻撃性が増加
このような行動を見せた場合、その場からすぐに離れましょう。
子どもを守るための攻撃は特に執着心が強く、一度狙われると簡単には諦めない傾向があります。
雨の日の「昼間の活動」vs晴れの日の「夜間の活動」!
天候によってアライグマの活動時間は大きく変化し、特に雨の日は昼間でも活発に活動することを覚えておきましょう。「雨の日は動物も活動を控えるはず」という考えは、アライグマには当てはまりません。
むしろ、こんな特徴が見られます。
- 雨の日:日中でも餌を探して活発に行動
- 晴れの日:夜間の活動が9割以上を占める
- 曇りの日:夕方から活動を開始する傾向
「雨だから散歩は昼間にしよう」と考えがちですが、それが危険を招くことも。
じとじとした雨の日は、アライグマも普段の活動時間を変更して、昼間から動き回っているんです。
朝の「散歩時」vs夕方の「餌場探し」の遭遇率!
一日の中で時間帯による遭遇率には大きな差があり、特に夕方の散歩時間帯は要注意です。朝と夕方では、アライグマとの遭遇リスクが全く異なります。
以下の時間帯別の特徴を把握しておきましょう。
- 早朝(夜明け前):餌場から巣に戻る時間で遭遇率が高め
- 日中(9時〜15時):ほとんど活動せず遭遇率は極めて低い
- 夕方(日没前後):餌場探しの時間で最も遭遇率が高い
夕暮れ時は、アライグマが活動を始める準備をしている時間帯なんです。
特に、日没前後2時間は遭遇率が急上昇します。
この時間帯の散歩コースは、水辺や物置の周りを避けて設定しましょう。
愛犬を守る5つの実践的な対策

- 散歩コースに「柑橘系の粉末」を週2回撒いて寄せ付けない!
- リードに「直径2センチの鈴」を複数取り付けて警戒心を誘う!
- 「アンモニア水」を染み込ませた布を庭の要所に設置!
- 散歩用の「複数の小型ライト」で光による撃退態勢を整える!
- 「アルミホイルのボール」を持参して緊急時の対策を万全に!
散歩コースに「柑橘系の粉末」を週2回撒いて寄せ付けない!
みかんやゆずの皮を乾燥させて作る粉末には、アライグマを寄せ付けない強い効果があります。この天然の防衛策で、愛犬との散歩を安全に楽しみましょう。
柑橘系の皮には、アライグマが「くしゃっ」と顔をしかめる強い香り成分が含まれています。
「これなら自然な方法で対策できそう!」と思った方も多いはず。
効果を最大限に引き出すポイントは3つです。
- みかんやゆずの皮は、天日干しで水分を完全に飛ばす
- すり鉢でつぶして粗めの粉末にする
- 散歩コースの要所に3メートルおきに撒く
「とりあえず適当に」は禁物。
アライグマの通り道を把握して、計画的に撒いていきましょう。
雨が降った後は香りが薄れるため、必ず撒き直しが必要になっちゃいます。
柑橘系の粉末は犬にも安全なので、愛犬が少し嗅いでも心配ありません。
「ぷんぷん」と漂う爽やかな香りは、人間にとっても心地よいものです。
ただし、散布する量は1か所につき小さじ1杯程度に抑えましょう。
効果は約3日間持続します。
リードに「直径2センチの鈴」を複数取り付けて警戒心を誘う!
鈴の音は、アライグマの警戒心を刺激する効果的な対策です。愛犬のリードに適切なサイズの鈴を取り付けることで、アライグマとの予期せぬ遭遇を防ぎましょう。
アライグマは「ちりんちりん」という突然の音に敏感に反応します。
「でも、うちの子が怖がらないかな?」と心配な方も大丈夫。
愛犬は飼い主と一緒に散歩する時の音として認識してくれるんです。
効果的な鈴選びのポイントをまとめました。
- 直径2センチ以上の大きめの鈴を選ぶ
- リードの根元から10センチの位置に付ける
- 3個以上の鈴を取り付けて音を重ねる
また、鈴同士が「がちゃがちゃ」とぶつかり合わないよう、適度な間隔を開けて取り付けることが大切。
鈴の取り付け位置も重要です。
リードの持ち手に近すぎると、手の動きで不規則な音が出てしまい、愛犬が落ち着かなくなることも。
根元から10センチの位置なら、自然な動きに合わせた心地よい音色になるというわけです。
「アンモニア水」を染み込ませた布を庭の要所に設置!
アンモニア水を染み込ませた布は、アライグマの嫌う強い刺激臭で庭への接近を防ぎます。設置場所と交換時期を工夫すれば、高い効果を発揮する心強い味方になります。
アライグマは鋭い嗅覚を持つため、「むわっ」と鼻を突く強い臭いを嫌います。
「でも、臭いが強すぎて自分たちも困らない?」という心配は無用。
適切な設置方法なら、人間や愛犬への影響は最小限に抑えられるんです。
効果的な設置方法は以下の通りです。
- 布は手のひらサイズに切る
- アンモニア水は5倍に薄めて使用
- 地面から30センチの高さに設置
- 庭の境界線に2メートルおきに配置
アライグマの鼻の位置に合わせることで、より効果的に警戒心を引き出せます。
「ふんふん」と地面を嗅ぎながら近づいてくる習性を利用した、賢い対策というわけ。
布は週1回の交換が必要です。
雨に濡れると効果が弱まってしまうため、軒下や物置の周りなど、雨の当たりにくい場所を選んで設置しましょう。
散歩用の「複数の小型ライト」で光による撃退態勢を整える!
小型のライトを複数持参することで、不意の遭遇時にアライグマを混乱させることができます。光の使い方次第で、愛犬を守る強力な武器になります。
アライグマは突然の光に弱い生き物。
「でも、ただ照らすだけじゃ逃げてくれないのでは?」という不安も当然です。
実は、光の当て方には重要なコツがあるんです。
効果的な光の使い方をご紹介します。
- ライトは3個以上を持参する
- 異なる明るさのものを組み合わせる
- 照らす位置を不規則に変える
- 光をゆっくりと揺らすように照らす
まずは弱い光で様子を見て、徐々に強い光に切り替えていく。
急に強い光を当てると、かえってアライグマが興奮してしまう可能性があります。
ライトの選び方も大切です。
乾電池式の物を選び、予備の電池も必ず持参しましょう。
「きっと大丈夫」は禁物。
万が一の備えが、愛犬の命を守ることにつながるというわけです。
「アルミホイルのボール」を持参して緊急時の対策を万全に!
アルミホイルで作ったボールは、緊急時の撃退グッズとして優れた効果を発揮します。手軽に作れて携帯も簡単な上、アライグマへの威力は抜群です。
アルミホイルが地面で「がさがさ」と音を立てながら転がる様子は、アライグマの警戒心を強く刺激します。
「そんな簡単なもので効果があるの?」と思われるかもしれません。
でも、音と光の反射を組み合わせた効果は、意外なほど強力なんです。
効果的なボールの作り方をまとめました。
- アルミホイルは30センチ四方を使用
- 中心に小石を3個入れる
- 表面はでこぼこに仕上げる
- 握りこぶし大に丸める
小石が大きすぎると重くなりすぎ、小さすぎると音が弱くなってしまいます。
親指の先ほどの大きさの小石を3個入れると、ちょうど良い重さと音が出るというわけ。
使用時は、アライグマの1メートルほど手前に投げ入れます。
決してアライグマに向けて投げつけないよう注意しましょう。
あくまでも、音と光で威嚇するための道具として使用することが大切です。
愛犬との散歩時の重要な注意点

- 犬の体格が「アライグマの2倍以下」は複数人での散歩を!
- 散歩コースは「日中のうちに」安全確認を!
- 「水場や茂み」の周辺は迂回が基本!
犬の体格が「アライグマの2倍以下」は複数人での散歩を!
小型犬や中型犬との散歩は、必ず複数人で行くことが大切です。「一人で散歩させても大丈夫かな?」と思っている飼い主さんも多いはず。
でも、アライグマの攻撃は素早くて強力なんです。
体格差が2倍以内の場合、アライグマの方が圧倒的に有利になってしまいます。
- 飼い主一人では咄嗟の判断と対応が難しい
- 複数人ならすぐに助けを呼べる態勢が整う
- アライグマも複数の人間がいると警戒して近づきにくい
- 万が一の際も役割分担ができて冷静な対応が可能
愛犬を守るために、必ず誰かと一緒に散歩しましょう。
散歩コースは「日中のうちに」安全確認を!
散歩コースの下見は、必ず日中に行いましょう。アライグマの痕跡を見つけやすく、危険な場所も把握できます。
「急いでいるから適当に歩こう」はとても危険。
事前の確認で、愛犬の命を守れるんです。
- 物置や倉庫の裏側は特に要注意で、アライグマの好む場所
- 街灯の明るさや配置を確認して、暗がりを把握
- 緊急時の避難場所となる開けた場所をチェック
- 周辺住民に目撃情報を確認して、出没状況を把握
「水場や茂み」の周辺は迂回が基本!
アライグマは水場や茂みの近くに潜んでいることが多いため、そういった場所は大きく迂回しましょう。「ちょっとだけなら大丈夫」という考えは危険です。
愛犬の命を守るために、ぐるりと遠回りする心構えが必要なんです。
- 池や水たまりの周囲3メートルは避ける
- 背の高い茂みからは5メートル以上離れる
- 生垣の隙間には特に注意が必要
- 暗がりの植え込みは必ず避けて通る