アライグマはどこで寝る?【日中は木の上や物置が寝床】暗くて乾燥した高所に巣を作る習性に注目

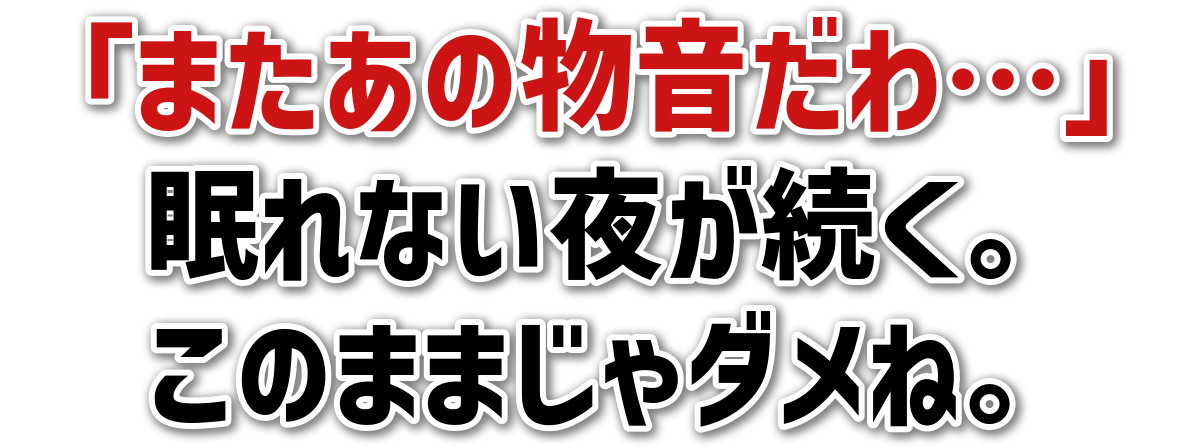
【疑問】
アライグマの寝床はすぐに見つけられるの?
【結論】
アライグマは木の上や物置など人目につきにくい高所に寝床を作るため発見が難しいです。
ただし、夜間の物音や新鮮なフンの有無をチェックすることで寝床の場所を特定できます。
アライグマの寝床はすぐに見つけられるの?
【結論】
アライグマは木の上や物置など人目につきにくい高所に寝床を作るため発見が難しいです。
ただし、夜間の物音や新鮮なフンの有無をチェックすることで寝床の場所を特定できます。
【この記事に書かれてあること】
深夜に怪しい物音がして目が覚めたことはありませんか?- アライグマは木の上や物置に寝床を作る習性があり日中8?12時間の休息を取る
- 乾燥した高所の暗い場所を好んで寝床にする
- 寝床は直径60センチメートルほどの広さを確保する
- 柑橘系の香りや風鈴の音で寝床を放棄させられる
- 近隣住民との情報共有で被害の分散化を防ぐ
実はそれ、アライグマの仕業かもしれません。
驚くべきことに、アライグマは私たちの身近な場所で昼寝をしているんです。
木の上や物置、時には屋根裏で「ぐうぐう」と眠っているアライグマたち。
「うちの周りにいるかも…」と心配になってきますよね。
でも大丈夫。
アライグマの寝床の特徴を知れば、効果的な対策が見えてきます。
今回は、アライグマの昼寝事情と、寝床対策の秘訣をお伝えします。
【もくじ】
アライグマの寝る場所と習性

- 日中は木の上や物置で「長時間の休息」を取る!
- 高さ1メートル以上の「乾燥した場所」が定番の寝床に
- 自分で見つけた寝床に「定住」はNG!
日中は木の上や物置で「長時間の休息」を取る!
夜行性のアライグマは、日中に8時間から12時間もの長い休息を取ります。「そろそろお昼寝の時間かな」とばかりに、朝方の活動を終えたアライグマは休息場所へ向かいます。
特に昼過ぎから夕方にかけては、ぐっすりと深い眠りに入る時間帯です。
休息中のアライグマは、まるでもふもふの毛玉のように丸まって眠ります。
尾を体に巻き付け、顔を前足で覆い隠すような独特の姿勢です。
でも「油断大敵!」と言わんばかりに、周囲の物音には敏感に反応します。
気温によって休息時間は大きく変化します。
暖かい季節は8時間ほどですが、寒い冬場になると「もう少しぬくぬくしていたいな」とばかりに15時間以上も休息を取ることも。
- 朝方の活動終了後に休息開始
- 昼過ぎから夕方が深い眠りの時間帯
- 寒い季節は休息時間が1.5倍以上に
「何か物音がしたぞ」「危険が近づいてないかな」と、常に周囲の変化に敏感に反応できる状態を保っているのです。
高さ1メートル以上の「乾燥した場所」が定番の寝床に
アライグマが選ぶ休息場所には、はっきりとした特徴があります。それは高さ1メートル以上の乾燥した暗い場所です。
「ここなら安心して眠れそう」と、木の上や物置、時には建物の屋根裏までもが寝床の候補地に。
なぜそんな場所を選ぶのでしょうか。
それは「下から忍び寄る危険」から身を守るためなのです。
寝床選びの基準は厳しく、以下の条件を全て満たす場所を探し回ります。
- 地上から1メートル以上の高さがある
- 雨や風を防げる屋根がある
- 日光が直接当たらない暗がり
- 乾燥していて湿気が少ない
- 人の往来が少ない静かな場所
「万が一の時はあっちに逃げよう」「こっちにも逃げ道があるぞ」と、抜け道をしっかり確認してから寝床を決めるんです。
自分で見つけた寝床に「定住」はNG!
アライグマの寝床を発見したら、そのままにしておいてはいけません。なぜなら寝床が子育ての場所になってしまうからです。
「この場所、気に入った!」とアライグマが判断すると、春には4匹から5匹もの子育て場所として定着してしまいます。
すると「がさごそ」「ばたばた」という物音が昼夜問わず聞こえるように。
寝床が見つかったら、次のような対策が有効です。
- 柑橘系の香りの設置
- 風鈴による不規則な音の演出
- 扇風機での気流の変化
「私の寝床を荒らすな!」と、普段の穏やかな様子から一転、攻撃的な性格を見せることも。
対策を講じる時は、必ず50メートル以上離れた場所から様子を見ながら進めていきましょう。
寝床を作る場所の特徴

- 枯れ草や布切れで直径60センチの巣材を確保
- 暗くて静かな場所に「複数の逃げ道」を確保
- 屋根裏や物置に「体を伸ばせる広さ」を探す
枯れ草や布切れで直径60センチの巣材を確保
アライグマの巣作りには必ず巣材が使われます。身の回りにある様々な物を器用に集めて、快適な寝床を作るんです。
巣材には、枯れ草や布切れ、新聞紙、ビニールなどを使います。
巣は円形で、直径は60センチほどの大きさです。
寝床を作る時は、次のような特徴が見られます。
- 入り口は小さめに作り、内部は広くふかふかに仕上げる
- 巣材を何重にも重ねて、体温を逃がさない工夫をする
- 雨風を防ぐため、上部には厚めの材料を敷き詰める
- 周囲の巣材に体をこすりつけて、においをつける
暗くて静かな場所に「複数の逃げ道」を確保
寝床選びで最も重視するのが安全性です。アライグマは人目につきにくい暗がりで、静かな場所を好みます。
寝床には必ず複数の逃げ道があるのが特徴。
万が一の時にさっと逃げられる環境を整えているのです。
- 物陰に隠れた場所を選び、人の動きを観察できる位置取り
- 木の枝や壁伝いに素早く逃げられる経路を2つ以上確保
- 天敵から身を守れる高さのある場所を選択
- 周囲の物を利用して、身を隠せる環境作り
屋根裏や物置に「体を伸ばせる広さ」を探す
アライグマは休息時に体を自由に伸ばせる広さを必要とします。窮屈な場所は避け、屋根裏や物置の中でもゆったりとした空間を選んで寝床にします。
寝床の条件は以下の通りです。
- 体長の2倍以上の広さがあり、くるりと体を丸められる空間
- 雨風が直接当たらず、乾燥している場所
- 床が平らで、安定した場所
- 温度変化が少なく、年中過ごしやすい環境
他の動物との寝床の違い

- ハクビシンの寝床vs「広々アライグマの寝床」に注目
- タヌキの地上巣vs「高所のアライグマ巣」を確認
- 猫の定住型vs「アライグマの移動型」を理解
ハクビシンの寝床vs「広々アライグマの寝床」に注目
ハクビシンとアライグマでは、寝床の広さに大きな違いがあります。アライグマは体を伸ばして眠れる直径60センチメートルの広々とした空間を必要とします。
「狭い隙間なら安全そう」と考えるハクビシンは、体幅の2倍程度の狭いすき間を好んで寝床にします。
一方、アライグマは「ゆったり休みたい」という習性があり、体を自由に動かせる広さを確保します。
まるで和室と洋室の違いのように、休息スタイルが全く異なるんです。
ハクビシンが布団で眠るような感覚なら、アライグマはベッドで寝るような感じ。
そのため、建物の構造でも見分けがつきます。
- ハクビシンの寝床:換気扇の隙間やトタン板の間など
- アライグマの寝床:物置の天井裏や倉庫の屋根裏など
- ハクビシンの痕跡:細長い爪痕や体毛の付着
- アライグマの痕跡:広範囲の足跡や巣材の散乱
タヌキの地上巣vs「高所のアライグマ巣」を確認
タヌキとアライグマでは、寝床を作る場所の高さが全然違います。アライグマは必ず高い場所を選びますが、タヌキは地上や地面の近くに巣を作ります。
「地面でのんびりしたい」というタヌキに対して、アライグマは「高いところで安全に過ごしたい」という習性があります。
まるで一戸建てとマンションの違いのように、住む階層が異なるんです。
それぞれの特徴をみてみましょう。
- タヌキ:竹藪の下や土手の窪み、倒木の下に巣を作る
- アライグマ:木の上や建物の2階以上、物置の天井に寝床を作る
- タヌキ:地面に這うように移動し、巣の周りに丸い足跡が残る
- アライグマ:垂直に登り降りする爪痕が残り、高所での足跡がある
猫の定住型vs「アライグマの移動型」を理解
飼い猫が同じ場所で寝るのに対し、アライグマは毎日のように寝床を変える習性があります。この違いを知っておくと、対策がグッと変わってきます。
猫は「ここが私の場所」と決めると、そこを長期間使い続けます。
でも、アライグマは「今日はここ、明日はあっち」とコロコロ寝床を変えるんです。
まるで、定住派と旅行好きの違いのよう。
具体的な違いを見てみましょう。
- 猫:寝床に毛が厚く堆積し、同じ場所を繰り返し使用
- アライグマ:複数の寝床を持ち、状況に応じて使い分け
- 猫:周辺に餌皿や水場を作る傾向がある
- アライグマ:寝床と餌場を意図的に離して確保する
5つの寝床チェックポイント

- 寝床周辺に「柑橘系の香り」で撃退効果!
- 風鈴の音で「警戒心」を刺激する方法
- 扇風機で「気流の変化」を起こして不快に
- 反射板で「日光の反射」を活用した対策
- 防虫ネットで「物理的な進入」を防止
寝床周辺に「柑橘系の香り」で撃退効果!
アライグマの寝床対策には柑橘系の香りが効果的です。特にみかんやレモンの強い香りは、アライグマの鋭い嗅覚を刺激して不快感を与えます。
「どうしてもあの場所で寝たくない」と思わせるほど、柑橘系の香りはアライグマにとって強力な撃退効果があるんです。
具体的な対策方法として、以下のような手順で香りを活用します。
- みかんやレモンの皮を乾燥させて、寝床の周りに置く
- 柑橘系の精油を染み込ませた布を、寝床から2メートル以内に配置
- 天然由来の柑橘系芳香剤を3日おきに交換しながら設置
- 柑橘系の植物を寝床付近にプランターで育てる
香りが弱まるとアライグマは警戒心を解いてしまいます。
また、柑橘系の香りには持続性が大切です。
「これくらいでいいかな」と思っても、毎日こまめに香りの確認と補充を行いましょう。
そうすることで、アライグマは「ここは居心地が悪い」と感じて、自然と別の場所へ移動していくというわけです。
風鈴の音で「警戒心」を刺激する方法
アライグマは静かな場所を好むため、風鈴の不規則な音は効果的な撃退方法となります。チリンチリンという予測できない音の変化が、アライグマの警戒本能を刺激するんです。
寝床対策として風鈴を活用する場合は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 風鈴は寝床から1メートル以内の距離に設置
- 複数の風鈴を異なる高さに配置して音の変化をつける
- 金属製の風鈴を使って澄んだ音を出す
- 強風時は取り外して騒音対策を忘れずに
「ここは落ち着かない」とアライグマに感じさせることで、2〜3日程度で寝床を放棄させることができます。
ただし、近所迷惑にならないよう音量には配慮が必要です。
「カランカラン」とうるさすぎない程度の心地よい音色を選びましょう。
風の強さによって音量が変わるので、天候に応じて設置位置を調整するのがおすすめです。
扇風機で「気流の変化」を起こして不快に
扇風機を使って空気の流れを変化させることで、アライグマの休息を妨げることができます。静かな場所を好む習性を利用した、効果的な対策方法なんです。
「どうして扇風機が効果的なの?」と思う方も多いはず。
それは、アライグマが一定の環境で休息を取りたがる習性があるためです。
扇風機による寝床対策のポイントは以下の通りです。
- 首振り機能を活用して不規則な風を作り出す
- 寝床から2メートル以内の距離に設置する
- 風速は弱めから中程度に設定する
- 防水対策をしっかり行う
- 24時間稼働させて環境変化を維持する
「ふわふわ」と揺れる空気の流れが、アライグマの快適な休息を邪魔してしまいます。
ただし、強い風は逆効果。
「びゅうびゅう」と音がうるさすぎると警戒心が強まってしまうので、静かな送風を心がけましょう。
電気代の管理も忘れずに行うことが大切です。
反射板で「日光の反射」を活用した対策
太陽の光を反射させることで、アライグマの休息を妨げる方法があります。暗い場所を好む習性を逆手に取った対策で、昼間の寝床を効果的に使えなくするんです。
具体的な反射板の設置方法は以下の通りです。
- 寝床の周囲に複数の反射板を配置する
- 太陽の動きに合わせて角度を調整する
- 光が直接当たる位置を日々少しずつ変える
- 近隣への影響を考えて反射方向を決める
「きらきら」と不規則に光が差し込むことで、アライグマは落ち着かない気持ちになります。
光の強さは天候によって変化するので、曇りの日は別の対策と組み合わせると良いでしょう。
「ちかちか」とした光の変化で、3日程度で寝床を放棄する効果が期待できます。
防虫ネットで「物理的な進入」を防止
目の細かい防虫ネットを活用すれば、アライグマの寝床への侵入を物理的に防ぐことができます。爪で引っかいても破れにくい、丈夫な素材を選ぶのがポイントです。
防虫ネットを使った効果的な設置方法をご紹介します。
- 網目の間隔が5ミリ以下の物を選ぶ
- 出入り口や窓の周りを隙間なく覆う
- ネットの端を2重に固定して補強する
- 破損しやすい角の部分を補強する
- 定期的に破れていないか点検する
「がりがり」と爪で引っかいても簡単には破れない、頑丈なネットを選びましょう。
設置後は週に1回の点検がおすすめ。
小さな破れでも見つけたら、すぐに補修することが大切です。
「ここは入れない」とアライグマに認識させることで、新しい寝床を探して移動していくというわけです。
寝床を見つけた時の注意点

- 寝床から「50メートル以上」離れて観察!
- 子育て中の巣には「特別な警戒」が必要
- 寝床対策は「近隣と情報共有」が重要
寝床から「50メートル以上」離れて観察!
アライグマの寝床を見つけたら、必ず50メートル以上の距離を保って観察します。「近づいて確認したい」という気持ちはわかりますが、むやみに接近するのは危険です。
寝床付近で物音を立てたり、急な動きをしたりすると、警戒心の強いアライグマがすぐに飛び出してくることがあります。
観察時は次の点に気をつけましょう。
- 双眼鏡を使って安全な距離から確認する
- 急な動きは避け、ゆっくりと静かに様子を見る
- 風上から観察し、においを察知されないよう注意する
- 写真撮影時はフラッシュ禁止で記録する
子育て中の巣には「特別な警戒」が必要
春から初夏にかけて見つけた寝床には、特に慎重な対応が必要です。この時期は子育て中の可能性が高く、母親アライグマの攻撃性が通常の3倍以上に高まっているんです。
「子どもがかわいそう」という気持ちで近づくのは絶対にやめましょう。
- 子どもの鳴き声が聞こえたら要注意
- 母親が威嚇するような声を出したら即退散
- 巣の周りをうろうろする素振りを見せたら危険信号
- 尾を膨らませて体を大きく見せる仕草も警戒サイン
寝床対策は「近隣と情報共有」が重要
アライグマの寝床対策は、ご近所と協力して進めることが大切です。「うちの対策がうまくいった!」と喜んでも、実は被害が隣家に移っているだけかもしれません。
地域ぐるみで次のような情報を共有しましょう。
- 寝床の発見場所と時期を地図に記録
- 対策の成功例と失敗例を話し合う
- 季節ごとの出没パターンを把握する
- 被害の拡大を防ぐための環境整備