アライグマの大きさはどれくらい?【体重8キロの力は侮れない】握力15キロと跳躍力で被害拡大

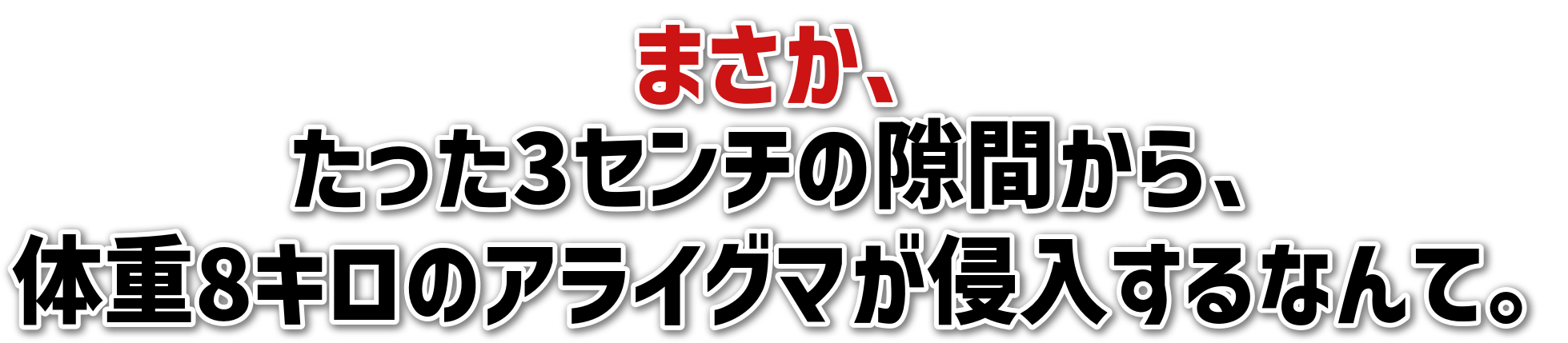
【疑問】
アライグマの体の大きさや力はどれくらいなの?
【結論】
成獣のアライグマは体重6〜10キロで体高30センチ、前足の握力は15キロにもなります。
ただし、都市部では餌が豊富なため、さらに2割ほど大きく成長する個体もいるので要注意です。
アライグマの体の大きさや力はどれくらいなの?
【結論】
成獣のアライグマは体重6〜10キロで体高30センチ、前足の握力は15キロにもなります。
ただし、都市部では餌が豊富なため、さらに2割ほど大きく成長する個体もいるので要注意です。
【この記事に書かれてあること】
アライグマの体の大きさ、想像以上かもしれません。- 成獣アライグマは体重6〜10キロと体高30センチまで成長
- オスはメスより体重が1.5倍も重く最大10キロに到達
- 前足は握力15キロで人の子供並みの破壊力を持つ
- 生後半年で体重4キロまで急成長して被害を引き起こす
- 都市部では豊富な餌により8キロ以上に成長する個体も
「せいぜい猫くらいでしょ?」なんて考えていませんか?
実は体重8キロの破壊力を持つ"小さな重量級"なんです。
さらに、握力は人間の子供並みの15キロ!
その力は、家屋への侵入時に大きな被害をもたらします。
体の大きさと力の実態を知れば、アライグマ対策の考え方が大きく変わるはず。
「かわいそうだから追い払うのはちょっと…」という気持ちも、その危険な実態を知れば変わってくるでしょう。
【もくじ】
アライグマの大きさと体重の基本

- 体重8キロの破壊力!人の子供並みの握力に要注意
- 大人の腕サイズと同じ「体高30センチ」の衝撃事実
- 小型犬サイズは危険!成獣の体格を甘く見るのはNG
体重8キロの破壊力!人の子供並みの握力に要注意
アライグマの体重は平均で8キロ。この重さは中型犬と同程度ですが、その破壊力は想像以上です。
人の子供と同じくらいの握力15キロを持つアライグマは、家屋に深刻な被害をもたらします。
「えっ、たかが8キロでしょ?」と侮ると大変なことに。
その力は金属製の物置を歪ませ、木材をばりばりと破壊するほど。
特に警戒すべきなのが、次の3つの破壊パターンです。
- 前足を使って金網をぐいぐいと引っ張り広げる
- 両手で板材をがりがりとかじって穴を開ける
- 体重を活かして天井裏の床板をどんどんと踏み抜く
「可愛らしい手をしているから大丈夫」という油断は大きな間違いです。
小さな隙間も、器用な手先と強靭な握力で広げられてしまうのです。
大人の腕サイズと同じ「体高30センチ」の衝撃事実
成獣のアライグマの体高は30センチ。これは大人の腕の太さとほぼ同じサイズです。
「たった30センチ」と思うかもしれませんが、この高さが被害を深刻化させる要因になっています。
なぜなら、この体高により次のような行動が可能になるからです。
- 換気口や排水溝の隙間に体を潜り込ませる
- 物置や倉庫の低い位置から侵入する
- 狭い天井裏でも自由に動き回る
体高30センチの体は、まるでゴムのように縮んだり伸びたりします。
「この隙間は無理でしょ」と思える場所でも、すうっと体を折りたたんで侵入してしまうんです。
体が小さい分、人が気づかない細かな隙間も見逃しません。
ぴったりと体を合わせて侵入するため、侵入経路の発見が遅れることも。
小型犬サイズは危険!成獣の体格を甘く見るのはNG
「小型犬くらいの大きさだから」と安心してはいけません。アライグマの体格は見た目以上の能力を秘めているのです。
体長60センチの成獣は、次のような脅威となる特徴を持っています。
- 全身の筋肉が極めて発達しており、力が強い
- 体の割に長い手足で、広い範囲に届く
- 柔軟な背骨で、体をくねらせて動く
なぜなら、アライグマは人を警戒する賢さと、逃げ場を探す判断力を持っているから。
追い詰められると、体格以上の力を発揮して反撃してきます。
夜行性で警戒心が強いため、昼間に見かけることは稀。
しかし、その体格を過小評価すると、家屋への被害は日に日に広がっていくのです。
年齢と性別による体格の特徴

- 生後6か月で体重4キロまで急成長する驚異の発達力
- オスは最大10キロ!メスより1.5倍の体重差に注目
- 繁殖期のメスは体重3割増!通常以上の警戒が必要
生後6か月で体重4キロまで急成長する驚異の発達力
アライグマの子供は急速に成長し、わずか半年で4キロの体重まで大きくなります。生まれたときはたった70グラムほどの小さな体ですが、とんとん拍子に大きくなっていくんです。
- 生後1か月:体重500グラム、ふらふらと歩き始める
- 生後3か月:体重2キロ、ぴょんぴょん跳ねて動き回る
- 生後6か月:体重4キロ、がっしりとした体つきに
しかし、子供と侮るのは大きな間違い。
すくすくと育つスピードは驚くほど速いのです。
オスは最大10キロ!メスより1.5倍の体重差に注目
アライグマは性別によって体格が大きく異なり、オスは6〜10キロ、メスは4〜7キロという体重差があります。がっしりとした体つきのオスは、見た目以上の力を持っているんです。
- オス:肩幅25センチ、胸囲45センチの筋肉質な体
- メス:肩幅20センチ、胸囲35センチのすらっとした体型
- 頭部:オスの方が2センチほど大きい
メスの大きさを基準に考えると、オスの力に対応できない防護柵になってしまいます。
繁殖期のメスは体重3割増!通常以上の警戒が必要
繁殖期のメスは通常の体重から3割も増加します。妊娠中のメスは食欲旺盛で、ごはんをもりもり食べて体重を増やしていくんです。
- 妊娠初期:体重1割増で動きは俊敏
- 妊娠中期:体重2割増でのっしのっしと歩く
- 妊娠後期:体重3割増で動きは緩慢に
さらに子育て中は警戒心が強まり、攻撃的な性質に変わることも。
通常以上の対策が必要になります。
生息地で異なる体格の比較

- 都市部vs山間部!餌場の違いで体重差2キロの衝撃
- 平地vs高地!標高による体格差は2割の差
- 沿岸部vs内陸部!魚介類で筋肉質な沿岸部の個体
都市部vs山間部!餌場の違いで体重差2キロの衝撃
都市部に住むアライグマは、豊富な餌のおかげで体重8キロを超える大きな個体がたくさんいます。山間部の個体との体重差は実に2キロもあるんです。
「なんで都会のアライグマってこんなに大きいの?」その理由は、実は私たちの生活にあります。
都市部では生ゴミや果樹が豊富で、アライグマは毎日たっぷりと栄養を摂取できます。
- 都市部の餌場:生ゴミ置き場、果樹園、家庭菜園、ペットの餌
- 山間部の餌場:木の実、野生の果実、小動物、昆虫
- 都市部の特徴:年中餌が豊富、カロリーが高い、簡単に手に入る
体重6キロほどの山間部の個体は、がさごそと木の上を移動したり、ぴょんぴょん岩場を飛び回ったりと、自然の中で暮らすのに適した体格なのです。
都市部の個体は餌が豊富な分、体重が重くなりすぎて動きが緩慢になりがち。
この特徴を知っておくと、防護柵の強度を決める時の参考になります。
平地vs高地!標高による体格差は2割の差
高地に住むアライグマは、平地の個体より体格が2割も小さいことをご存知ですか?標高1000メートル以上の場所では、餌が少なく気温も低いため、自然と体が小さくなるのです。
「寒いところのアライグマって大変そう」という声が聞こえてきそうですが、実は高地の個体には高地なりの生存戦略があります。
- 体重が軽い:素早く動ける、エネルギー効率が良い
- 体が小さい:寒さに強い、隙間に入りやすい
- 筋肉質:限られた餌を最大限活用できる
この体格差は気温と餌の量が大きく影響しているんです。
寒い場所では体を小さく保つことで、少ない餌でも効率よく生きていけるというわけです。
高地の個体は体が小さい分、家屋への侵入口も小さくて見逃しやすいので要注意。
体重は軽くても破壊力は十分なので、侮れません。
沿岸部vs内陸部!魚介類で筋肉質な沿岸部の個体
沿岸部に住むアライグマは、魚介類が豊富な食事のおかげで、がっしりとした筋肉質な体つきをしています。内陸部の個体より1〜2キロも重いんです。
「え?魚を食べるの?」と驚く方も多いはず。
実は、アライグマの手先は驚くほど器用で、ざぶざぶと水に浸けて魚をつかまえることができます。
- 沿岸部の餌:魚、カニ、貝類、水生昆虫
- 内陸部の餌:果実、木の実、小動物、昆虫
- 沿岸部の特徴:タンパク質が豊富、年中餌が安定
これは魚を捕まえる時に必要な力が自然と備わったものです。
内陸部の個体が体重6〜7キロなのに対し、沿岸部では7〜9キロになることも。
この体格差は防護対策にも影響します。
沿岸部では特に、がっしりとした作りの柵や、丈夫な収納ボックスが必要になってきます。
体格から見る5つの危険な特徴
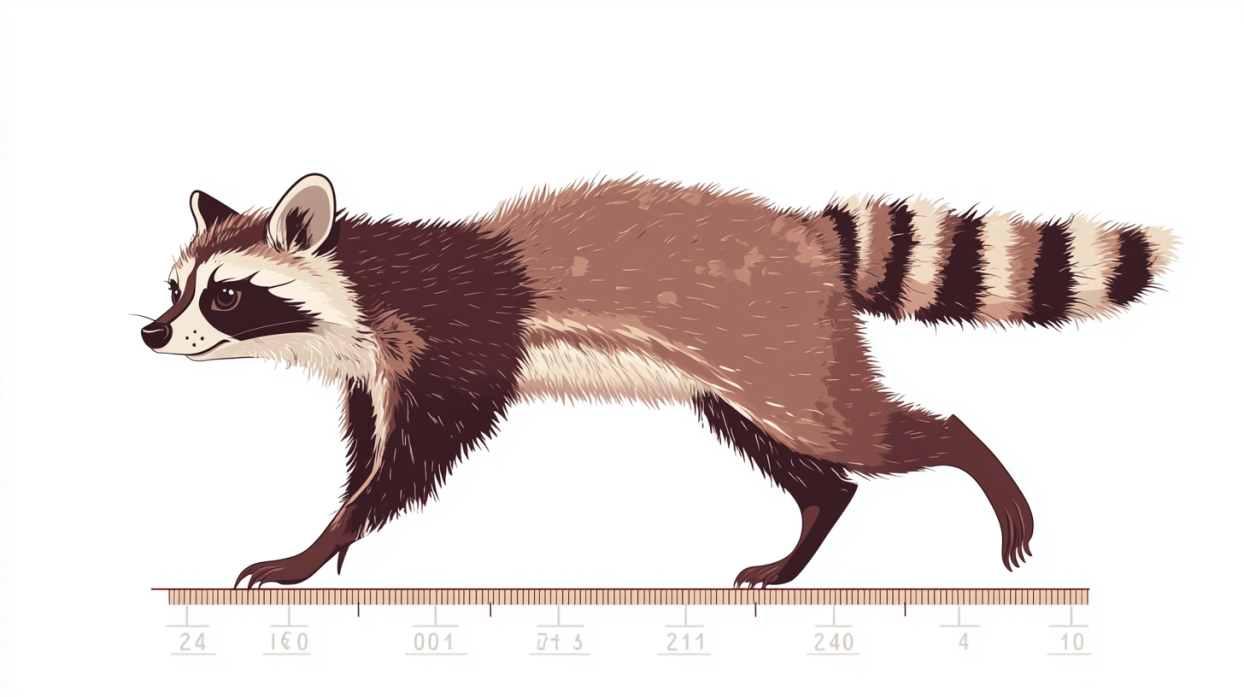
- 前足の握力15キロ!金属製の柵も破壊する怖さ
- 8センチの手のひら!器用な指先で隙間から侵入
- 体高30センチの跳躍力!1メートルの柵も楽々越え
- 2センチの鋭い犬歯!かじられた被害は修理必須
- 季節で変動する体重!秋は2割増の最強期に警戒
前足の握力15キロ!金属製の柵も破壊する怖さ
アライグマの前足の握力は、なんと人間の子供と同じくらいの15キロもあるのです。「そんな小さな動物に何ができるの?」と侮ってはいけません。
この握力の強さは、私たちの想像をはるかに超えています。
例えば、お弁当箱のふたを開けるのに必要な力が約2キロ。
アライグマの握力はその7倍以上なんです。
実際の被害も深刻です。
- 薄い金属製の柵をぐにゃりと曲げる
- 針金を切断したような跡が残る
- 木製の柵に爪跡と共に深いくぼみができる
- 物置の扉の隙間を広げてしまう
特に危険なのは、この力を器用な前足の動きと組み合わせて使うこと。
まるでペンチのように物をつかんでねじり取ることができるんです。
さらに怖いのは、この握力で一度つかまれると簡単には離してくれないということ。
「ガシッ」としっかりと掴んで離さない習性があり、防護柵の設置には握力15キロに耐える強度が必要不可欠というわけです。
8センチの手のひら!器用な指先で隙間から侵入
アライグマの前足は、人間の子供の手のひらとほぼ同じ大きさの8センチ。この意外な事実を知らないと、適切な対策が取れません。
人間の手そっくりの器用な前足を持つアライグマは、私たちの想像以上に細かい作業ができるんです。
- 引き戸の取っ手を握って開ける
- 網戸の小さな穴を広げて侵入
- ゴミ箱の留め具を外す
- ペットフードの袋を器用に開封
「こんな小さな隙間からは入れないでしょう」という油断が大きな被害につながります。
実は、手のひらが入る大きさの隙間さえあれば、体を器用にくねらせて侵入できてしまうのです。
さらに怖いのは、この手先の器用さを記憶する能力の高さ。
一度成功した侵入方法は忘れません。
「ガチャガチャ」と物音がしたと思ったら、もう家の中。
そんな事態になる前に、手のひらサイズの隙間を全てふさぐ必要があるというわけです。
体高30センチの跳躍力!1メートルの柵も楽々越え
アライグマは体高30センチと小柄に見えますが、その跳躍力は驚くべき強さです。立ち上がると体長は60センチにもなり、さらに垂直跳びで1メートル以上跳び上がることができます。
この跳躍能力がもたらす被害は深刻です。
- 庭の低い柵を軽々と飛び越える
- 物置の屋根まで一気にジャンプ
- ベランダの手すりを乗り越えて侵入
- 木の枝から屋根へと飛び移る
実は、この跳躍力と体の柔軟性を組み合わせることで、見た目以上の高さを越えられるんです。
さらに注目すべきは、この跳躍力と着地の正確さ。
「ぴょんっ」と軽やかに飛び上がり、狙った場所にピタリと着地。
まるで猫のような身のこなしで、私たちの予想をはるかに超える場所に到達してしまうというわけです。
2センチの鋭い犬歯!かじられた被害は修理必須
アライグマの歯、特に犬歯の長さは2センチもあり、その鋭さは野生動物の中でも特筆ものです。この歯の力は想像以上の破壊力を持っています。
被害の特徴を見てみましょう。
- 木材に深さ2センチの傷跡が残る
- 物置の扉に歯形の穴が開く
- 換気口の金網が噛み切られる
- 雨どいに歯型の跡がつく
例えば、私たちが缶詰を開けるのに缶切りを使うように、アライグマは鋭い歯で物を「ガリガリ」とかじって穴を開けていきます。
一度かじられた被害箇所は、見た目以上に深刻な状態になっているのが特徴。
表面的な傷に見えても、構造部分まで達していることも。
「ちょっとした傷だから」と放置すると、雨漏りの原因になったり、さらなる被害を招いたりしてしまうんです。
季節で変動する体重!秋は2割増の最強期に警戒
アライグマの体重は、季節によって大きく変動します。特に秋は通常の2割増しとなり、8キロを超える個体も珍しくありません。
季節による変化を見てみましょう。
- 春:基本の6キロ程度で活動開始
- 夏:7キロ前後まで徐々に増加
- 秋:8キロ以上に急激な増加
- 冬:7キロ程度まで若干減少
餌を求めて行動範囲を広げ、体重も最大になるため、被害も深刻化します。
例えば、通常の柵なら持ちこたえられる力でも、体重が増えた秋には「みしみし」と軋んで壊れてしまうことも。
「今までは大丈夫だった」という油断が、思わぬ被害を招くというわけです。
さらに、この時期は冬に向けた食欲が最も旺盛になる時期とも重なるんです。
体格を考慮した対策のポイント

- オスの最大サイズ「体重10キロ」に耐える防護柵
- 前足サイズ「8センチ」より小さい隙間を全て封鎖
- 体高30センチの跳躍力に負けない「1メートルの壁」
オスの最大サイズ「体重10キロ」に耐える防護柵
アライグマの体重は性別によって大きな差があり、オスは最大で10キロもの体重になります。「たかがアライグマ、この柵で十分でしょ」なんて考えていると大変なことに。
体重10キロの力で押し倒されたり、へし折られたりする被害が続出しているんです。
防護柵を選ぶときは、以下の3点に注意が必要です。
- 柵の支柱は地中30センチまでしっかり埋める
- 柵と柵の接合部は二重に補強する
- 支柱と支柱の間隔は50センチ以下にする
前足サイズ「8センチ」より小さい隙間を全て封鎖
アライグマの前足は人間の子供の手のように器用で、長さ8センチ、幅6センチの大きさがあります。「この小さな隙間からは入れないはず」と思っても、すりすりっと体をくねらせて侵入されることも。
隙間を見つけたら、以下の対策が必要です。
- 換気口には目の細かい金網を取り付ける
- 壁の亀裂は直径7センチ以下でも補修する
- 配管まわりの隙間も完全に塞ぐ
前足を器用に使って登っていくので、壁との接合部もしっかり点検しましょう。
体高30センチの跳躍力に負けない「1メートルの壁」
成獣のアライグマは体高が30センチもあるため、立ち上がると人の膝上まで届きます。「この高さなら飛び越えられないはず」と思っても、ぴょんぴょんと軽々と越えていってしまうことも。
効果的な対策には以下のポイントがあります。
- 防護壁は地上から1メートル以上の高さを確保
- 壁の上部は内側に30度以上の角度をつける
- つかまりやすい突起物は極力なくす