アライグマのジャンプ力はどれくらい?【垂直に1メートル以上】建物侵入を防ぐ5つの新発想

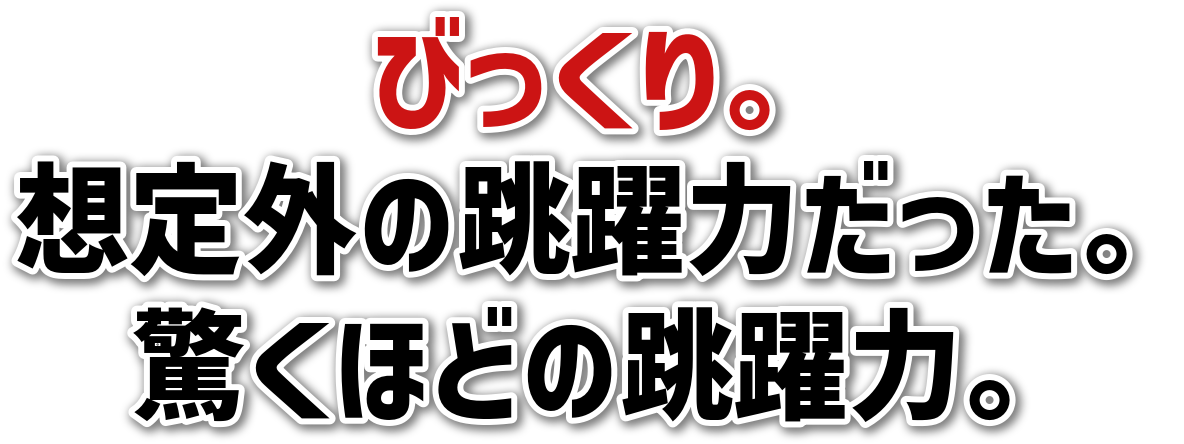
【疑問】
アライグマの跳躍力で家に侵入される可能性はどれくらいあるの?
【結論】
垂直に1.2メートル、助走をつければ2メートルの距離を跳躍できるため、一般的な柵や塀では侵入を防げません。
ただし、傾斜板の設置や回転式カバーなどの対策を組み合わせることで、効果的に侵入を防ぐことができます。
アライグマの跳躍力で家に侵入される可能性はどれくらいあるの?
【結論】
垂直に1.2メートル、助走をつければ2メートルの距離を跳躍できるため、一般的な柵や塀では侵入を防げません。
ただし、傾斜板の設置や回転式カバーなどの対策を組み合わせることで、効果的に侵入を防ぐことができます。
【この記事に書かれてあること】
アライグマの脅威は、その驚異的な身体能力にあります。- 成獣の垂直跳びは1.2メートルに到達する驚異の跳躍力
- 体重8キロでも0.3秒で方向転換できる俊敏性を持つ
- 春から夏にかけて運動能力が最大化する危険な時期
- 小型犬の1.5倍、タヌキの2倍という圧倒的な跳躍能力
- 傾斜板や回転カバーなど5つの新発想で効果的に侵入を防止
特に跳躍力は想像を超えるもので、なんと垂直に1.2メートルもジャンプできるんです。
「え?そんなに跳べるの?」と驚かれる方も多いはず。
でも、これが現実なんです。
体重8キロの成獣でも、バネのような瞬発力で軽々と柵を飛び越えてしまいます。
低い防護柵で安心していると、思わぬ被害に見舞われかねません。
今回は、アライグマの跳躍力の実態と、効果的な対策方法をご紹介します。
【もくじ】
アライグマのジャンプ力と到達可能な高さ

- 垂直に1.2メートル!アライグマの「驚異の跳躍力」を実測
- 成獣でも体重8キロなのに「バネのような瞬発力」に要注意
- 低い柵で満足は危険!「想定以上の跳躍力」に警戒を
垂直に1.2メートル!アライグマの「驚異の跳躍力」を実測
アライグマは体重8キロの成獣でも、垂直方向に1.2メートルもの高さまで跳び上がることができます。アライグマの跳躍力はすごいんです。
その場から一気に跳び上がる様子は、まるでバネ仕掛けのおもちゃのように軽やかです。
「そんな高くまで跳べるはずがない」と侮っていると、とんでもない事態に。
地面からすーっと姿勢を低くして、ぐっと後ろ足に力を込めたかと思うと、ぴょーんと垂直に跳び上がります。
その瞬発力たるや驚くべきもの。
- 後ろ足の筋肉が発達していて、体重の5倍もの力を生み出せる
- 体の大きさの2倍以上の高さまで、楽々と跳躍可能
- 着地の衝撃を吸収する足裏のクッション性が優れている
「まさか我が家までは…」なんて油断は大敵です。
低い柵や塀は、アライグマにとってはちょっとした踏み台程度の障害物にすぎないのです。
成獣でも体重8キロなのに「バネのような瞬発力」に要注意
アライグマは体重8キロほどの小柄な体格ながら、その瞬発力は驚くべきものです。まるでゴムまりのような跳躍の秘密は、体重のわりに発達した足の筋肉にあります。
「こんな小さな動物に何ができるの?」なんて考えていると、とんでもない誤算に。
- 体格のわりに太い後ろ足の筋肉が、爆発的な力を生み出す
- 体重が軽いぶん、身のこなしが素早くて正確
- 四肢の関節が柔軟で、様々な体勢からの跳躍が可能
ぴょんぴょんと連続して跳び上がる様子は、まるで運動場で遊ぶ子どものよう。
しかも、狙った場所に的確に着地できる精密な身体能力を持っているんです。
これほどの運動能力を持つアライグマは、低い塀や柵をものともしません。
「うちの柵なら大丈夫」という思い込みが、思わぬ被害を招くことになってしまうのです。
低い柵で満足は危険!「想定以上の跳躍力」に警戒を
一般的な高さの柵や塀では、アライグマの跳躍力を防ぐことはできません。「うちの柵は1メートルあるから安心」なんて考えていませんか?
それは大きな誤算です。
アライグマは垂直跳びだけでなく、助走をつけることで更に高い場所まで到達できる能力を持っています。
ぎゅっと体を縮めて、すーっと忍び寄り、だーっと走り出したかと思えば、ぴょーんと跳び上がる。
その一連の動きはわずか数秒。
気づいた時には手遅れです。
- 助走から跳躍までの動作が素早く、対応が難しい
- 体の大きさを活かして、狭い場所でも助走が可能
- 物置や樹木を足場にして、更に高所まで到達できる
- 柵の隙間や突起を器用に利用して、よじ登る技も持つ
防護策は想定以上の高さが必要というわけです。
侵入を狙う時の動きと特徴

- 春から夏にかけて「運動能力がピーク」に到達!
- 夜間の静寂時に「最も活発な動き」を見せる習性
- 助走から跳躍までわずか「0.3秒の俊敏性」に驚愕
春から夏にかけて「運動能力がピーク」に到達!
気温の上昇とともに、アライグマの身体能力は急激に高まります。とくに春から夏にかけて、運動能力は年間で最も活発になるんです。
この時期は、次のような特徴が見られます。
- 体が軽くしなやかで、跳躍力が通常の1.2倍にアップ
- 冬場の体重が減少して、動きがすばしっこくなる
- 運動時間が長くなり、持久力も向上
- 餌を探す行動範囲が広がり、活動量が増える
でも春先は要注意。
冬を越えた個体が新たな住処を必死に探している時期なので、侵入の危険性が格段に高まってしまいます。
夜間の静寂時に「最も活発な動き」を見せる習性
日が沈んでから2時間後、それがアライグマの活動開始時刻です。静かな夜の闇に紛れて、すばやい動きを見せ始めます。
この時間帯は、下記のような特徴的な行動パターンが現れます。
- 物音を立てずにそろりそろりと移動する
- 周囲の様子をじっくり確認しながら活動
- 侵入可能な場所を念入りにチェック
- 人の気配がないことを確認してから行動開始
静寂に包まれた住宅街を、まるで忍者のようにすいすいと移動していくのです。
助走から跳躍までわずか「0.3秒の俊敏性」に驚愕
動き出してからジャンプするまでの速さに、思わずぎょっとしてしまいます。わずか0.3秒という驚くべき素早さで、助走から跳躍までを完了させてしまうんです。
この俊敏性には、次のような特徴があります。
- 方向転換が一瞬で、急な動きの変化が得意
- 体の向きを変えずに横方向への跳躍も可能
- 着地と同時に次の動作に移れる
- 暗闇でも正確な距離感で跳躍できる
ジャンプ力で比較する危険度

- アライグマvs小型犬の跳躍力!1.5倍の衝撃的な差
- アライグマvsタヌキの運動能力!2倍の実力差に注目
- アライグマvsネコの身体能力!互角の跳躍に警戒を
アライグマvs小型犬の跳躍力!1.5倍の衝撃的な差
「まさか、うちの犬より跳べるなんて…」。そう思われる方も多いのではないでしょうか。
実は、アライグマは同じ体重の小型犬と比べて、なんと1.5倍もの跳躍力を持っているのです。
体重8キロのアライグマと、同じく8キロの小型犬を比べてみましょう。
犬が垂直方向に80センチメートルほど跳躍するのに対し、アライグマは1.2メートルまで跳び上がることができます。
この差は侮れません。
また、跳躍の特徴も大きく異なります。
- 犬は全身でどすんと跳ぶのに対し、アライグマはしなやかにすいっと跳躍
- 犬は着地時の衝撃が大きいのに対し、アライグマは音もなく着地
- 犬は跳躍前に態勢を整えるのに対し、アライグマは突然跳躍
アライグマは獲物を捕まえたり、敵から逃げたりするために、瞬発的な跳躍を得意としているんです。
「うちの犬なら追い払えるはず」という考えは、とても危険というわけです。
アライグマvsタヌキの運動能力!2倍の実力差に注目
「タヌキと同じような動物でしょ?」なんて思っていませんか。実は、アライグマはタヌキの2倍もの跳躍力を持っているのです。
同じような姿かたちをしているように見えるタヌキとアライグマですが、運動能力には大きな差があります。
タヌキが垂直方向に60センチメートルほどしか跳べないのに対し、アライグマは1.2メートルまで跳び上がれます。
さらに、連続跳躍の能力も違います。
タヌキがぴょんぴょんと単発的な跳躍しかできないのに対し、アライグマはとんとんとリズミカルに跳び続けることができます。
その理由は、前足の特徴にあります。
- タヌキは歩行重視の肉球構造
- アライグマは跳躍に適した筋肉配置
- アライグマは器用な前足の使い方が可能
「タヌキ対策と同じでいいや」という考えは、大きな間違いなんです。
アライグマvsネコの身体能力!互角の跳躍に警戒を
猫の身体能力といえば、誰もが認める高い運動神経。でも、アライグマは体重あたりの瞬発力で、なんと猫と互角の跳躍力を持っているのです。
体重3〜4キロの猫が垂直方向に1.5メートルほど跳べるのに対し、その2倍以上の体重があるアライグマでも1.2メートルまで跳躍できます。
これは、体重あたりの力で見ると、ほぼ同等の能力といえるでしょう。
驚くべきことに、動きのしなやかさも猫に引けを取りません。
- 着地時の衝撃吸収がぷにぷにと柔らかい
- 体をくるりと回転させて姿勢を立て直せる
- 狭い足場でもすいすいと移動できる
- 細い枝でもふわっと着地できる
むしろ、猫と同等の身体能力を持つ野生動物だからこそ、より慎重な対策が必要というわけです。
5つの新発想で侵入防止を実現

- 斜め45度の「傾斜板設置」で着地ポイントを消滅!
- 回転式の「防護カバー」で登攀を完全ブロック!
- 砂利敷きの「不安定地帯」で助走を阻止!
- ネット張りの「斜め60度」で足場作りを防止!
- 支柱間の「揺れる紐」で心理的バリアを形成!
斜め45度の「傾斜板設置」で着地ポイントを消滅!
建物の壁面に取り付ける傾斜板は、アライグマの侵入を防ぐ画期的な対策方法です。傾斜板は「どうしても足場が確保できない!」とアライグマを困らせる仕組みなんです。
傾斜角度が45度以上あると、どんなに力強く跳躍しても着地する場所がなくなってしまいます。
設置のポイントは以下の3つです。
- 雨どいの周辺を重点的に覆う
- つるつるした素材を使用する
- 壁との隙間をなくす
「ここなら登れそう」とアライグマが目をつける場所だからです。
そのため、雨どいの両側50センチまでは必ず傾斜板で守りましょう。
材質選びも大切です。
アライグマは「爪でひっかけて」「体を支えて」「少しずつ上る」という技を使うので、爪が引っかからない素材がおすすめ。
アルミや硬質プラスチックなら、ツルツルとした表面で爪も効きません。
回転式の「防護カバー」で登攀を完全ブロック!
柵の上部に取り付ける回転式の防護カバーは、アライグマの登り越えを不可能にする新しい発想の防具です。直径10センチ以上の筒状のカバーが、アライグマの動きを完全に封じ込めます。
「掴もうとしても、くるくる回って手が滑る」という状態を作り出すのです。
効果を高める工夫として、次の点に気をつけましょう。
- 表面は滑らかな素材を選ぶ
- 軽い材質で自由に回転させる
- 雨の影響を考えて重さを調整する
- 両端はしっかり固定する
アライグマが「えいっ」と飛びついた瞬間、自分の体重で回転し始め、バランスを崩して落下してしまうのです。
この防護カバーは、冬場の凍結にも強い樹脂製がベスト。
「カチカチに固まって回らなくなる」心配がないため、一年中安定した効果を発揮します。
砂利敷きの「不安定地帯」で助走を阻止!
物置や倉庫の周りに敷く丸い砂利は、アライグマの助走と踏ん張りを封じる効果的な対策です。粒の大きさは直径5センチ程度がおすすめ。
「ガラガラ」と音を立てて転がる丸い砂利は、アライグマに「ここは危険!」という警戒心を与えます。
効果を高めるコツは以下の通りです。
- 砂利は30センチ以上の幅で敷く
- 定期的に表面を耕して固まりを防ぐ
- 雨どいの下は特に念入りに整える
「しっかり踏ん張って跳躍しよう」と思っても、足元がフワフワして力が入りません。
この方法の良いところは、見た目の美しさも保てること。
「庭の景観を損なわずに済む」と、多くの家庭で好評なんです。
お手入れも簡単で、月に一度「サクサク」と表面を掻き混ぜるだけでOKです。
ネット張りの「斜め60度」で足場作りを防止!
建物の周りに張る防護ネットは、斜めに設置することで効果が倍増します。地面から60度以上の角度をつけることで、アライグマは体を支えられなくなるのです。
この方法のミソは、アライグマの得意技を逆手に取ること。
通常なら「爪でネットを引っかけて」「少しずつよじ登る」という技を使うのですが、斜めに設置すると体重で「ずるずると滑り落ちる」状態になります。
設置時の重要ポイントをご紹介します。
- 支柱は1メートルごとにしっかり固定
- ネットの端は地面に埋め込む
- 目合いは5センチ以下を選ぶ
- 張り具合は「ピン」と強めに
「びよーん」と伸びる柔らかいネットは、すぐにゆるんでしまうためNGです。
支柱間の「揺れる紐」で心理的バリアを形成!
支柱の間に張る細い紐は、アライグマに心理的な圧迫を与える効果的な防護策です。紐は1メートルおきに設置します。
「ふわふわ」と揺れる不安定な紐を見ると、アライグマは本能的に警戒心を抱くのです。
これは野生動物の「未知のものを避ける」という習性を利用した方法なんです。
より高い効果を得るためのポイントは以下の通り。
- 紐は風で良く揺れる細めのものを使用
- 夜間でも目立つ明るい色を選ぶ
- 複数の高さに設置する
- 張り具合は「ゆるゆる」と余裕を持たせる
「誰でも手軽に始められる」と評判です。
定期点検も「ぎゅっと」引っ張って張り具合を確認するだけでOK。
費用対効果の高い対策方法といえます。
ジャンプ力対策での注意点

- 建築基準法に注目!「高さ制限」をクリアする防護策
- 近隣への配慮!「日照と景観」を損なわない工夫
- 防護材の端部処理!「怪我防止」の安全対策
建築基準法に注目!「高さ制限」をクリアする防護策
防護柵の設置には建築基準法の制限があります。「せっかく設置したのに撤去を命じられた…」なんてことにならないよう、しっかり確認しましょう。
まずは自治体によって異なる高さ制限を把握することが重要です。
「基準を知らなかった」では済まされません。
- 住宅地での一般的な制限は地上から2.2メートルまで
- 道路に面した場所では見通しを確保するため1.8メートルまで
- 角地では交差点から2メートルの範囲は1.2メートルまで
ガタガタと音を立てながら歩く様子は要注意のサイン。
すばやく対策を。
近隣への配慮!「日照と景観」を損なわない工夫
防護柵の設置は近隣との関係も大切です。「うちは安全になったけど、お隣が困ってる…」そんな事態は避けたいものです。
日照への影響を最小限に抑えるポイントをおさえましょう。
- 金属製の柵は網目状のものを選んで光を通す
- 植物を活用する場合は成長を管理して高さを抑える
- 設置位置は敷地の内側に余裕を持たせる
スッキリとした見た目で、かつ効果的な防護を実現する工夫が求められます。
防護材の端部処理!「怪我防止」の安全対策
防護材の端部は思わぬ事故の原因になります。「子どもが遊んでいてケガをした」なんて心配はしたくありません。
安全な端部処理のチェックポイントを確認しましょう。
- 突起物は丸みのあるカバーで包む
- ネットの切れ端は折り返して固定する
- 金属部分は防錆処理を徹底する
キチンと処理して、子どもやお年寄りも安心な環境を作りましょう。
定期的な点検もお忘れなく。